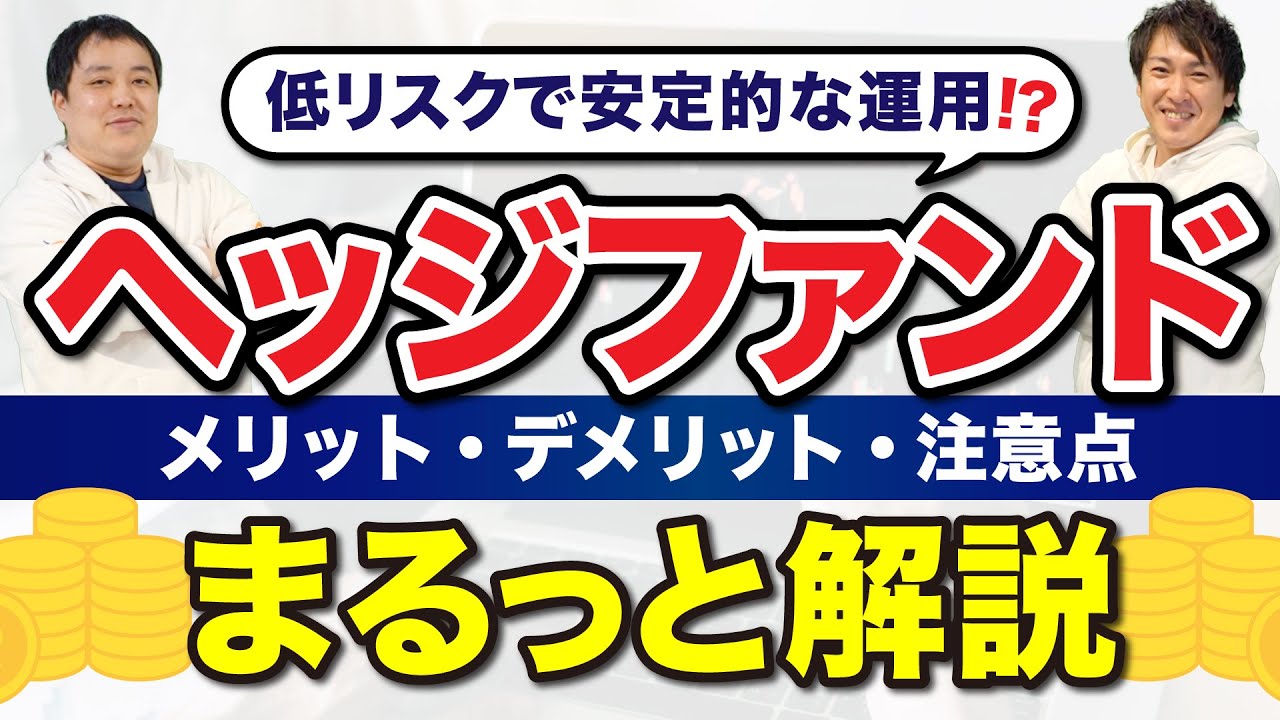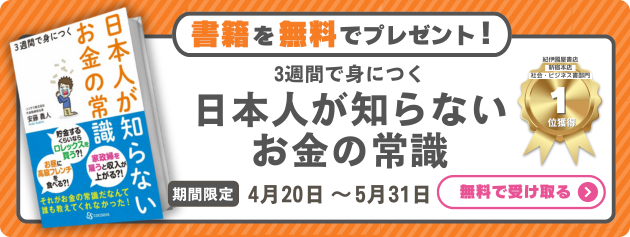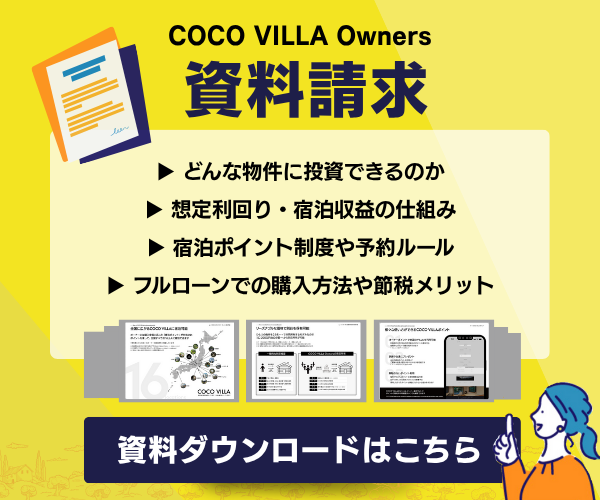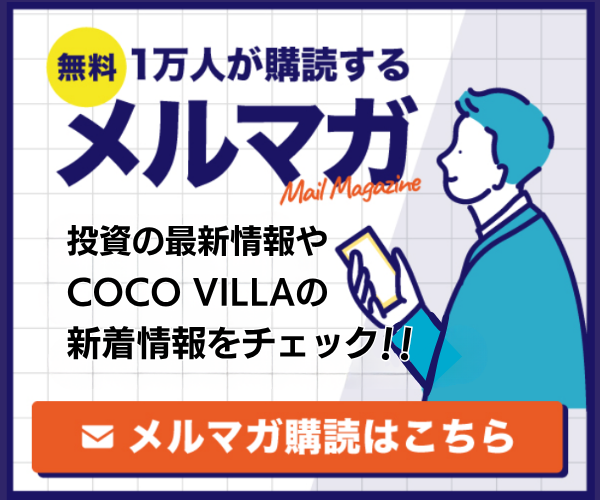ヘッジファンドってナニ?特徴を解説


社長、金融商品の中でたまに耳にする「ヘッジファンド」という投資について。
資産形成チャンネルでも名前は出てきたことはありますが、ヘッジファンドとは具体的にどんなものなんですか?

例えば株式投資や債券の投資。
こういった投資はだいぶ一般的な投資ですよね?

金融商品の中で1番聞く投資ですよね。

ヘッジファンドはこれらとは全く違っています。
少し難しい言葉で言うと「オルタナティブ投資」というカテゴリなんです。


オルタナティブ投資?
初めて聞きました。

たまに経済新聞を見ていると、カタカナで出てきます。
「非伝統的資産」と言われているのですが…
不動産だったり、金やREITなど伝統的な昔からあるような運用ではないもの。
その中の1つが、ヘッジファンドと呼ばれているものです。
ヘッジファンドは読んで字のごとく「リスクをヘッジする」ということです。
“リスクヘッジ”という言葉がありますよね?
そのためのファンドです。
様々な取引の手法を駆使し、市場が上がったとしても暴落したとしても、◯◯ショックが起きたとしても…


絶対に勝てる!というような…?

「絶対に勝てる!」とは言ってはいけないと思いますが…
普通の投資信託は相場が上がったり下がったりという、この影響を当然受けます。
相場が一方向に動いた時だけ利益が出る仕組みになってるものがほとんどです。
上がったら儲かる、下がったら儲かるような仕組みもあったりします。
ただ、ヘッジファンドはウネウネしてる相場だったとしても…

そういうコンセプトのもと、開発されているものがほとんどです。
動画で確認したい方はこちら
ヘッジファンドのメリットとデメリットは?


ヘッジファンドのメリットや強みは今お話いただいた部分でしょうか?

そうですね。
絶対収益!という言葉をよく使いますが…
どんな状況であっても収益を目指せるというところは大きなメリットの1つです。
もう1つ挙げるとすると、あらゆる伝統的資産。
皆さんがよく知っているような金・プラチナの価格や株式の価格、こういったものと連動しない動きをします。

色々な相場を見ていなかったとしても、ヘッジファンドマネージャーという方々にお金を預けてるわけなので、その状態で安定的に収益を上げてくれる。
ここが特徴です。

逆にデメリットを挙げるとすると…?

「伝統的資産とは連動しません」という話をしましたが、細川さんに「ヘッジファンドは何で運用してるのですか?」と聞かれたら、僕は今答えられないんですよ。

どういうことですか?

これがデメリットの大きなポイントかもしれません。
投資信託なら、ロボティクスファンドと言ったらハードウェアの物理的なロボット、ソフトウェアのロボット、最近だとチャットGPTなど…
いろんなロボットによってこのファンドが組成されてますよと教えてくれますよね?
だから、ロボティクスファンドに投資する。

一切見せてもらえないのです。
機動的に運用していて、資産の入れ替えペースも早いです。
ヘッジファンドマネージャーと呼ばれる方々が、その時々に応じて資産の入れ替えをガンガンやるのです。

説明ができないぐらい、色々と回してるという理由でしょうか?

そうなんですよ。
イメージとしては投資がものすごく上手な友達にお金を預けて運用してもらうみたいな…

中身というより、こちらで増やすから、お前は黙っていろと…

面白いのが報酬形態です。
もしかしたらデメリットと言われるかもしれませんが、手数料が高いのです。
ヘッジファンドは1,000万円単位で預けるのですが、やっているだけで年2%かかります。
つまり、20万円の信託報酬がかかる。
普通の投資信託はこれだけの手数料ですよね?

はい。そうですね。

しかし、ヘッジファンドはこれだけではありません。
私の1,000万円が1年で1,300万円になったとしましょう。
300万円が増えているので、30%も伸ばしてくれた。
ここから20%(60万円)をまた手数料として持っていきます。

そうなると結構高いですね…

手数料率で言うと普通の投資信託とは比べ物にならないぐらい高いのです。
しかし、1,000万円を回してもらうことだけで20万円かかる。
これが信託報酬です。
そして増えた300万円の中から20%の成功報酬だったとしましょう。
300万円から、60万円を抜きます。
そうすると240万円になって、そこから信託報酬の20万円を引く。
最終的に220万円、これが私のリターンなのです。
「1年で22%増えているよね?」と。
手数料引き後のこの数字で目標リターンを超えていれば、別にいくら取ってもらってもいいじゃない?と。
知り合いで、投資が上手い人がいたとして「とにかく20%毎年資産増やすよ!」と。
そして結果、その方が実は50%儲けていたとしても、その人にお願いしない限り20%は儲からないのですから。

まあそうですね。

だったらいいよねというぐらい、強気な考え方で手数料を取ります。
デメリットをまとめると…

あとねもう1つ。
これはそんなに大きなデメリットではありませんが…

投資信託のようにワンクリックで1日後、2日後に戻るという話ではありません。
1ヶ月くらいかかったりもします。

ヘッジファンドはいくらからできるの?
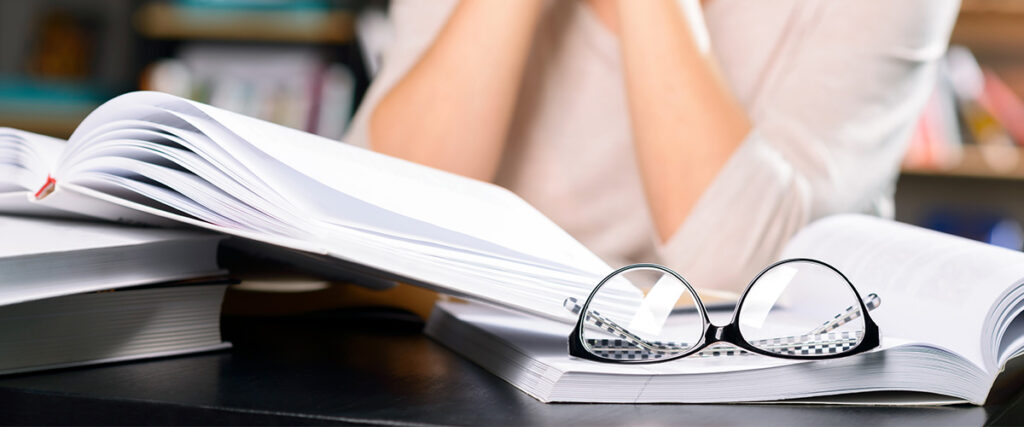

先ほど社長は1,000万円から運用できるとお話していましたが…
基本的にはどんな方がそういったヘッジファンドで投資されているのですか?

富裕層の方が多いです。
例えばうちのIFAで1,000万円単位で紹介していますが、これはかなり小口に分けてもらっているのです。

1,000万円台でも小口なのですね。

本来、大手証券からヘッジファンドを買うとなると、1億円ぐらいのロットだったりするのです。
世界の富裕層は本当に何百億円も何兆円も持ってる方々もいますよね。
イーロン・マスクは、もう20兆円くらいの資産があると思いますが…
そういう方々は高い手数料を払ってでも、大きなリターンがある。
なので、自分の資産のうち30%、40%ぐらいをヘッジファンドに預けているような方もいらっしゃいます。
1兆円を預けていたとしたら、5%だったとしても500億円ですよ?

すごいですね…


他に投資するのは、世の中でお金を持っている機関投資家。
どういうところがあるかというと、大学の基金。
大学って資産運用をしているんですよ。
日本の大学も資産運用しています。

それは授業料から…?

今までの収益を集めたものを運用している。
例えば、ハーバード大学は7兆円ぐらいの資産があるらしいのですが、3割以上をヘッジファンドで回してるらしいのです。
トータルリターンは年10%以上と…

すごいですね。

すごいよね、7,000億円入ってますね。
ヘッジファンドには様々な種類のものがありますが、ほぼマイナスを出さず30年平均で10%以上を複利で運用してるファンドもあったりする。

富裕層の方はそういった利回りの高い投資を皆さんやっているのですね。

運用する側としても、100万円で何千口を集めるより、10億円を1人の投資家で運用していただく方が楽ですよね?
毎月レポートも発行するので、1,000人に発行するよりも1人に送りたいですよね。

取り組む時に注意すること


この商品に取り組む時の注意点はありますか?


1番は運営母体がちゃんとしてるかどうか。
これは投資ですから、仮に自分が1,000万円をそのファンドに入れたとしましょう。
「運用が悪かった、ごめんなさい」と言われたら0になるリスクを抱えているわけです。

運用次第ですもんね、もちろん。

そうなんですよ。
では「どういうヘッジファンドだったらいいんだ!」という話ですが…
今の時代は色々な投資詐欺の話がありますよね。
「うちのヘッジファンドに集めましょう!」と言って、お金を集めている会社もいっぱいあります。
その方が言ってるヘッジファンドは多分、私が知っているヘッジファンドではありません。
私が知っているヘッジファンドは「バークレイズ」や「UBS」や「ブラックロック」だったり…
もう世界の名立たる金融機関や「ゴールドマンサックス」だったり。
こういったところが組成しているようなヘッジファンドばかりです。
こういったものっては破綻リスクがものすごく少ない。
ではどこを見分ければいいかというと…


「1年間だけやりました。結果は10%でした。」だったら…
来年マイナス10%かもしれませんよね?

その1年の運用が、たまたまかもしれないですよね。

いや、ほんとにそうなのです。
そもそもコロナ禍は毎年アメリカのNASDAQは20%、30%伸びたりしていました。
となると、長い期間安定的にリターンを出してきたかどうかなのですよ。
5年実績でも当てにならない。
20年や30年、どれぐらいのパフォーマンスが出ているのか?という点はぜひ押さえていただきたいです。
あとは富裕層向け商品を小口化していると、会社にお勤めの方でも取り組めるぐらいの金額で販売されてたりします。
とはいえ「まともなヘッジファンドは」という言い方をしますが…
10万ドル(今でいうと1,370万円ぐらいかな?1,500万円弱ぐらいのお金)を払わないとそもそもアクセスすることができません。
例えば、自分の家計に2,000万円しかありませんという人が、約1,500万円をヘッジファンドに入れると資産の75%がヘッジファンドになってしまう。
これはリスクを取りすぎじゃない?と思います。
ヘッジファンドに取り組むぐらいなので、当然リスクヘッジをしたいんでしょう?
だとしたら、2,000万円の資産のうち700万円・700万円・600万円で分けるとか…
そして、その600万円を金融系の投資にする。
このように、資金状況に応じて資産を分散させていきましょう。

今回は「ヘッジファンド」に関する解説をさせていただきました。
ありがとうございました。