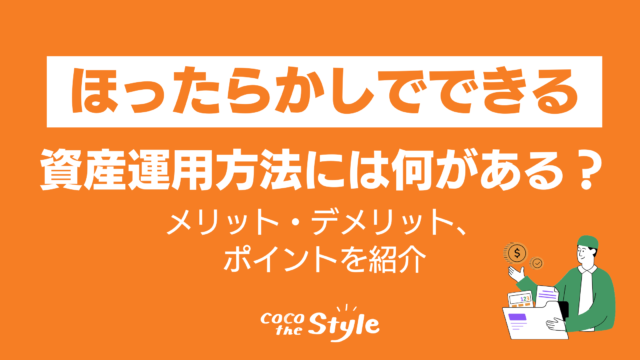改正要望でどう変わる?18歳未満と新NISAの最新動向

2026年度の税制改正に向けて、金融庁が「18歳未満の未成年にも新NISAを利用可能にする」要望を提出しました。
これにより、現在は対象外となっている子供名義での積立投資が、再び非課税枠で可能になるかもしれません。
現時点ではまだ“要望段階”であり、今後の政府・与党の議論や国会審議を経て制度化される必要がありますが、家庭にとっては大きな関心事といえるでしょう。
金融庁が2026年度税制改正で出した要望
金融庁は2025年8月に、2026年度の税制改正要望として「未成年へのNISA拡大」を盛り込みました。
これは、2024年に始まった新NISAの仕組みを基盤としつつ、ジュニアNISA廃止後の空白を埋める形で検討されているものです。
要望の背景には、教育資金の準備や金融リテラシー向上といった社会的ニーズがあります。
18歳未満が対象になるのは「つみたて投資枠」のみ?
金融庁の要望内容からは、未成年が利用できるのは「つみたて投資枠」に限定される見通しです。
成長投資枠(株式やETFなど)を含めてしまうと投機的なリスクが高まるため、制度設計としては堅実な積立型投資信託に絞り込みたい意向と考えられます。
これにより、長期・分散・積立という投資の基本を未成年のうちから実践できる環境が整うことになります。
年間投資枠や管理方法の予測
具体的な年間投資枠や金額については、現時点で金融庁から正式な数値は発表されていません。
専門家の間では「成人と同額ではなく、年間60万円程度に抑えられるのではないか」との見方もありますが、確定情報ではありません。
今後の税制改正大綱で明らかになるでしょう。
また、管理方法についても詳細は未定ですが、想定される運用体制は次の通りです。
・ 投資判断や資金拠出は保護者が代理で実施
・ 対象商品はつみたてNISA適格商品に限定
・ 子供本人による取引や引き出しは制限される見込み
このように、制度が実現すれば「親が子供の将来のために資産を積み立てる仕組み」が整うことになります。
正式な制度設計が決まるのはこれからですが、家庭としては早めに準備を進めることでスムーズな導入につながるでしょう。
未成年が新NISAを使えるとこんなに変わる!4つのメリット

もし制度改正が実現し、18歳未満でも新NISAを利用できるようになれば、家庭や子供にとって大きなメリットがあります。
単に非課税で投資できるだけでなく、長期的な資産形成、教育、家族の資産戦略に幅広く役立つ制度となるでしょう。
複利効果を最大化できる「長期運用」
資産形成において最大の武器は「時間」です。
未成年期から投資を始めれば、成人よりも早く複利効果を享受することができます。
例えば、年間60万円を15年間積み立てると元本900万円になりますが、年率3%で運用すれば約260万円の運用益が非課税で得られる計算になります。
長期間の積立投資により、少額でも大きな資産形成につながる点は大きな魅力です。
教育資金・独立資金を非課税で準備できる
未成年がNISAを利用できるようになれば、教育資金や将来の独立資金を効率的に準備できます。
大学進学や留学、社会人になったときの生活立ち上げ費用など、必要になるタイミングに向けて計画的に積み立てることが可能です。
非課税で運用できるため、課税口座での投資に比べて効率よく資金を育てられるのも大きなメリットです。
親子で投資に取り組むことで金融教育にもなる
親が代理で管理する未成年NISAは、単なる資産形成にとどまらず、子供への金融教育の場にもなります。
口座開設や商品選びを一緒に行ったり、運用状況を確認したりすることで、子供が自然と「お金の流れ」「投資の仕組み」を学べます。
これにより、金融リテラシーが身につき、将来の家計管理力や経済への理解が深まります。
家族全体で非課税枠を拡大できる
未成年が新NISAを利用できるようになれば、家族全体で非課税投資枠を広げられるというメリットもあります。
親が自分のNISA枠を活用しつつ、子供名義でも積立を行うことで、世帯全体での非課税投資枠を最大限に利用できます。
これにより、分散投資の幅が広がり、家族の将来に向けた資産形成をより効率的に進めることが可能になります。
未成年NISAで広がる運用のシナリオとシミュレーション

2026年から未成年も新NISAを使えるようになった場合、家庭や子供の未来にどのような資産形成の可能性が広がるのでしょうか。
ここでは「銀行預金だけの場合」と「未成年NISAを活用した場合」を比較しながら、具体的なシミュレーションをもとに未来像を描いていきます。
シナリオ1:教育資金を18歳までに準備する未来
前提条件として、0歳のときから毎年60万円をコツコツ積み立て、年率3%で運用を続けた場合を考えます。
18歳になる頃には、元本1,080万円に加えて約200万円の運用益が積み上がり、合計で約1,280万円になります。
一方で、同じ金額を銀行預金(金利0.001%程度)に預けていた場合、元本の1,080万円からほとんど増えず、実質的にはインフレの影響で価値が目減りしてしまいます。
つまり、同じ積み立てでも「投資をするかどうか」で200万円前後の差が生まれるのです。
・18歳時点の資産額:約1,280万円(元本1,080万円+運用益約200万円)
| 年率 | 元本 | 最終資産額 | 運用益 |
|---|---|---|---|
| 3% | 1,080万円 | 約1,290万円 | 約210万円 |
| 5% | 1,080万円 | 約1,520万円 | 約440万円 |
| 7% | 1,080万円 | 約1,820万円 | 約740万円 |
この差額は決して小さくありません。
例えば、国立大学の授業料4年間分(約220万円前後)に匹敵し、あるいは私立大学への進学時に必要となる入学金や留学費用の一部をまかなえる規模です。
つまり、積立投資によるわずかな利回りの違いが、進学や将来の選択肢に大きく影響を与える可能性を持っています。
シナリオ2:社会人になる20歳まで運用する未来
0歳から毎年60万円を積み立て、年率5%で運用した場合を考えます。
20歳になる頃には、元本1,200万円に加えて約780万円の運用益が上乗せされ、合計で約1,980万円まで資産が膨らみます。
一方で、同じ金額を銀行預金に置いておくだけでは1,200万円にしかならず、その差はなんと約780万円。
大学の学費総額に匹敵する規模であり、投資をするかどうかで「人生のスタート資金」が大きく変わることを意味します。
・20歳時点の資産額:約1,980万円(元本1,200万円+運用益約780万円)
| 年率 | 元本 | 最終資産額 | 運用益 |
|---|---|---|---|
| 3% | 1,200万円 | 約1,470万円 | 約270万円 |
| 5% | 1,200万円 | 約1,980万円 | 約780万円 |
| 7% | 1,200万円 | 約2,570万円 | 約1,370万円 |
社会人として独立する際には、新生活の初期費用(引っ越し代、家具・家電の購入など)で100万円以上かかることも珍しくありません。
また、結婚式や新婚生活の準備には数百万円単位の資金が必要になります。
さらに将来の留学や起業といった挑戦にも、大きなまとまったお金が支えになります。
銀行預金だけに資金を預けていた場合、積み立てた元本はそのまま維持できますが、インフレの影響を受けて実質的な価値は少しずつ目減りしていきます。
その結果、せっかく準備した教育資金や将来の独立資金も「思っていたほどの力を発揮できない」という状況になりかねません。
一方で、未成年NISAを活用すれば、積立投資と複利効果によって資産は時間とともに大きく成長していきます。
預金だけでは生まれなかった運用益を効率的に積み上げられるため、大学進学や社会人としてのスタート資金といったライフイベントに向けて、計画的に備えることが可能になります。
この制度改正が実現すれば、子供の未来はより大きな安心と可能性に支えられるものとなり、家庭にとっても大きな転機となるでしょう。
【相続・贈与の観点】未成年NISAは相続税対策になる?(具体シミュレーション)

未成年NISAについて「相続税対策になるのでは」と言われるのは、結果的に資産移転効果があるからです。
ただし、NISAそのものに相続税や贈与税の優遇措置があるわけではありません。
ここでは、普通に相続した場合、生前贈与した場合、未成年NISAを活用した場合をシンプルに比較して、その違いを見ていきましょう。
普通に相続した場合
親が1,000万円を遺したとき、相続税の基礎控除を超える規模であれば課税対象となります。
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除は 3,000万円+600万円×2=4,200万円。
・相続税の基礎控除を超える場合は課税対象
・仮に課税対象となれば、数十万円〜数百万円の相続税が発生する可能性あり(家庭の状況により異なる)
遺産全体がこの範囲を超えると課税されるため、1,000万円がまるまる相続税の対象となるわけではないものの、他の資産と合算すれば税負担が発生する可能性は十分にあります。
生前贈与した場合
生前に毎年110万円までの基礎控除を活用すれば、9年間で約990万円を非課税で移転できます。
時間をかければ「合法的に相続財産を減らす」手段になりますが、一括で1,000万円を贈与した場合には大きな税負担がかかります。
・9年間で約990万円を非課税で移転可能
・110万円を超えると贈与税の課税対象になるため注意が必要
つまり、「時間をかければ有効だが、まとめて贈与すると負担が重い」という特徴があります。
未成年NISAを活用した場合
親が子供名義で毎年60万円を積み立てれば、18年間で合計1,080万円を基礎控除の範囲内で移転可能です。
しかも、ただ移すだけではなく、その間に得られる運用益は非課税で積み上がっていきます。
・18年間で1,080万円を基礎控除の範囲内でコツコツ移転可能
・さらに、その間の運用益は非課税で積み上がる
・「資産を移しながら、効率的に増やせる」仕組みとして機能
ここが「単なる生前贈与」との決定的な違いです。
つまり、資産を移転しながら効率的に増やせる仕組みとして機能します。
▼1,000万円を移す場合の比較表
| 方法 | 移転額 | 税金(目安) | 実際に残る資産 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 普通に相続 | 1,000万円 | 数十万〜数百万円(基礎控除超過時) | ケースによる | 相続時にまとめて課税リスクあり |
| 生前贈与(1回で1,000万円) | 1,000万円 | 約253万円 | 約747万円 | 一括贈与だと課税負担が大きい |
| 生前贈与(毎年110万円×9年) | 990万円 | 0円 | 990万円 | 基礎控除を活用できるが時間が必要 |
| 未成年NISA | 60万円×18年=1,080万円+運用益 | 0円(毎年基礎控除内) | 1,080万円+運用益 | 贈与税なし、運用益も非課税 |
贈与税の仕組み(一般贈与)
贈与税は、基礎控除110万円を超える部分に対して課税され、金額に応じて10〜55%の累進税率がかかります。
・超えた部分に累進課税が適用され、税率は10%〜55%まで段階的に上昇
贈与税速算表(2025年時点)
| 課税される贈与額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
未成年NISAでの年間60万円積立は基礎控除110万円以内に収まるため、贈与税はかからないのが大きな特徴です。
未成年NISAはあくまで資産形成を目的とした制度です。
相続税や贈与税を直接的に優遇するものではありません。
結果的に「資産移転効果」があるにすぎないため、相続対策そのものとして過信するのは危険です。
大きな金額を扱う場合は、必ず税理士に相談し、正確な試算や対策を講じることが欠かせません。
制度を「相続税対策」として使うのではなく、「資産形成の一環」として正しく活用することが重要です。
なぜ今?金融庁が未成年NISAを求める理由とは

2025年8月、金融庁は2026年度の税制改正に向けた要望の中で「未成年にもNISAを利用できるように対象を拡大する」ことを盛り込みました。
この要望は単なる制度拡充ではなく、時代の流れに沿った重要な狙いを含んでいます。
長期・積立・分散投資を国民に広げたい狙い
金融庁は「長期・積立・分散」という投資の基本原則を、国民に浸透させることを目指しています。
とくに若年層が早くから投資を始めれば、複利効果を活かしやすく、資産形成の基盤を強固にできるため、未成年NISAはその一助になると考えられています。
ジュニアNISA廃止後の空白を埋める必要性
2023年で終了したジュニアNISAの廃止後、未成年が非課税で投資できる制度は存在しません。
この「空白期間」により、教育資金や子供の資産形成を非課税で進めたい家庭には選択肢がなくなっていました。
新制度はその穴を埋め、再び子供名義で非課税投資を可能にする道を開くものです。
金融教育を子供のうちから推進する意図
未成年NISAは単なる資産形成手段にとどまらず、「家庭での金融教育」を促す意図もあります。
親が代理で投資を進めつつ、子供と一緒に資産運用を確認することで、自然とお金の仕組みや経済の流れを学ぶ環境が整います。
これは金融リテラシー向上を国として後押しする狙いに合致しています。
制度化に備えて今からできる4つの準備
未成年NISAはまだ要望段階ですが、制度化が決まればスムーズに始められるよう、家庭でできる準備があります。
親名義の新NISAを活用して教育資金を積み立てる
まずは現行の新NISAを親が活用し、教育資金や子供の将来資金を積み立てておくことが有効です。
制度が始まるまでの期間も「時間を味方にする」運用を続けることで、資産形成のリズムを整えることができます。
子供のマイナンバーカードや書類を整えておく
未成年口座開設にはマイナンバーカードや住民票、保険証などの本人確認書類、親子関係を示す戸籍謄本などが必要になります。
制度化に先立ち、必要書類を早めに整えておくと、手続きがスムーズです。
家族で投資の目的や方針を話し合う
「教育資金として使うのか」「独立資金として残すのか」など、目的を家族で共有しておくことも重要です。
目的が明確であれば、積立金額や期間の設定もぶれにくくなります。
証券会社の未成年口座対応を調べておく
証券会社によっては未成年口座の対応が異なります。
現時点でもジュニア口座や未成年口座の仕組みを提供している証券会社はあり、今後の新制度対応にも期待ができます。
早めに比較・調査しておくと、制度開始時の選択がスムーズです。
未成年NISAで広がる未来、その第一歩をどう踏み出すか

金融庁の要望は「国民に長期・積立・分散投資を広げる」「ジュニアNISA終了後の空白を埋める」「金融教育を家庭から進める」という3つの背景があります。
まだ要望段階ではありますが、制度化が実現すれば、家庭にとって大きなチャンスとなるでしょう。
そのためにも、親自身のNISA活用、必要書類の準備、家族での話し合いなど、今からできることを少しずつ始めておくのがおすすめです。
とはいえ、「実際にどのくらい積み立てればよいのか」「家計全体でどう制度を活用すればよいのか」悩む方も多いはずです。
そんなときは、お金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのが安心です。
ココザスでは、教育資金やライフプランに合わせたNISA活用法を無料でご相談いただけます。
今すぐ、将来に備える第一歩を踏み出しませんか?
ココザスの無料FP相談はこちらからご利用いただけます。