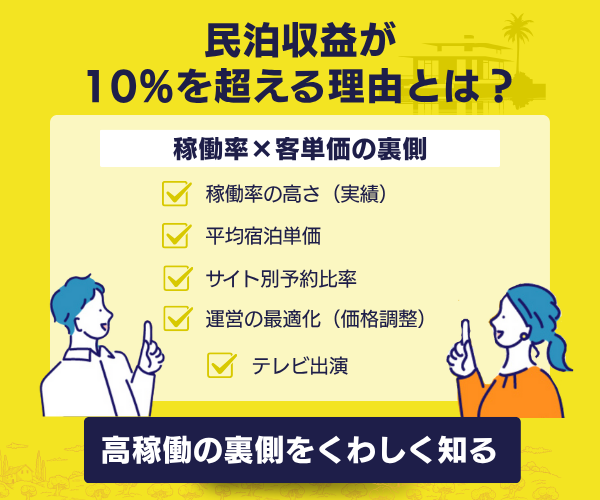サラリーマンでも資産管理会社を作れる?

資産管理会社は、もともと富裕層や経営者が利用するイメージがありますが、実はサラリーマンでも設立可能です。
投資規模や目的に応じて検討すれば、節税や資産形成の有効な手段となりえるでしょう。
資産管理会社の概要とサラリーマンが作る理由について紹介します。
資産管理会社とは何か
資産管理会社とは、その名のとおり「個人の資産を会社として一括管理するための法人」を指します。
主に所有する不動産や株式、投資信託などを法人名義に移し、法人を通して管理・運用する目的として設立されるケースが多いです。
法人化することで、個人での投資と異なる税制が適用され、法人税率の利用や経費計上の幅が広がるといったメリットがあります。
例えば、不動産の管理費用や車両費、通信費なども会社の必要経費として処理できるため、課税所得を抑えられるのです。
また、資産管理会社は「合同会社」「株式会社」といった法人形態を選んで設立できます。
合同会社なら設立費用が比較的安く、維持コストも抑えやすい点が特徴です。
一般的に資産規模が大きい方に向いていますが、近年では不動産投資を行うサラリーマンが節税や相続対策のために活用するケースも増えています。
サラリーマンが作る理由
サラリーマンが資産管理会社を設立する背景には、給与所得だけに依存することへの不安や、税負担を軽減したいという思いがあります。
給与は安定していますが、個人事業主と違って経費計上の幅が狭く、所得が増えるほど累進課税で税率が高くなるため、高収入のサラリーマンほど重い税負担を抱えることになります。
その点、資産管理会社を設立すれば、所得に対して法人税率を適用できるため、個人の最高税率(最大55%)よりも低い税率で納税できるケースが出てきます。
| 区分 | 課税所得 | 税率(所得税+住民税) | 法人税率(目安) |
|---|---|---|---|
| 個人 (給与・事業所得) |
〜195万円 | 15%(所得税5%+住民税10%) | ― |
| 個人 | 〜330万円 | 20%(所得税10%+住民税10%) | ― |
| 個人 | 〜695万円 | 30%(所得税20%+住民税10%) | ― |
| 個人 | 〜900万円 | 33%(所得税23%+住民税10%) | ― |
| 個人 | 〜1,800万円 | 43%(所得税33%+住民税10%) | ― |
| 個人 | 4,000万円超 | 55%(所得税45%+住民税10%) | ― |
| 法人 | 年800万円以下の所得 | 約23.2%(法人税+地方法人税+住民税等を含む実効税率) | 23.2% |
| 法人 | 年800万円超の所得 | 約30.6%(同上) | 30.6% |
法人税はフラットに約23〜30%で、個人の高額所得者に比べて低い水準であることがわかります。
さらに副業や不動産収入で所得が増えた場合でも、法人を活用すれば役員報酬や経費計上によって課税所得を分散でき、結果的に手取りが増える可能性があります。
また、資産管理会社を持つことで投資を「事業」として扱えるため、会計処理が明確になり、資産規模を拡大する際に金融機関からの評価も高まりやすくなります。
給与以外の収入を効率的に管理・拡大したいと考えるサラリーマンにとって、資産管理会社は単なる節税の仕組み以上に「将来の資産形成戦略」として有効な選択肢となるのです。
資産管理会社を作るメリット

サラリーマンが資産管理会社を作るメリットには3つあります。
・不動産や株式投資の管理がしやすくなる
・相続・贈与の対策になる
1つずつ紹介します。
大きな節税効果が期待できる
資産管理会社を設立すると、法人税の適用を受けられるほか、投資や運用に関する支出を経費として計上できるため、課税所得を抑えることができます。
サラリーマンは給与所得控除がある一方、経費として認められる範囲が非常に限られており、節税の余地が少ないのが実情です。
| 項目 | サラリーマン(個人) | 資産管理会社(法人) |
|---|---|---|
| 控除・経費 | 給与所得控除のみ(自動計算) | 投資や運営に関する幅広い経費を計上可能 |
| 経費計上例 | ほぼ不可(通勤費程度) | 修繕費、管理費、事務所利用分、自動車費、通信費など |
| 税率 | 所得が増えるほど最大55% | 法人税は約23〜30%でフラット |
| 所得分散 | 不可 | 家族に役員報酬を出すことで分散可能 |
| 節税余地 | 限定的 | 大きい(資産規模が大きいほど効果的) |
例えば、不動産投資に関する修繕費や管理費、さらには事務所として使う自宅の一部や通信費、車両費なども必要経費として処理できる可能性があります。
また、家族を役員にして役員報酬を分散させることで、個人の高額な所得税負担を軽減することも可能です。
法人税率は所得税の最高税率より低いため、資産規模が大きいほど節税効果が大きくなり、特に年収が高く投資額も大きいサラリーマンには有効な手段といえます。
不動産や株式投資の管理がしやすくなる
資産管理会社を通じて不動産や株式を保有すると、個人名義で複数棟に所有している場合に比べ、資産の一元管理が可能になるメリットがあります。
例えば、不動産を複数所有している場合、収支の管理や修繕履歴の把握、融資の返済状況などを会社の帳簿でまとめられるため、資産状況が明確になりやすいのが特徴です。
また、法人名義であれば金融機関からの評価が高まり、融資を受けやすくなるケースもあります。
株式投資についても、法人を通して取引すれば利益や損失を法人税務上で一括処理でき、個人よりも柔軟に損益通算を活用できる場合があります。
サラリーマンにとっては「給与所得」と「投資所得」が完全に分かれて管理されることになり、税務処理や資産形成の戦略を立てやすくなるでしょう。
相続・贈与の対策になる
資産管理会社を活用すると、相続や贈与に関する負担を事前に軽減できる点が大きなメリットです。
個人で不動産や株式を直接所有している場合、相続時に評価額が高くなり、結果として多額の相続税が発生する可能性があります。
しかし、資産を資産管理会社に移しておけば、相続時には「会社の株式」として承継する形となり、個別資産よりも評価額を下げやすくなるのです。
さらに、家族を役員や株主にしておくことで、生前から少しずつ株式を贈与し、相続時の課税対象を分散させることが可能です。
この仕組みを使えば、不動産を直接分割する必要がなく、株式の持分を調整するだけで公平に分配できます。
特に将来の相続トラブルを避けたい場合や、多額の資産を次世代にスムーズに引き継ぎたいサラリーマンにとって、資産管理会社は計画的な相続・贈与のための有効な手段でもあるのです。
資産管理会社を作るデメリット

一方、資産管理会社を作るデメリットも3つあるので紹介します。
・節税効果が出るのは一定以上の資産規模から
・税務調査リスクや管理の手間
1つずつ確認しておきましょう。
設立・維持コストがかかる
資産管理会社を設立するには、会社登記費用や定款作成費用、登録免許税など初期コストが発生します。
合同会社であれば比較的安く済みますが、株式会社にする場合は設立費用が高くなることがあります。
さらに、設立後も毎年の法人住民税や会計処理費用、税理士報酬などの維持費がかかり、資産規模が小さい場合はメリットよりも維持コストの方が大きくなることがあります。
サラリーマンの場合、給与所得以外の資産規模が少ないと、わずかな節税効果では維持費を回収できない可能性がある点に注意が必要です。
節税効果がでるのは一定以上の資産規模から
節税効果が現れるのは、一定以上の資産規模がある場合であることを理解しておく必要があります。
資産管理会社を通じた節税は、法人税率のメリットや経費計上の幅広さを活用することで実現します。
しかし、資産が少ない場合は、経費で処理できる支出も限られ、法人を設立しても個人より節税効果がほとんど出ないことがあります。
そのため、資産規模が小さい段階で無理に法人を設立すると、コストや管理負担だけが増えるリスクがある点に注意しましょう。
税務調査リスクや管理の手間
資産管理会社には税務調査リスクや管理の手間があります。
資産管理会社は法人として運営するため、帳簿や決算書の作成、税務申告などの管理業務が必要です。
特に経費として計上する範囲は税務署から確認される可能性があり、不適切な計上があると追徴課税のリスクがあります。
また、役員報酬の設定や家族への給与支払いなども適切に運用する必要があり、管理の手間が増える点もデメリットです。
サラリーマンが副業的に法人を運営する場合、日常業務に加えてこれらの管理負担が発生することを事前に認識しておきましょう。
サラリーマンが資産管理会社を作る具体的な方法

資産管理会社を設立する際には、具体的な手順や必要な資金、専門家への依頼方法を理解しておくことが重要です。
ここでは設立の流れや費用目安について紹介します。
設立の流れ
資産管理会社を作る基本的な流れは、以下のとおりです。
このように、順を追って手続きを進めることで、サラリーマンでも資産管理会社を立ち上げることが可能です。
必要な資本金と登記費用
資産管理会社の設立に必要な資本金は、法律上1円から可能です。
ただし、金融機関から融資を受けることを考えると、50万円〜100万円程度の資本金を用意するケースが多いです。
さらに合同会社であれば登録免許税が約6万円、株式会社であれば約15万円が目安としてかかりますが、その他にもさまざまな費用がかかるので事前に確認しておきましょう。

税理士や専門家に依頼する場合
税理士や専門家に依頼する場合は、費用は設立手続きだけで 5〜20万円程度、会計・税務顧問契約は年間 10〜50万円程度が目安でかかります。
会社設立や運営に不安がある場合、税理士や司法書士など専門家に依頼するのがおすすめです。
専門家に依頼すると、定款作成や登記申請、法人設立届出などの手続きがスムーズになり、初めて法人を設立するサラリーマンでも安心して進められます。
また、税務申告や会計処理も専門家に任せることで、経費の計上漏れや税務リスクを回避できます。
時間とリスクを考えると、専門家に依頼することは長期的に効率的な選択となるでしょう。
資産管理会社を活用した節税方法

ここではサラリーマンの方が資産管理会社を活用した節税方法を3つ紹介します。
・家族を役員にして給与を支払う方法
・退職金制度を利用する
1つずつ確認しておきましょう。
役員報酬を活用した所得分散
資産管理会社の代表者(社長)が自分自身に支払う役員報酬を適切に設定することで、所得分散による節税が可能です。
例えば、会社の利益をすべて役員報酬として受け取るのではなく、必要な経費を計上した上で残りの利益を会社に残すことで、法人税率で課税される額を調整できます。
法人税率は個人の高額所得税率より低いため、利益を法人に残すだけで税負担を軽減できます。
役員報酬は毎月一定額を支払う形にするのが基本で、税務上も認められやすい方法として活用されています。
家族を役員にして給与を支払う方法
家族を役員や従業員として登用し、給与を支払うことで所得を分散させることができます。
例えば、妻や子供を役員にして給与を設定すれば、個人の高額所得税率にかかる所得を軽減しつつ、家族全体で所得を分散できます。
給与として支払った金額は法人の必要経費として認められるため、会社の課税所得を減らすことも可能です。
ただし、給与の金額は業務実態に見合った額である必要があり、税務署に不自然な高額給与と判断されないよう注意しましょう。
退職金制度を利用する
資産管理会社では、将来の退職金をあらかじめ役員に支給する制度を設けることで節税効果を高めることができます。
退職金は、法人が支払うときは損金(経費)として処理でき、受け取る側も退職所得控除が適用されるため、課税額を大幅に抑えられます。
特に長年にわたって役員報酬を積み上げてきた場合、退職金としてまとめて受け取ることで個人所得税の負担を軽減できます。
サラリーマンが自分の資産管理会社を活用する場合、退職金制度を計画的に設けることは、将来の資産形成と節税の両面で有効な手段となるのでおすすめです。
資産管理会社を作るのに向いている人は?

資産管理会社は誰にでも向いているわけではなく、ある程度の資産規模や投資状況、相続のニーズがある人にメリットが大きくなります。
ここでは、資産管理会社を作るのに向いている人の特徴を3つ紹介します。
・不動産投資を複数所有している場合
・相続対策を重視する場合
1つずつ見ていきましょう。
資産規模が1億円以上ある場合
資産管理会社を設立して節税効果を実感できるのは、一般的に資産規模が1億円以上ある場合です。
それ未満の場合は、設立や維持のコストが節税効果を上回る可能性があるため、慎重に見極めましょう。
高額資産を法人名義で管理することで、法人税率を活かした課税所得の圧縮や、経費計上による税負担軽減が可能になります。
サラリーマンでも、給与以外に投資や不動産収入が大きい場合は、資産管理会社を設立することで手取りを増やす効果が期待できます。
不動産投資を複数所有している場合
不動産投資を複数所有している方は、資産管理会社の設立に適しています。
資産管理会社を設立すると、物件ごとの収支や修繕費、管理費などを法人で一括管理できるため、会計処理や税務申告が効率化されます。
また、法人経費として多くの費用を計上できるため、個人よりも高額所得に対する節税効果が得られやすくなります。
不動産投資が本格化しているサラリーマンには特に向いている運用方法です。
相続対策を重視する場合
相続対策を検討している方には、資産管理会社の設立が適しています。
個人所有の不動産や株式をそのまま相続すると高額な相続税が発生する可能性がありますが、会社名義で所有していれば株式として承継でき、評価額を下げやすくなります。
さらに、家族を役員や株主にしておくことで、生前贈与を計画的に行い、相続時の負担を分散することも可能です。
相続対策を重視するサラリーマンにとって、資産管理会社は資産承継の強力なツールとなるでしょう。
まとめ

サラリーマンでも、資産管理会社を設立することで節税や資産運用、相続対策といった多くのメリットを受けることができます。
法人化することで所得を法人税率で分散でき、経費計上の幅も広がるため、個人で投資するより効率的な資産形成が可能です。
また、不動産や株式の管理が一元化できることで、資産状況の把握や金融機関からの評価も向上します。
ただし、設立や維持にはコストと手間がかかるため、資産規模が小さい場合は十分な節税効果が得られない可能性があります。
そのため、資産管理会社の設立は、資産規模が一定以上ある方や複数の不動産投資を行っている方、相続対策を重視する方に特に向いています。
また、資産管理会社の設立や運用は専門的な知識が必要なため、独自で進めるのはハードルが高い場合があります。
そこで、まずはココザスのような専門家に相談することをおすすめします。
ココザスでは、設立手続きから税務対策、将来の相続対策までトータルでサポートしています。
そのため、初めて資産管理会社を作るサラリーマンでも安心して進められます。
相談料は何度でも無料です。
ぜひ一度お問い合わせください。