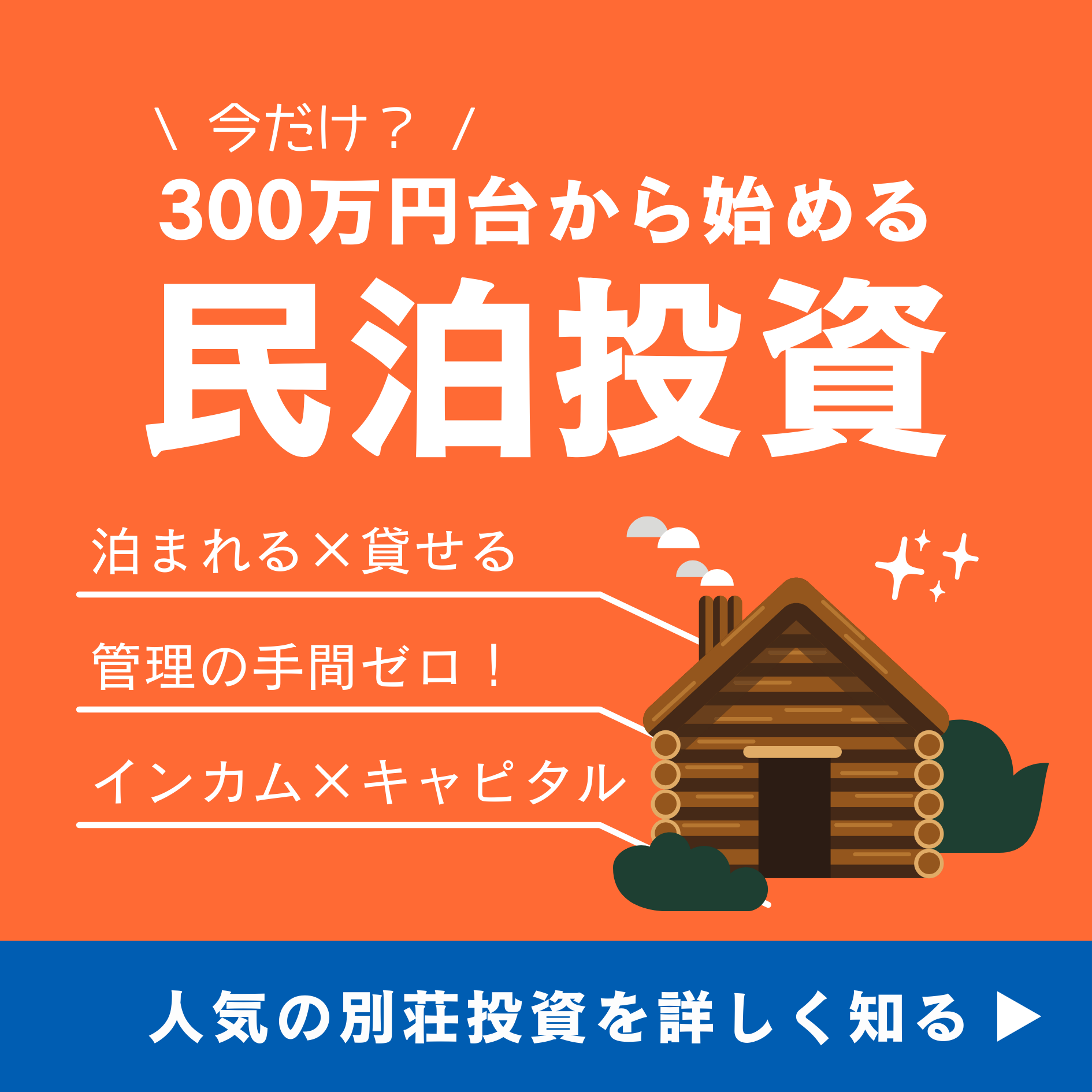住民税を普通徴収にできる?

住民税の納税方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
会社員の場合、住民税は毎月の給与から自動的に天引きされる「特別徴収」が原則ですが、状況によっては自分で納める「普通徴収」に切り替えることも可能です。
ここでは、特別徴収と普通徴収の違いや、普通徴収が可能なケース・できないケースについて紹介します。
普通徴収は可能だが、原則は特別徴収
住民税は、原則として特別徴収(給与天引き)で納める仕組みになっています。
これは、地方税法により会社などの給与支払者に対して、従業員の住民税を天引きして自治体に納める義務があるためです。
会社員が確定申告や年末調整を行うと、その情報が市区町村に送付され、住民税の決定通知が会社に届きます。
会社はその通知に従い、従業員の給与から住民税を天引きして納めることになります。
これが「特別徴収」です。
そのため、何もしないままでいると自動的に特別徴収となり、自分で住民税を納める「普通徴収」にはなりません。
普通徴収ができるケース
以下のようなケースでは住民税を普通徴収にすることができます。
・自治体にもよりますが、副業による雑所得や事業所得がある場合、その分の住民税は申告の内容によって普通徴収に変更することが可能です。
確定申告の際に「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択することでできます。
・自分で事業をしている場合は給与支払者がいないため、住民税は原則として普通徴収になります。
・自治体によって異なりますが、例外的に普通徴収が適用されることがあります。
東京都の場合、次の理由【普A〜普F】に該当する場合は、普通徴収にすることができます。
・普A:事業所の総従業員数が2人以下
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
・普B:他の事業所で特別徴収
・普C:給与が少なく、税額を天引きできない
・普D:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
・普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
・普F:退職者又は退職予定者(5月末日まで)
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます)
普通徴収ができないケース
一方で、普通徴収を希望してもできないケースが3点挙げられます。
・基本的に会社には住民税の特別徴収を行う義務があるため、従業員が希望しても、「特別徴収のみ対応」とされることがあります。
・確定申告書の「住民税に関する事項」で何も記載しなければ、自治体が判断して特別徴収になることがあります。
・一部の自治体では、特別徴収の徹底を進めており、例外的な事情がない限り普通徴収を受け付けていない場合があります。
普通徴収へ切り替える方法

ここでは、会社員で副業収入がある場合、退職して給与収入がない場合、個人事業主やフリーランスなどの給与以外の収入がある場合の3つに分けて、切り替え方法を詳しく解説します。
・ 退職した人(無職・年金生活者含む)の場合
・ 給与所得以外の収入がある個人事業主・フリーランスの場合
自分の勤務状況などに応じた方法を確認していきましょう。
会社員で副業収入がある人の場合
副業で収入がある会社員が、副業分の住民税だけ普通徴収にしたい場合は、確定申告時に以下の対応を行います。
- 確定申告書の第二表を確認
確定申告書B様式の第二表の右下にある「住民税・事業税に関する事項」という欄に注目してください。
「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。
このチェックにより、副業分の住民税は給与から天引きされず、あなたのもとに納税通知書が届くようになります。
「特別徴収を希望する」を選ぶと、会社を通じて住民税が納付され、副業分も含めて一括で天引きされる可能性があるので注意しましょう。
- 副業収入の種別を正確に記載
確定申告書の「収入の内訳」欄で、副業の収入を適切に分類しましょう。
・事業所得:継続的に行っている業務(ライター、デザイナー、物販など)
それぞれの所得について、事業主名や支払者の名称を記載することで、会社の給与所得とは別の収入であることを明示できます。
- e-Taxか紙で提出する際の注意
「住民税の徴収方法の選択」欄にあるプルダウンから「自分で納付」を必ず選択してください。
一部の市区町村ではe-Taxのデータを正しく受信できないケースもあるため、念のため送信後に住民税通知を確認しておきましょう。
第二表の該当欄に必ず「自分で納付(普通徴収)」と記載して提出します。
- 提出後の確認
副業分の住民税の納付書が自宅に届いていれば、手続きは完了したと判断できます。
会社に通知されていないかも確認しましょう。
退職した人(無職・年金生活者含む)の場合
退職して給与収入がなくなった方の場合、特に自分で切り替えを申し出なくても、自動的に普通徴収になるのが一般的です。
ただし、タイミングによっては注意しなければいけないケースもあります。
5月以降に退職した場合は、その年の住民税をすでに特別徴収で一部納めている可能性があります。
残りの未納分については、普通徴収として一括で請求される場合もあります。
自分で納付する必要があるため、自治体から届く「住民税決定通知書」で支払いスケジュールを確認しておきましょう。
給与所得以外の収入がある個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主やフリーランスのように、給与をもらわずに事業や業務委託などで収入を得ている人は、住民税は原則として普通徴収になります。
切り替えの手続きというよりも、以下のような流れになります。
所得税の申告とあわせて自治体に所得情報が送られ、住民税が計算されます。毎年確定申告しましょう。
②住民税決定通知書が自宅に届く
通常6月ごろに送られてくる通知書で、普通徴収(自分で納付)であることが明記されています。
③通知書に記載された期日までに納税する
年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付するのが基本です。
なお、フリーランスであっても、報酬を支払う企業が誤って「給与扱い」で処理していた場合は、特別徴収扱いになることも稀にあるため、報酬の区分には注意してください。
普通徴収の手続き手順

自分で納付する必要があるため、『いつ、どのような手続きが必要か』を理解しておくことが重要です。
ここでは、普通徴収における手続きの流れを、3つのケースに分けて解説します。
2. 退職した人(無職・年金生活者を含む)の場合
3. 給与所得以外の収入がある個人事業主・フリーランスの場合
一つずつ確認していきましょう。
所得税の確定申告データから自治体が計算する
住民税は、基本的に前年の所得をもとに算出されます。
個人で普通徴収を選んだ場合でも、住民税の金額は以下のようなプロセスで決まります。
所得税の確定申告を行うことで、1年間の収入と所得控除の情報が税務署を通じて市区町村に送られます。
②住民税の課税資料として自治体が利用
送付された申告情報をもとに、各自治体が独自に住民税(市町村民税+都道府県民税)の計算を行います。
③「自分で納付(普通徴収)」と申告していれば、その設定が反映される
確定申告書やe-Tax上で「普通徴収を希望する」にチェックを入れていれば、自治体が普通徴収の可否を確認し、住民税の納付書が自宅に届く仕組みです。
会社員で副業収入がある人は、本業の給与分は特別徴収のまま、副業分のみが普通徴収になるよう処理されます。
住民税決定通知書が届く
確定申告が完了し、自治体による住民税の計算が終わると、6月頃に「住民税決定通知書」および「納付書(納税通知書)」が自宅に郵送されます。
この通知書には以下の内容が記載されています。
・住民税の年税額(市民税・県民税の内訳)
・普通徴収で納付すべき金額
・納付期限と回数
・納付書が4枚(6月・8月・10月・翌年1月の納期分)添付
通知書が届いたら、記載された納付スケジュールと金額を必ず確認しましょう。
副業収入のみが課税対象になっているか、本業と混ざっていないかも要チェックです。
また、一部自治体では電子通知(eLTAX連携)やマイナポータルで確認できます。
納税を行う
住民税の納税は、通知書に記載されたスケジュールに従い、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付するのが基本です。
もちろん一括払いも可能で、期末までに全額支払えば延滞にはなりません。
納付方法は以下のとおりです。
・コンビニ支払い(バーコード付き納付書)
・自治体窓口
・スマホ決済(PayPay、LINE Pay、au PAYなど)※対応自治体に限る
・口座振替(事前に自治体で手続きが必要)
万が一納期限を過ぎると延滞金が発生することもあります。
忘れずに納付できるようにカレンダーやアプリでスケジュールを登録しておきましょう。
普通徴収にするメリット・デメリット
住民税を普通徴収にすると、自分で納税手続きを行う必要がありますが、その分メリット・デメリットもあるので、ここで詳しく紹介します。
メリット:納付時期を自分でコントロールできる
普通徴収最大のメリットは、納税のタイミングをある程度自分で調整できることです。
住民税の普通徴収は、基本的に年4回(6月・8月・10月・翌年1月)の分納ですが、一括納付も可能です。
これにより、一時的に出費がかさむ月を避けて、余裕のあるタイミングで納付できたり、資金繰りを考慮して一括で支払っておくなどの選択肢が可能です。
また、会社の給与から自動で天引きされるわけではないため、収支の全体像を自分で把握しやすくなるという点も、個人事業主や副業をしている人には大きなメリットと言えるでしょう。
デメリット:納付漏れのリスクが伴う
一方で、普通徴収には自己管理が必須であるので、納付漏れのリスクが伴うデメリットがあります。
会社が代わりに払ってくれるわけではないため、納付書が届いても放置してしまいがちです。
うっかり忘れると延滞金が発生するため注意しなければいけません。
また納付までに時間的余裕があるため、手元資金を他の支出に回してしまい、納付時に困るケースも少なくありません。
このように納付に対しての管理を忘れてしまう方も多く、延滞金が発生したり、催促状の送付によって個人の信用に影響が出る可能性もあるので注意しましょう。
普通徴収にする場合の注意点
住民税を普通徴収にすることで得られるメリットもありますが、制度の仕組みや自治体の運用方法を正しく理解していないと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、普通徴収を選択するうえで注意すべきポイントを3点紹介します。
2. 普通徴収=副業がバレないというわけではない
3. 一度特別徴収になると、途中変更が難しい
1つずつ確認してから普通徴収にするか検討しましょう。
自治体によっては「普通徴収にできない」ことがある
自治体によっては「普通徴収にできない」ことがあります。
住民税の徴収方法に関する基本方針は全国共通ですが、実際の運用は各市区町村の判断に委ねられている部分が多いです。
そのため、確定申告で「普通徴収を希望する」にチェックを入れていても、普通徴収が認められないケースもあります。
特に、会社が給与支払報告書を提出していて、自治体が自動的に特別徴収として処理している場合は、自治体の方針により普通徴収に切り替えられないこともあります。
事前に自治体の住民税課に確認しておきましょう。
普通徴収=副業がバレないというわけではない
「副業が会社にバレたくないから普通徴収にしたい」と考える方は多いですが、普通徴収にしたからといって副業が完全に隠せるわけではありません。
会社が市区町村からの住民税通知で合計所得額を把握する場合や、副業先が給与として支払っており、その情報が給与支払報告書経由で自治体に届くルートによってバレる可能性があります。
確定申告で「普通徴収にする」と明記していても、副業収入の形や金額によっては会社に知られるリスクはゼロではないので注意しましょう。
一度特別徴収になると、途中変更が難しい
住民税は毎年6月にその年度の課税額が決定されますが、この時点で特別徴収として処理されてしまうと、年度の途中で普通徴収へ変更することは原則できません。
すでに会社が従業員の住民税額を自治体に通知しており、課税処理が完了しているため、原則変更できません。
また、特別徴収を解除するには、会社からの申し出(「特別徴収義務者の異動届出書」など)が必要となるため、簡単には切り替えられません。
まとめ

住民税を普通徴収に切り替えることで、納税のタイミングを自分で管理できるというメリットがありますが、制度の理解や確定申告時の正確な手続きが欠かせません。
また、自治体の方針や会社の対応によっては、希望どおりに普通徴収にできない場合もあります。
副業を会社に知られたくない、退職後に自分で納税管理をしたいといった理由で普通徴収を検討する方は、事前に住んでいる自治体の運用や会社の方針を確認し、確定申告での記載もれがないよう注意しましょう。
不明点がある場合は、自治体の住民税課や税理士など専門家への相談もおすすめです。
正しい知識と準備で、自分に合った納税方法を選びましょう。