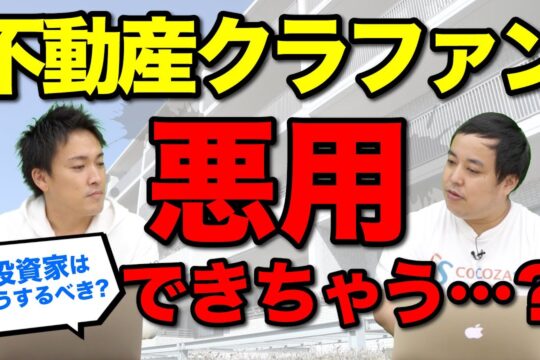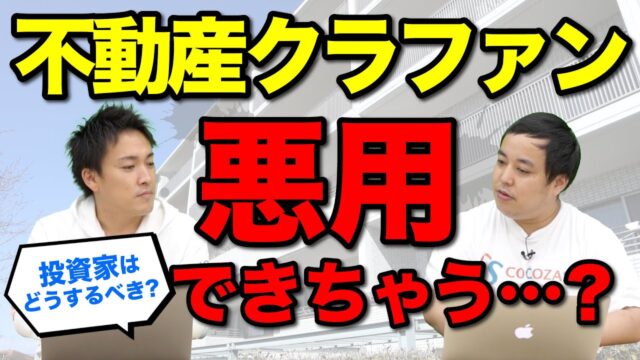不動産クラウドファンディングは元本割れのリスクがある

不動産クラウドファンディングでは、元本保証がなく、投資金額が目減りする可能性があります。
元本割れする原因には、不動産特有のリスクや外的な要因が影響しています。
こちらでは、具体的な理由やリスク要因を詳しく解説します。
元本割れはなぜ起こるのか?
不動産価格が下落する主な理由は、次の通りです。
・自然災害の影響
地震や洪水などの災害が発生すると、その地域の不動産の需要が低下し、資産価値が落ちることがあります
・経済危機や市場の低迷
景気後退や金融市場の混乱が続くと、不動産の売買が停滞し、価格が伸び悩む可能性があります
こうした要因によって資産価値が下がると、投資金額にも影響が及んでしまいます。
リスクが高まる案件の特徴
元本割れリスクが高い案件には、以下の特徴が見られます。
(1)立地条件が悪い物件
人口減少エリアや交通の便が悪い地域では、賃貸需要が低下しやすいです。
例えば、過疎化が進む地方都市やインフラが未整備なエリアの物件は、資産価値が維持しにくい傾向があります。
(2)築年数が古い物件
築年数が古い物件は修繕費用が増加し、不動産価値が低下するリスクがあります。
また、築30年以上の物件では耐震性の問題が影響し、需要が低下するケースも考えられます。
(3)運営会社の信頼性が低い場合
財務状況が不透明な運営会社では、不動産の運用が適切に行われるか不確かで、トラブルが発生するリスクが高まります。
過去に問題が多い会社や実績が乏しい会社では、物件の管理が行き届かず、賃料収入が安定しにくくなるかもしれません。
不動産クラウドファンディング元本割れ以外に知っておきたいリスク

不動産クラウドファンディングは、元本割れ以外にも、注意すべき点がいくつかあります。
詳細をこちらで見ていきましょう。
(1)分配金の遅延や未払い
不動産クラウドファンディングでは、分配金が予定通りに支払われないリスクがあります。
遅延や未払いが発生する理由として、以下のような点が挙げられます。
・空室率の増加
物件の賃貸需要が低下し、賃料収入が不足する場合、分配金の支払いに影響を与えます
・売却の遅れ
キャピタルゲイン(物件の売却益)を狙った案件では、不動産売却が計画通りに進まず収益が確保できない可能性があります
運営側の見通しが甘かったり、不動産市場全体が低迷していたりする場合は、よりリスクが高まります。
(2)基本的に途中解約ができない
不動産クラウドファンディングでは、投資期間中の途中解約が認められていません。
この特性には、以下のようなデメリットがあります。
・資金の移動が制限される
投資中の資金が拘束されるため、急な出費が必要になっても現金化できません
柔軟な対応が難しくなる
他の投資機会があった場合でも、すぐに資金を動かせないため、機会損失につながることがあります
例えば、想定外の医療費や緊急の出費が発生した際でも資金を引き出せない点は、大きな制約となるでしょう。
(3)案件選びに制限がある可能性
不動産クラウドファンディングでは、すべての案件を自由に選べるわけではありません。
参加者が直面する可能性がある制限には、次のような点があります。
・案件の募集数が限られている
人気の高い案件は短時間で募集終了となり、希望のタイミングで投資できないことがあります
・選択肢が限られる
市場や運営方針によっては、投資可能な案件が少なく、希望する条件の物件が見つからない場合があります。
例えば、地方の築年数が古い物件や、賃貸需要が不透明な案件が中心になる可能性もあります。
不動産クラウドファンディングで元本割れを防ぐ具体策

元本割れのリスクを抑えるためには、安全性を重視した投資判断や信頼できる運営会社の選定が必要です。
ここでは、具体的な対策として、利回りだけにとらわれない判断基準や優先劣後出資制度の活用法、分散投資の重要性を詳しく解説します。
(1)利回りだけでなく安全性を重視する
高い利回りの案件は魅力的に見えますが、その分リスクも高くなります。
収益が不安定な案件を避けるためには、次の点を確認しましょう。
・物件の立地や用途
賃貸需要が高いエリアや商業的価値のある物件を選ぶことで、リスクを抑えられます
・案件の規模と収益モデル
小規模な案件よりも、複数の物件を含む大規模な案件のほうが収益の変動が少ない傾向があります
利回りだけに注目せず、物件の特性や市場の需要を考慮した投資判断が重要です。
(2)優先劣後出資方式を利用する
優先劣後出資方式は、不動産クラウドファンディングで元本割れリスクを軽減する制度です。
・優先出資とは
投資家が出資する資金で、利益が出た場合は優先的に分配されます
・劣後出資とは
事業主や運営会社が自ら出資する資金で、損失が発生した場合はこの資金から先に負担されます。
この制度では、劣後出資の割合がリスク軽減の鍵となります。
●劣後出資の割合が重要な理由
例えば、劣後出資の割合が20%の場合、不動産価値が20%下落しても投資家の資金には影響が出ません。
劣後出資が多いほど、参加者が損失を受けるリスクを下げられます。
●優先劣後方式を採用しているかを確認する方法
優先劣後方式を採用しているファンドかどうかは、ファンド概要や運営会社の公式サイトで確認できます。
「優先劣後出資制度の導入」と明記されているか、劣後出資割合が記載されている場合、制度が適用されている可能性が高いです。
疑問点があれば、運営会社に直接問い合わせるのも有効です。
優先劣後方式を採用しているファンドを選ぶことで、初心者でも比較的安全に投資を始めやすくなります。
ただし、劣後出資割合が高くても、元本保証があるわけではないため、投資判断の際には十分な注意が必要です。
(3)運営会社を慎重に選ぶ
不動産クラウドファンディングでは、選んだ運営会社によって投資の成果が大きく左右されます。
資金管理や物件の運営方針に差があるため、信頼できる会社を選ばなければ、分配金の遅延やトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
そのため、慎重に見極めることが大切です。
確認すべきポイント
- 不動産特定共同事業の許可取得
不動産クラウドファンディングを運営するには、「不動産特定共同事業」の許可を取得している必要があります。
金融庁や国土交通省の公式サイトで、運営会社の登録状況を確認しましょう。 - 上場企業または親会社の規模
上場企業は財務状況や経営実績を公開しており、透明性が高い傾向があります。
また、親会社が上場している場合も、事業の安定性を判断する材料になります。
ただし、未上場でも実績が豊富な会社は多いため、上場の有無だけで判断せず、他の要素とあわせて総合的に評価することが重要です。 - 過去の案件成功率と償還実績
公式サイトや投資家向けの資料を確認し、運営会社が手掛けた案件が予定通り償還されているかチェックしましょう。
分配金の支払い実績や、投資家の口コミも参考になります。 - 投資家へのサポート体制
問い合わせへの対応が適切か、サポート体制が整っているかを確認します。
公式サイトのFAQや問い合わせフォームを活用し、返答の速さや丁寧さをチェックするのも有効です。
また、投資家向けの説明会やウェビナーを開催している会社は、透明性が高いと判断できます。
これらの点を総合的に判断し、信頼できる運営会社を選ぶことで、リスクを抑えながら投資を進めやすくなります。
(4)分散投資を心がける
不動産クラウドファンディングだけに資金を集中すると、1つの案件の影響を強く受けるため、リスク分散が難しくなります。
そこで、他の投資手法と組み合わせることで、投資全体のリスクを抑えるのが有効です。
例えば、次のような組み合わせが考えられます。
●不動産クラウドファンディング + REIT(不動産投資信託)
REITは複数の不動産を分散して運用するため、クラウドファンディング単体よりもリスクが軽減されます。
REITの配当収益とクラウドファンディングの利回りを組み合わせれば、収益源を複数持つことができるため、安定した資産運用が可能です。
●不動産クラウドファンディング + 債券投資
債券は株式市場や不動産市場の変動に強い資産です。
一定割合を債券に振り分けることでリスクヘッジができます。
これらは、不動産クラウドファンディング単体の元本割れ対策とは異なるものの、投資全体のリスクを抑える方法として活用できます。
元本割れを防ぐためには、クラウドファンディングに集中しすぎず、資産全体のバランスを考えた分散投資を心がけましょう。
他の不動産投資と比較したメリット・デメリット

不動産クラウドファンディングは、リート(REIT)や現物不動産投資とは異なる特徴を持っています。
ここでは、各々の違いを比較し、自分に合った投資方法を選ぶための判断材料をお伝えします。
不動産クラウドファンディングとリート(REIT)の違い
不動産クラウドファンディングとリート(REIT)は、少額から不動産投資を始められるという点では共通しています。
ただし、具体的な仕組みやリスクが異なります。
●主な違い
(1)流動性
- リート:証券市場で取引されるため、株式のように売買が容易です。急な資金需要があっても現金化しやすいのが特徴です
- クラウドファンディング:投資中に資金を引き出すことは基本的にできません
(2)管理コスト
- リート:運営会社が大規模なポートフォリオを管理するため、運営コストが利回りに反映されることがあります
- クラウドファンディング:案件ごとの管理となり、コストは比較的抑えられる場合が多いです
(3)リスク分散
- リート:複数の不動産物件に投資するため、分散効果が高く、特定の物件リスクを軽減できます
- クラウドファンディング:1つの物件やプロジェクトに資金を集中する場合が多く、リスクが偏る傾向があります
●どちらが適しているか?
短期間で資金を動かしたい場合や、分散投資を重視したい場合はリートがおすすめです。
一方で、個別の不動産案件に投資したい場合は、クラウドファンディングが向いています。
現物不動産投資との違い
現物不動産投資は、物件を直接購入し、所有するスタイルです。
一方、不動産クラウドファンディングは、運営会社が物件を管理し、投資家は出資する形で参加する投資方法です。
●主な違い
(1)初期費用
- 現物不動産:物件購入には多額の初期費用が必要です。頭金だけでも数百万円が必要になることがあります
- クラウドファンディング:少額から投資可能で、1万円から参加できる案件もあります。
(2)管理責任
- 現物不動産:賃貸借契約や修繕、税金の支払いなど、オーナーとしての管理責任が発生します
- クラウドファンディング:運営会社が物件の管理を行うため、投資家には負担がありません
(3)リスクとリターン
- 現物不動産:物件を直接所有するため、キャピタルゲインを狙える一方、物件価格の下落による損失を直接受けます
- クラウドファンディング:運営会社によって案件が管理されるためリスクは軽減されますが、高いリターンを得るのは難しい場合があります
●どちらが適しているか?
自ら物件を管理して高いリターンを目指したい場合は、現物不動産投資が向いています。
一方で、少額から手軽に始めたい場合や、管理の手間を避けたい場合は不動産クラウドファンディングがおすすめです。
初心者から始められる不動産クラウドファンディングの実践ステップ

ここでは、初心者が無理なく不動産クラウドファンディングを始めるための3つの実践ステップを解説します。
ステップ1: 投資目的を明確にする
投資を始める前に、自分の投資目的を明確にすることが重要です。
●短期的な利益を狙うのか、安定収益を目指すのか
キャピタルゲインを重視する場合と、インカムゲイン(賃貸収益)を重視する場合で選ぶ案件が異なります。
●どれくらいのリスクを許容できるか
高い利回りを狙う場合はリスクも高まるため、リスク許容度に応じた案件を選ぶ必要があります。
投資目的がはっきりしていれば、自分に適した案件を選びやすくなります。
ステップ2: 投資額と資金計画を決める
次に、実際に投資する金額や資金計画を立てます。
●生活費を削らない範囲で資金を用意する
投資は余剰資金で行うことが基本です。
生活費や緊急時の資金を確保したうえで、余裕資金から投資額を決めましょう。
●少額から始めて経験を積む
初心者は1万円程度の案件からスタートし、投資の仕組みに慣れながら規模を広げるのがおすすめです。
資金計画をしっかり立てることで、無理のない範囲での投資が可能になります。
ステップ3: 投資後の経過を定期的にチェックする
投資を始めた後も、定期的に経過を確認することが重要です。
放置せず、自分の投資案件や市場の動きを把握しましょう。
●運営会社からのレポートを確認する
不動産クラウドファンディングでは、運営会社から定期的に案件の進捗や収益報告が送られます。
これを必ず確認し、状況を把握します。
●案件の収益が想定通りかをチェックする
分配金が予定通りに支払われているか、不動産市場の変動が案件に影響を与えていないかを確認します。
●次の投資に活かす
現在の投資案件の結果を踏まえて、次回の案件選びや資金配分に役立てます。
定期的に経過を確認することで、より適切な投資判断を続けやすくなります。
まとめ

不動産クラウドファンディングには、元本割れのリスクがあります。
自然災害や経済の変動、不動産市場の低迷など、資産価値が下がる要因を把握することが、適切な対策につながります。
損失を抑える方法として、優先劣後出資制度を採用している運営会社を選ぶのが有効です。
また、少額から始め、経験を積みながら慎重に判断することで、安定した運用を目指せます。
不動産クラウドファンディングの仕組みを理解し、準備を整えれば、より自分に適した投資が進められるでしょう。