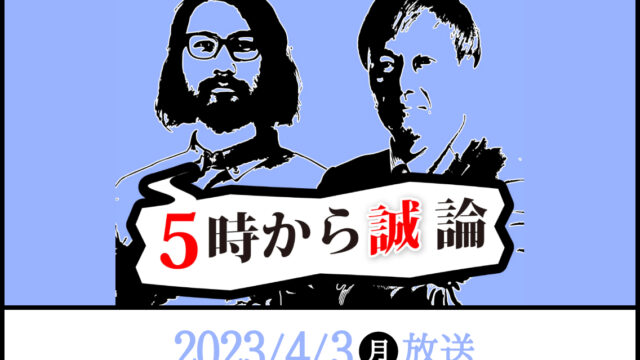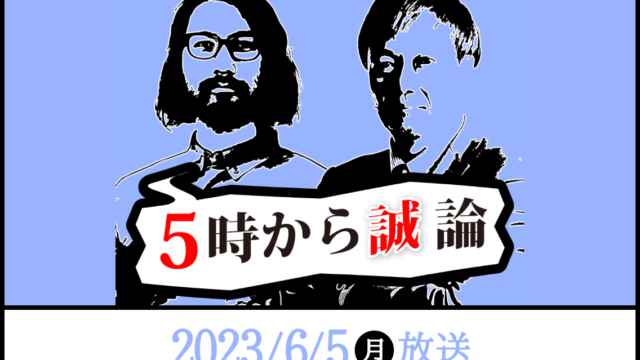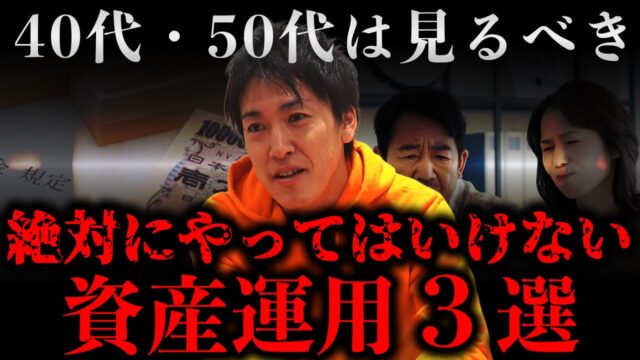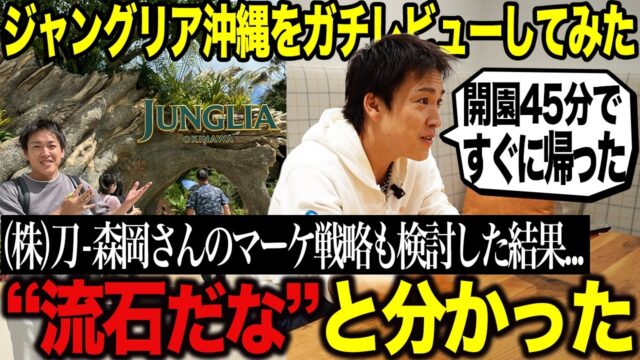FIT制度終了後の売電価格
電気の買取価格について解説します。
繰り返しになりますが、FIT制度の期間である20年間は国によって電力会社の買取が義務付けされています。
しかし、この期間を超えると電力会社は電気を買い取る義務がなくなり、固定価格よりも低い価格で取引されることが予想されています。
実際に10年で買取期間が終了する10kW未満の家庭用太陽光発電では、2022年のFIT価格17円に対し、FIT終了後の買取価格8.5円と大きく引き下げられています。
※FIT終了後の買取価格は電力会社によって異なります
この例はあくまで家庭用太陽光発電の場合であり、投資用太陽光発電も同様の割合になるとは言えません。
しかし、固定買取制度が終了したことによって利益が出なくなるというケースは充分に考えられます。
では、20年後どのような運用をしていけばいいのでしょうか。
参考|資源エネルギー庁「固定価格買取制度」
参考|東京電力エナジーパートナー「再エネ買取標準プラン」

初心者向け太陽光発電投資とはどんな投…
20年後の買取価格終了後の収益はどうなっていく?

FIT制度の終了により、20年後には売電価格が大幅に下がる可能性があります。
さらに、設備自体の劣化や維持コストの増加も収益に影響を与える要因となるでしょう。
ここでは、20年後以降に考慮すべき重要なポイントを整理します。
パネルの寿命と発電効率の低下
太陽光パネルは耐用年数が長いものの、20年を超えると発電効率が徐々に低下していきます。
一般的には、設置から20年経過すると初期性能の80〜90%程度に落ち込むケースが多いとされています。
発電量が減少すれば売電収入も減るため、長期運用を前提とする場合は劣化リスクを想定しておくことが大切です。
また、設備メーカーによる保証期間も多くが20〜25年程度で設定されており、それ以降は自己負担で修理・交換に対応しなければなりません。
メンテナンス・修理費用の累積
太陽光発電システムは定期的な点検と保守が求められるため、20年を超えると累積コストも無視できない水準に達します。
特に、パワーコンディショナーなど主要機器の寿命は10〜15年程度とされており、20年運用中に一度は交換が必要になる可能性が高いでしょう。
こうした設備更新や不具合対応に数十万円単位の出費が発生することを見込んでおかなければ、収益シミュレーションにズレが生じる恐れがあります。
安定運用を目指すなら、メンテナンス予算をあらかじめ資金計画に組み込んでおくことが現実的です。
売電終了後の収益モデル(自家消費化 or 撤去)
FIT期間終了後、売電単価が大幅に下がった場合には、発電した電力を自家消費に回す選択肢も考えられます。
自宅や施設で使用する電力をカバーできれば、買電コストの削減につながり、間接的な経済効果を得ることが可能です。
一方で、パネルや機器の老朽化が進んでいる場合は、売却や撤去を検討する選択肢も現実味を帯びてきます。
撤去には費用負担も伴うため、20年後の発電効率や維持コストを総合的に見極めたうえで、最適な対応を選ぶ必要があります。
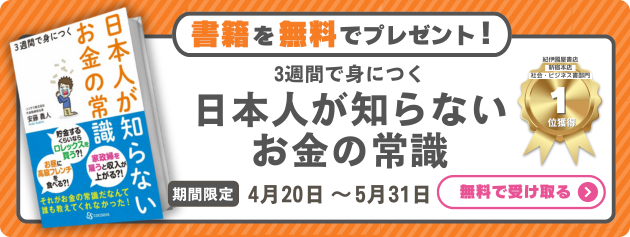
FIT制度が終了した後の運用方法

FIT制度が終了した後の運用方法については、以下の4つの選択肢が考えられます。
(2)他社の電力会社と契約を結ぶ
(3)自家発電に切り替える
(4)売却する
(1)同じ電力会社と契約を結び直す
FIT制度の適用期間が終了したからといって売電できないということはありません。
固定買取期間終了後も引き続き契約を結ぶことが可能です。
しかし、FIT終了後は契約や価格は事業者と電力会社の双方の合意が必要になります。
その場合、買い手である電力会社から提示される価格が大きな影響力を持つことが予測されます。
(2)他社の電力会社と契約を結ぶ
また、同じように売電する方法として電力会社を変更する方法があります。
電力会社を替えるメリットは、売電価格を比較しながら決められる点です。
家庭用太陽光発電の買取価格では、新電力会社の方が大手会社よりも高い値段で買い取られることもあります。
調査や手続きの手間は必要ですが、調べる価値は充分にあります。
(3)自家発電に切り替える
売電契約を結ばない場合は、自家発電への切り替えを検討することができます。
FIT制度が終了後に売電価格が下がることにより、買電価格の方が高くなる可能性があり、自家発電に切り替える方が費用対効果が高くなる可能性も考えられます。
できる限り自家発電でまかない、余剰分を売電に回すといった方法も選択肢に入れておくことが無難です。

投資をするなら太陽光発電投資と不動産…
(4)売却する
四つ目は太陽光発電を売却するという選択肢です。
太陽光発電には毎年維持費や管理の手間、固定資産税などが発生します。
また、機器の老朽化により交換が必要な場合もあるかもしれません。
「売電価格」「継続費用」「機器の交換費用」など複合的に判断し、もしマイナスの収支になりそうなのであれば、FIT制度終了と同時に売却をすることで余計な負担や費用を節約できます。
以上がFIT制度の終了後の選択肢になります。
では実際に何を基準に判断すればいいのでしょうか。
ここからは選ぶ時の基準と注意点について解説します。
太陽光発電投資を継続する時の基準と注意点

継続するときの基準
「継続するか」それとも「売却するか」と迷ったときには、機器の交換・修繕費用を含めた収支で判断してください。
FIT制度が適用している20年間との違いとして、機器の寿命を考慮する必要があります。
例えば、売電価格が下がった状態で部品の交換をしたとすると「どのくらいの期間で回収できるのか」「修繕費用に見合うだけの収入はあるか」など、売電価格による収入・税金などの維持費用・機器の交換の3つの視点で判断するようにしてください。
注意点
太陽光投資を継続する際に注意していただきたいのは以下の2点です。
2:電力会社との契約時に条件を確認
どのような目的で太陽光投資を行うかにもよりますが、買電と売電の差が大きいようでしたら、積極的に自家発電に切り替えるもの一つです。
電力会社からの買電を削減することで、トータルの収支を改善できる場合があります。
また、電力会社と契約を結ぶ際にも注意が必要です。
同じ会社でも対象のエリアやプランが異なる場合があるので、比較検討する際にも充分に気を付けてください。

太陽光発電投資が減価償却で節税になる理由
20年後に後悔しないための出口戦略

ここまで、FIT制度が終了する20年後の状況や運用方法、注意点について解説してきました。
これらのことを踏まえ、最後に20年後に後悔しないための出口戦略について解説します。
(1)FIT制度終了後のことをあらかじめ考えておく
FIT制度により20年間の買取保証がされてはいますが、事前に20年後の運用について考えておくことをおすすめします。
一例として事前に考えておくメリットを紹介します。
・土地や設備を売却しやすい
・維持費や固定資産税などの支出を把握できる
・部品・設備の交換時の判断材料になる
FIT終了後のことを決めてしまう必要はありませんが、選択肢を複数持つことで余裕が生まれ適切な判断の助けになります。
(2)柔軟に対応する
上記で事前に選択肢を持つことの重要性を解説しましたが、そうは言っても20年という時間はとても長いです。
この20年間で制度や環境が変わることがあるかもしれません。
実際に2022年4月からFIP法という制度が導入され、2023年まではFIT制度とFIP制度のどちらも選択できるようになっています。
このように制度変更や情勢を考慮し柔軟に対応を変更していくことも必要です。
少なくとも年に1回は「資源エネルギー庁の公式サイト」などを確認し、運用方針を繰り返し改善していくことをおすすめします。
(3)リスクを分散させる
太陽光発電投資もその他の投資と同様にリスクを分散させておくことが重要です。
FIT制度で20年運用した例がないことと、今後20年間でどのような変化があるか分からない以上、太陽光発電投資だけに集中投資することは危険と言えます。
最悪の事態も想定し投資戦略・人生設計を行うことが大切です。

太陽光発電投資ってどんな仕組みで利益…
まとめ

ここまでFIT制度が終了する20年後について運用方法や注意点を紹介してきました。
太陽光発電投資は政府が買取価格の保証を設定している珍しい投資商品です。
一方でFIT制度が終了した20年後の出口戦略については、不確定なことが多いのも事実です。
そのため、運用方法について事前に選択肢を準備しておくことが重要になります。
今回の記事を参考にFIT後の運用について考えてみてはいかがでしょうか?
弊社はライフデザイン事業に注力しており、幅広い人生設計の選択肢の一つとして「太陽光発電投資」があなたの資産形成に合うのか?という視点でご提案・アドバイスをしています。
太陽光発電投資だけを扱う業者ではないからこそ、中立的で客観的なアドバイスやサポートが提供できます。
太陽光発電投資はもちろん、ライフプランのお悩みや不安などもお気軽にご相談ください。
基礎が学べる!無料オンラインセミナーへ参加しよう
ココザスの無料オンラインセミナーでは、国が保証してくれる仕組み・消費税還付によって翌年に〇〇〇万円返ってくる仕組みなどの基本知識を学ぶことができます。
また、物件選定のポイントなど具体的な内容もお話していきます。
太陽光発電投資のメリット・デメリットを分かりやすく解説していくため、これから太陽光発電投資を始めたいと検討している人におすすめです。