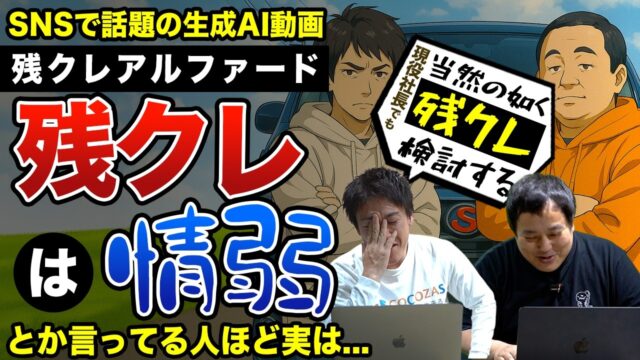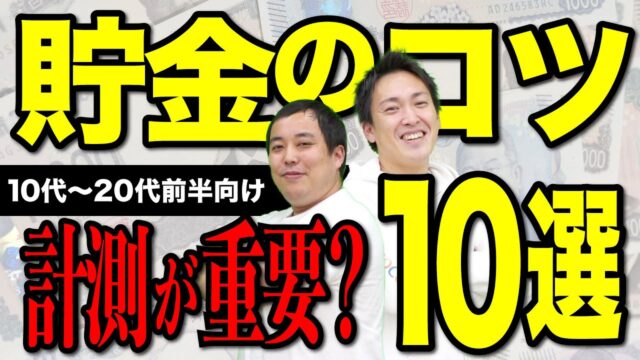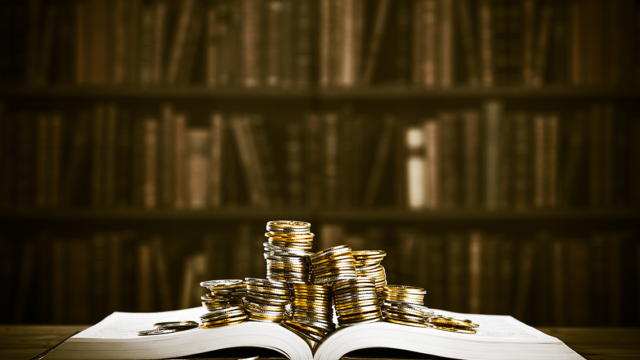ボーナスはいくら貯金するのが正解?使い道と貯金割合の目安

ボーナスの一部を、どのくらい貯金に回せば良いか迷う方は少なくないでしょう。
こちらでは、生活スタイルに応じたケースと、目的に合わせたボーナスの配分方法を紹介します。
独身・共働き・子育て世帯それぞれのモデルケース
ボーナスから貯金に回す割合は、家庭の状況によって変わります。
一般的な目安は、以下の通りです。
・独身(実家暮らし):手取りの50〜70%
住居費や生活費が抑えられるため、貯金に回しやすい環境になっています。
・共働き世帯:手取りの30〜50%
支出はあるものの2人分の収入で生活費をまかなえるため、一定の余裕があります。
・子育て世帯:手取りの20〜30%
教育費や日常の支出がかさみやすく、貯金に回せる割合は低めになります。
目的別に考えるボーナスの振り分け方(住宅・教育・緊急資金など)
ボーナスは「何割貯金するか」だけでなく、目的に応じて分けて考えることで資金の使い道が明確になります。
たとえば、次のようなイメージです。
・教育費:子どもの進学や学用品購入に備え、長期的に積み立てる
・緊急資金:医療費や修理代などの急な出費に対応するため、すぐ使える形で確保する
金額の決め方や具体的な分け方は、このあと詳しく解説します。
ボーナスをいくら貯金するか決めるために確認したい3つの数字

貯金額を決めるには、なんとなくの感覚ではなく、今の家計状況や将来の支出を整理することが大切です。
こちらでは、判断材料となる3つの数字を紹介します。
(1) 毎月の家計収支(収入と支出のバランス)
まず確認しておきたいのは、月収の中で生活費や固定費をどの程度まかなえているかです。
月々の支出が収入を下回り、黒字が出ている状態であれば、日常生活に余裕があると考えられます。
この余裕がある分、ボーナスを急な支出にあてる必要が少なくなり、貯金に回せる割合を高く設定しやすくなるでしょう。
たとえば毎月2万円の黒字があれば、ボーナスのうち生活費への補填が不要になります。
それにより、まとまった額を貯金に回すことが可能です。
(2)現在の貯金残高(手元にいくらあるか)
今どれくらいの貯蓄があるかによって、ボーナスをどれだけ貯金に回せるかの判断が変わります。
目安として、生活費の3〜6ヶ月分を「生活防衛資金」として確保できていれば、それ以上は目的別の貯金や投資にまわせる余力と考えられます。
たとえば月25万円の生活費なら、75万〜150万円を超える貯金があると、ボーナスの大半を貯金にあてる判断も可能です。
なお、普通預金・定期預金・証券口座など、貯金の置き場所によって使いやすさが異なります。
それぞれの口座にどれくらいあるのかを分けて把握しておくと、貯金計画が立てやすくなります。
(3) 目的ごとの必要資金(住宅・教育・老後などの将来支出)
将来の支出をあらかじめ見積もっておくと、ボーナスのうちどれくらいを貯金に回すか見通しが立てやすくなります。
たとえば住宅の頭金には、物件価格の2割を目安に600万〜800万円程度を用意するケースが一般的です。
教育費は進路によって大きく異なりますが、すべて公立の場合で約820万円、すべて私立で下宿も含めると2,000万円を超える場合もあります。
老後資金については、公的年金の不足分を補う形で2,500万円程度の準備が推奨されています。
それぞれの目標額と時期を整理しておけば、ボーナスから毎年どれくらい積み立てれば良いかが見えてくるでしょう。
参考|全国銀行協会「住宅資金の作り方、頭金の目安を教えてください」、日本政策金融公庫「教育資金はいくら必要?かかる目安額をご紹介」、一般社団法人 全国銀行協会「教えて!くらしと銀行」
ボーナスの貯金額を決めて行動に移すための3ステップ

家計の状況や将来の支出が把握できたら、ボーナスの使い方を具体的にする段階に入ります。
貯金額の決定から計画の調整までを、3つの流れに分けて紹介します。
STEP1.目標と必要額をもとに貯金額を決める
前項で整理した家計収支や現在の貯金残高、将来の必要資金をふまえて、ボーナスからいくら貯金するかを具体的に決めます。
ここで大切なのは、「なんとなく余った分を貯める」のではなく、目標金額から逆算して金額を明確にすることです。
たとえば住宅資金に毎年30万円かかる場合は、夏冬の賞与で15万円ずつ貯めていくなど、計画に基づく配分が必要になります。
優先順位をつけ、無理のない範囲で数字に落とし込むことで、実行しやすくなります。
STEP2.支給前に使用分と貯金分を分ける計画を立てる
計画的に貯金するには、支給後ではなく「支給前」に使い道を決めておくことが重要です。
たとえば40万円のボーナスが入ると分かっているなら、「〇万円は貯金」「〇万円は旅行」といったように、あらかじめ振り分けておきます。
家族と共有したり、用途メモを作ったりすることで、感情に流されず計画通りに使いやすくなります。
「残ったら貯金する」ではなく「貯金を先に確保して、残りで使う」の順番で考えましょう。
STEP3.実行後は月1回の見直しで軌道修正する
貯金計画は、一度立てて終わりではなく、実行後の定期的な振り返りも大切です。
毎月1回、家計簿や貯金額の進捗をチェックし「予定通りに積み立てられているか」「想定より支出が増えていないか」を確認してみてください。
出費が増えて目標に届きにくい場合は「積立額を調整する」「使いすぎた項目を見直す」といった対策がとれます。
家計簿アプリやグラフ機能を使えば、収支の変化がひと目でわかるため、状況に応じた対応がしやすくなります。
ボーナス貯金を確実に続ける仕組みの作り方

貯金の金額を決めても、忙しい日々のなかで実際に振り分けるのを忘れてしまい、思うように貯まらないこともあるでしょう。
意識しなくても続けられる仕組みや、途中で挫折しない工夫を取り入れることで、計画を実行に移しやすくなります。
こちらでは、ボーナス貯金を着実に進めるための具体的な対策を紹介します。
(1)支給日に自動で振り分ける設定をしておく
ボーナスは、自動で振り分けられるようにしておくと確実に貯金へ回せます。
たとえば、支給日に決まった割合を定期預金や別口座へ自動で振り分けるように設定しておきます。
ネットバンキングや給与振込先の銀行では、定額自動振替などの機能が使えることがあります。
銀行によっては対応していない場合や、支給日に合わせるのが難しいこともあるため、事前に利用している口座で確認しておくと安心です。
「30%は貯金」「10%は投資」など、あらかじめ比率を決めておくと判断にも迷いません。
やる気ではなく仕組みで管理することで、貯金を継続しやすくなります。
(2)「使う分」も明確に分けて満足感を得る
すべてを貯金に回そうとすると、我慢が続かず途中で挫折しやすくなります。
あらかじめ「これは使っていい」と決めた金額を確保しておくと、心の余裕と満足感を得られます。
たとえば40万円のうち5万円はレジャーや外食、趣味に使うなど、ご褒美的な要素を組み込むのが効果的です。
使う分は別口座や現金で分けておくと、無意識に使いすぎる心配も減ります。
全額を貯めるのではなく、計画的に「使う」ことでストレスなく貯金が続けられるようになります。
(3)毎月の生活をボーナスに頼らない設計にする
ボーナスは“あれば助かる”ものであり、“ないと困る”設計にはしないことが大前提です。
月収だけで生活が完結するように整えておけば、ボーナスは貯金や将来の出費に備える資金にあてやすくなります。
そのためには、スマホ代や保険、使っていないサブスクなど、固定費の見直しから始めるのが有効です。
たとえば手取りの8割以内で生活を組み立てておけば、急な支出にも柔軟に対応できます。
「ボーナスは上乗せ」として位置づけることで、収入が予想外に減った年でも慌てず対応しやすくなるでしょう。
ボーナスの一部を投資に活かす方法と注意点

ボーナスの中から少額でも投資に回すことで、将来の資産形成につながります。
こちらでは、投資への活用法と注意点を紹介します。
NISAやiDeCoを使って少額から投資を始める
ボーナスの一部をNISAやiDeCoに回せば、将来に向けてお金をじっくり育てていけます。
NISAは、投資で得た利益が非課税になる制度で、毎月決まった額を積み立てていくのが基本です。
あらかじめボーナスから半年分や1年分を取り分けておけば、その期間は口座残高から自動で積立が進みます。
iDeCoも同様に積立型の制度で、老後資金づくりに適しています。
掛金が全額所得控除の対象になる点がメリットです。
NISA、iDeCoのどちらも長期投資に向いており、手間や負担を増やさず始められるのが魅力です。
投資を進める上での注意点
1.投資は元本割れのリスクを前提に考える
投資は預金と違い、元本が保証されているわけではありません。
とくに短期間で成果を出そうと焦ると、値動きの大きい商品を選びがちです。
その結果として、元本割れのリスクが高まります。
期待が先行して判断を誤らないよう、冷静にリスクと向き合う姿勢が欠かせません。
2.ボーナス全額を投資に回さず、余剰分だけにとどめる
ボーナスをすべて投資に使うと、生活費や緊急時の備えが足りなくなるリスクがあります。
また、投資資金はすぐに引き出せないケースも多いため、現金の確保は最優先です。
投資と生活資金はしっかり線引きし、「余った分だけを使う」という姿勢が重要です。
いざという時に困らないようにするためにも、投資金額の上限はあらかじめ決めておきましょう。
よくある質問とその答え

ローンの繰上げ返済と貯金、どちらを優先するべき?
金利が低ければ貯金を優先するのが一般的です。
たとえば、固定金利1%未満の住宅ローンであれば、無理に返済を進めるよりも、生活防衛資金や将来のための資金を手元に残しておくほうが安心です。
一方で、精神的な負担を軽くしたいと考えて、あえて繰上げ返済を選ぶケースもあります。
貯金が苦手でも続けられる方法はある?
貯金は「仕組み」で管理したほうが長続きしやすくなります。
自動積立や口座振替、家計簿アプリの活用で、意識せずに貯める仕組みを作るのが有効です。
さらに、あらかじめ「この金額までは使っていい」と決めておくと気持ちに余裕が生まれ、貯金が習慣化しやすくなります。
ボーナスが減った年はどう対処する?
あらかじめ変動を想定した設計にしておけば、無理なく対応できます。
ボーナスありきで固定支出を増やすのではなく、「ボーナスはあったら使う」という位置づけにしておくと、急な変化にも振り回されにくくなります。
また、何%ではなく「いくら貯める」と金額で決めておけば、減額時の見直しも簡単になるでしょう。
ボーナスを全部現金で置いておくと損ですか?
すぐに損となるわけではありません。
ただし、ずっと現金のままにしておくと、資産が目減りする可能性はあります。
普通預金の金利はほとんどつかず、物価が上がればお金の価値は実質的に下がってしまいます。
まとめ|迷いなくボーナスを活かすために

ボーナスをいくら貯金すべきか迷ったときは、まずは家計の現状を整理することから始めましょう。
毎月の収支や今ある貯金、これからかかる大きな支出を見直すと、おおよその目安がつかめてきます。
次に、住宅資金・教育費・急な出費など、目的に応じて使い道を分けてみてください。
あらかじめ振り分けのルールを決めておけば、あとは自動積立や口座の使い分けで自然と貯めやすくなります。
完璧を目指さなくても大丈夫です。
できることから一つずつ進めていきましょう。