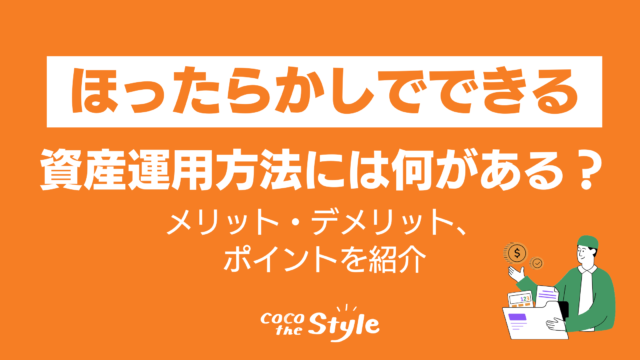iDeCo改悪と言われている内容とは?

ここではiDeCo改悪と言われている内容について紹介します。
改悪された内容とは
iDeCo制度改正で「改悪」と言われているポイントは、一時金での受け取り時に適用される退職所得控除のルール変更です。
2025年6月に年金制度改正法が成立し、加入可能年齢が65歳か70歳へ、さらに企業型DCの拠出限度額の拡充などが予定されています。
その中で、今後予定されている法改正の中にiDeCoの受け取り時の「5年ルール」が「10年ルール」に変更になると言われているのです。
これまでの制度では、退職金とiDeCoの一時金をそれぞれ5年以上の間隔を空けて受け取ることで、両方に対してそれぞれの退職所得控除が適用され、課税負担を大幅に軽減することが可能でした。
このルールは「5年ルール」と呼ばれ、出口戦略として非常に有効な節税方法とされていたのです。
しかし、改正後はこの「5年ルール」が「10年ルール」に延長されると報じられています。
つまり、iDeCoの一時金と退職金を別々に受け取る場合でも、その間隔が10年未満だと控除の重複適用が認められず、一方にしか退職所得控除が使えないことになるのです。
例を挙げると、60歳でiDeCoを一時金として受け取り、65歳で退職金を受け取ると、従来なら両方に控除が適用され非課税枠が最大限使えたものの、改正後はその5年の間隔では足りず、どちらか一方にしか控除が使えないという制度になります。
この改正によって、特に60代前半にiDeCoの一時金を受け取り、数年後に退職金を一括で受け取る予定の人は、想定以上の税金が発生し、手取り額が大きく減少する恐れがあります。
このように、制度全体としては掛金の上限引き上げなど「積立面の拡充」がある一方で、「受け取り面の制限強化」は見落とされがちです。
長期運用を前提とするiDeCoにおいて、出口戦略の自由度が下がることは、制度の根幹に関わる重大な変更であり、多くの専門家が「実質的な改悪」と位置づけています。
制度変更の背景について
iDeCo制度改正の背景には、「過度な節税の抑制」と「税制の公平性の確保」があります。
これまで、iDeCoと退職金を5年以上の間隔で一時金として受け取ることで、それぞれに退職所得控除を適用でき、税負担をほぼゼロに抑えることが可能でした。
しかし、こうした節税スキームが広く使われるようになり、高所得者や資産形成に積極的な層に税制優遇が集中するという不公平が指摘されていました。
また、国の財政悪化も見直しの要因です。
高齢化により社会保障費が膨らむなか、所得控除による税収減を抑える必要があると判断されました。
その結果、控除の重複適用には10年以上の間隔が必要となる方向で調整されており、制度の本来の趣旨を守る目的で実質的な課税強化が進められています。
iDeCo改悪が資産運用に与える影響とは?

iDeCoは長期積立・運用を前提とした制度ですが、改正の影響は出口戦略に大きく及びます。
ここでは、運用や節税に対するリスクを3つ紹介します。
(2)節税効果の低下リスク
(3)企業型DC・NISAとの比較
ひとつずつ確認していきましょう。
加入者の負担増の可能性
iDeCoの改正により、加入者の負担増の可能性が高まるリスクが挙げられます。
iDeCoの出口での受け取り方によっては、実質的な手取りが大きく減少するリスクが出てくるのです。
特に、60歳でiDeCoを一時金で受け取り、65歳で退職金を受け取るようなケースでは、改正前であれば両方に退職所得控除が適用されていましたが、今後は間隔が10年未満だと控除が圧縮され、税金が二重に課される形になります。
これまで「出口で節税できるから安心」とされていたiDeCoの設計が崩れることで、将来の受け取り時に資金計画を見直さざるを得ない加入者が増える可能性があります。
節税効果の低下リスク
節税効果の低下リスクも大きな懸念点の一つです。
iDeCoの魅力は「所得控除」「運用益非課税」「退職所得控除による受け取り時の節税」の3つのメリットがありました。
しかし、今回の制度変更によって受け取り時の優遇が制限されることで、節税効果が低下する可能性があります。
たとえ運用で利益が出ても、課税が重くなれば実質利回りは大きく減少します。
結果として、iDeCoが「節税メリットが薄い制度」として見直される恐れもあり、今後は「いくら積み立てるか」だけでなく、「いつ・どうやって受け取るか」が資産形成の成否を分ける重要な判断要素となるでしょう。
企業型DC・NISAとの比較
改正を受けてiDeCoのデメリットが浮き彫りになる中で、企業型DCや新NISAなど他の制度との比較検討の必要性が高まっています。
企業型DCは拠出限度額が高く、企業によるマッチング拠出などの恩恵もあり、受け取り方法も柔軟です。
NISAは運用益が非課税で、いつでも引き出し可能という高い自由度が魅力です。
しかし、iDeCoは60歳まで原則引き出せず、受け取り時の税制優遇にも制限が加わる可能性があるため、制度としての流動性や柔軟性で見劣りするようになってきました。
目的やライフステージに応じて、どの制度を選ぶか慎重に検討する必要があります。
iDeCoは続けるべき?

制度変更によって、全ての人にとって不利になるわけではありません。
ここでは、iDeCoをやめた方がいい人・続けたほうがいい人の特徴を紹介します。
やめたほうがいい人の特徴
iDeCoをやめたほうがいい人は、以下の3つの特徴に該当する方です。
2025年以降、退職金とiDeCoの一時金受け取りが10年以内だと、退職所得控除が重複して使えない可能性が高まります。
60歳でiDeCo、65歳で退職金を受け取ると、どちらか一方が課税対象になってしまい、想定以上の税金がかかるリスクがあります。
一括での受け取りは本来有利な手段でしたが、今後は課税負担が重くなる可能性があるため、節税目的での一時金受け取りが戦略として成り立たなくなる恐れがあります。
引き出し自由なNISAと比べると、60歳まで資金を自由に引き出せないiDeCoは流動性に乏しく、柔軟性も低いのが難点です。
自営業者や転職が多い人など、将来設計に不確定要素が多い人は、他の制度のほうが適しているケースもあります。
続けたほうがいい人の特徴
一方でiDeCoを続けた方がいい人の特徴は以下の3点に該当する方です。
iDeCoは年金として5年〜20年に分けて受け取ることも可能です。
年金形式であれば公的年金等控除が適用され、税負担を抑えやすいです。
改正の影響を受けにくい受け取り方なので、長期で分割受給できる人には今後も有効な制度です。
掛金が全額所得控除になるiDeCoは、所得税率の高い人ほど節税効果が大きくなります。
特に年収800万円以上の会社員などは、年間で数万円〜十数万円単位の節税メリットが見込め、積立期間中は恩恵が大きいため、続ける理由は十分あります。
20年、30年といった超長期スパンで積み立てを考えている人にとっては、運用益が非課税になるiDeCoは有利です。
出口での課税は意識しつつも、資産形成段階でのメリットは依然として魅力的なため、ポートフォリオの一部としてiDeCoを活用し続ける価値はあります。
▼ 合わせて読みたい
iDeCoの改悪に備えるための対策

では具体的にiDeCoの改悪に備えるための対策にはどのような方法が挙げられるのでしょうか。
ここでは2つの対策を紹介します。
年金受け取りを検討する
iDeCoの受取方法として、年金受け取りを選択する方法があります。
年金で受け取る場合は雑所得に分類され、「公的年金等控除」が適用されるため、控除枠の中に収まれば所得税・住民税がかからない、あるいは軽減されます。
これまで、iDeCoを一括で受け取ると、退職金とは別に退職所得控除が使え、ほぼ非課税で済むケースが多くありました。
しかし、制度改正後は退職金との受取時期が10年以内であれば控除が圧縮され、課税対象が増える可能性があります。
年金受け取りを選択すれば、毎年の課税所得をコントロールしながら受け取ることができます。
年金受け取りは5年〜20年の範囲で期間を自由に設定できるので、ライフプランや収入状況に合わせた柔軟な出口戦略が可能になります。
ポートフォリオの見直し
定期的なポートフォリオの見直しをすることも対策の一つです。
iDeCoは原則として60歳まで引き出せない長期積立型の制度であり、運用期間の終盤に差し掛かると「資産の安定性」が重視されます。
例えば、60歳での一時金受け取りを検討していた人が、税負担を避けて65歳以降の年金受け取りに変更する場合、その5年の期間で資産価格が大きく変動すると、手取り額や生活資金に大きな影響がでる可能性があるのです。
つまり、出口戦略の再構築にあわせて、運用リスクの低減も同時に検討しなければならないのです。
そこで重要になるのが、リスク資産から安定資産へのポートフォリオの変更です。
60歳前後を迎えたら、株式や外国資産の比率を抑え、定期預金型や保険型、国内債券などの元本確保型商品に切り替える方法もあります。
これにより、価格変動による資産目減りのリスクを避け、確実に受け取れる金額を維持することが可能です。
また、インフレリスクや金利上昇局面にも対応できるよう、債券や物価連動型資産の活用も選択肢になります。
単に「守り」に入るだけでなく、資産を分散して安定と成長のバランスを保つことが、これからのiDeCo運用では求められます。
ポートフォリオを見直しする際のステップ

ここではポートフォリオを見直しする際のステップを3段階に分けて紹介します。
(2)リスク分散を考慮する
(3)専門家に相談する
ひとつずつ確認しておきましょう。
投資目標を決める
はじめに、「いつまでにいくら必要になるか」という投資目標を決めましょう。
例えば「65歳から年間200万円を20年間取り崩したい」「医療費などの予備資金として300万円は元本確保したい」など、具体的な目的・金額・期間を設定することで、運用すべき資産規模とリスク許容度が把握できます。
iDeCoでは運用期間中の拠出額上限があるため、積み上げた資産でどこまで増やせるのかをシミュレーションすることが可能です。
また、老後収入とのバランスを踏まえ、iDeCoで補うべき金額を明確にすれば、他の資産運用への資金割合を減らすタイミングや運用終了年の設定もスムーズになることでしょう。
最初に投資目標を決めることで、適切な運用額と期間の設定が可能となるため、ポートフォリオを見直しする際は最初に検討していきましょう。
リスク分散を考慮する
次に、リスク分散を考慮して投資先を決めていきます。
例えば株式だけに頼っていると、暴落時に大きな損失を被る可能性があります。
特にiDeCoのように、60歳以降に資産を受け取る前提の制度では、老後直前の下落が家計に大きな打撃となるため、取り崩し時期に向けたリスク管理が非常に重要です。
20代や30代などの若い頃は、株式などのリスク資産で積極的にリターンを狙うことも有効です。
たとえ投資資産が一時的に値下がりしても、長期間運用を続けることで回復を待つことができます。
しかし、50代後半〜60代は、数年後にはiDeCoの資金を取り崩し始めるタイミングです。
50代や60代の段階で株価が暴落すると、損失を回復させる時間がなく、そのまま値下がりした状態で取り崩すリスクが高くなります。
そのため、リスクの高い資産を徐々に減らし、安全性の高い資産(債券・定期預金・保険など)を増やすことが推奨されるのです。
このように、年齢とともにリスクを考慮して資産配分を調整していく方法は、老後の資産保全に効果的です。
専門家に相談する
ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することで、よりリスクや投資目標に合わせたポートフォリオを構築できます。
iDeCoは税制優遇制度であるため、受け取り方によって実際の手取り額が大きく変わります。
運用商品選びだけでなく、受取時期の調整や一時金・年金形式の選択は、税務や社会保険制度と深く関わってきます。
そのため専門的な知識が必要となる資産運用ではありますが、独学では誤った知識を身に付けてしまうリスクがあり、なおかつ投資詐欺などの被害に遭う可能性も0ではありません。
特にiDeCo受け取りと退職金が近いタイミングの人や、医療費控除や扶養関係が変動するタイミングにある人は、節税と手取り最大化の観点からプロの意見が不可欠です。
ファイナンシャルプランナーなどの資格を持った人であれば、その経験と豊富な知識から疑問や不安を抱えたまま運用を続けるリスクを減らしてくれるでしょう。
ココザスはファイナンシャルプランナーとして投資や資産運用のサポートを行っております。
また、お客様の資産状況や家族構成、将来的なライフプランから適切な投資計画のアドバイスもしています。
さらに税金アドバイスや余剰金作りのための家計の見直し、保険やローンなどについての相談も承っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ

2025年のiDeCo改正は、「一時金受け取り」における課税上の不利が指摘され、改悪と捉えられる面があります。
しかし、制度全体としての節税効果や長期運用のメリットは依然として健在であるので、一概に制度自体が悪いとは言い切れません。
iDeCoを運用する上で大切なのは、制度変更の本質を理解したうえで、受け取り方法や資産配分を見直し、将来に備えることです。
やみくもにやめるのではなく、専門家と相談しながら自分に合った資産運用方法なのかを見極め、適切なポートフォリオを構築するようにしましょう。