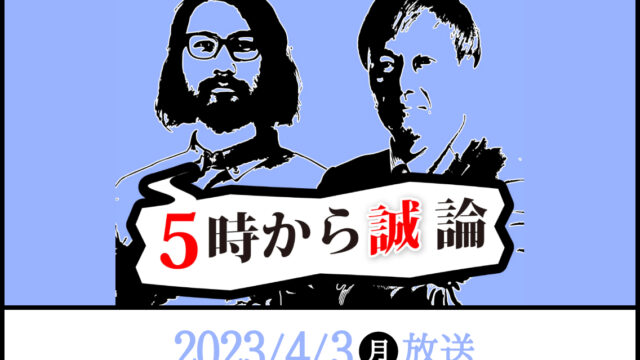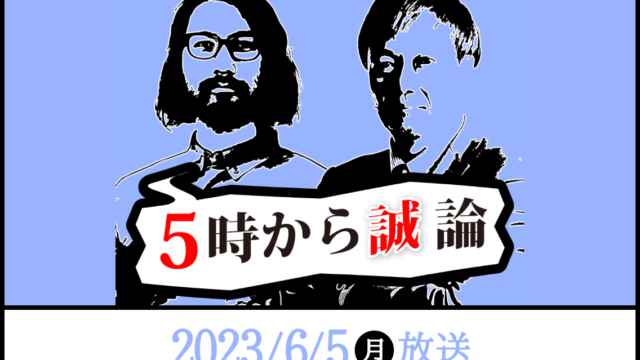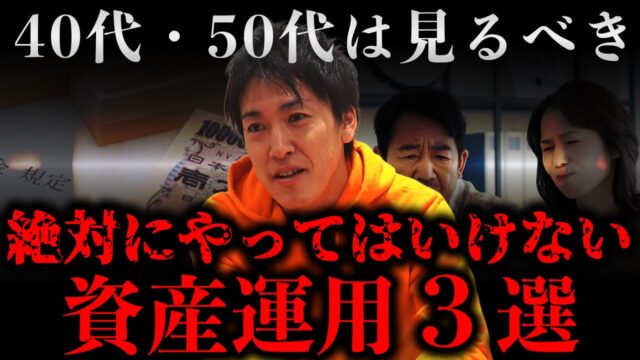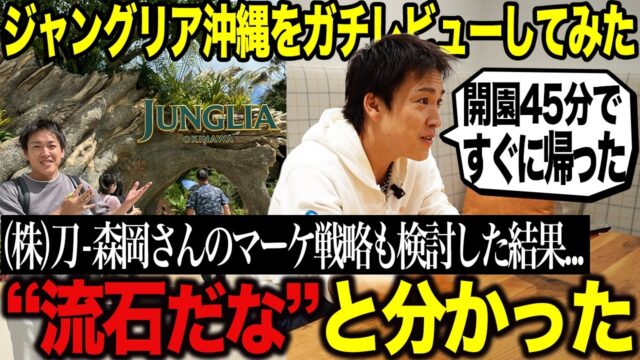金投資信託とは?

金投資信託とは、投資家から集めた資金を運用会社がまとめて金に投資し、その運用成果を投資家に分配する金融商品です。
金価格の動きに応じて基準価額が上下するため、金価格が上昇すれば利益が期待でき、下落すれば損失が出る可能性もあります。
現物の金を購入するのに比べて少額から投資でき、保管や管理の手間が不要なのが大きな特徴です。
金投資信託の仕組み
具体的には以下のような流れで運用されています。
投資信託は、証券会社や銀行を通じて購入できます。
購入単位は1口から数千円程度で始められるものが多く、現物の金を買う場合と比べて非常に少額で投資が可能です。
購入後、投資家は「基準価額」というファンドの価値を保有することになります。
集められた資金は、運用会社が金現物や金先物などに投資します。
先物連動型:将来の金価格に連動する先物取引で運用
この運用方法に応じて、ファンドの基準価額は金価格の動きと連動します。
投資信託の価値は、金の市場価格に応じて上下します。
金価格が上がれば基準価額も上昇し、下がれば基準価額も下落します。
運用中には、信託報酬などのコストが差し引かれるため、基準価額は金価格と必ずしも一致しない点に注意しましょう。
投資家は基準価額の上昇による値上がり益や、ファンドが分配金を支払う場合にはその分配金を受け取ることができます。
ただし、基準価額が下落すれば元本割れするリスクもあるため注意が必要です。
現物金投資との違い
現物金投資は、金の延べ棒やコインを直接購入して保有する方法です。
これに対して金投資信託は、金そのものを保有するわけではなく、運用会社が管理する金や金先物に投資します。
それぞれの違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 現物金投資 | 金投資信託 |
|---|---|---|
| 最低投資額 | 数十万円〜 | 数千円〜 |
| 保管 | 自宅や金庫、貸金庫が必要 | 運用会社が管理、保管不要 |
| 流動性 | 売買に時間・手間がかかる | 証券会社でいつでも売買可能 |
| 手数料 | 購入・販売時にかかる | 信託報酬など運用コストがかかる |
| 現物引き出し | 可能 | 不可 |
現物金投資は手元に金を保有できる安心感がありますが、盗難や保管費用のリスクがあります。
一方、金投資信託は実物を持たず運用会社が管理するため手間がかからず流動性も高いのが特徴です。
ただし信託報酬などのコストがかかり、基準価額は金価格や運用条件によって変動するため、長期運用ではリターンに影響する点に注意が必要です。
ETF・純金積立との違い
金投資にはETF(上場投資信託)や純金積立もありますが、金投資信託との違いは次のとおりです。
| 項目 | 金投資信託 | 金ETF | 純金積立 |
|---|---|---|---|
| 取引所上場 | なし | あり | なし |
| 購入単位 | 証券会社で1口単位 | 株式のように単位株で売買 | 月々数千円から積み立て可能 |
| 流動性 | 証券会社で売買 | 株式市場で即時売買可能 | 売却は証券会社を通じて換金 |
| 手数料 | 信託報酬あり | 売買手数料・信託報酬 | 購入手数料・信託報酬 |
ETFは市場で株式のように売買できるため、タイミングを見て短期的に売買したい人向きです。
一方、純金積立は長期でコツコツ資産を積み上げたい人に適しています。
金投資信託は少額から投資でき、管理の手間がほとんどない点で初心者に取り組みやすい特徴があります。
金投資信託の主な種類と特徴

金投資信託には、投資対象や運用方法によってさまざまな種類があります。
ここでは金投資信託の主な種類と特徴について紹介します。
現物連動型(金現物を保有するタイプ)
現物連動型は、運用会社が実際の金を保有し、その価格に基準価額を連動させるタイプです。
金価格の動きに忠実に反応するため、現物を持つ感覚で投資できます。
メリットは価格の透明性が高く、長期保有に向いており、安心感があります。
ただし、管理費用として信託報酬がかかり、売買に時間がかかる点はデメリットです。
先物連動型(金先物価格に連動するタイプ)
先物連動型は、金先物契約を通じて運用するタイプで、現物を持たずに金価格に投資できます。
少額で効率的に投資できる点が魅力です。
ただし、先物の価格変動やロールオーバー(契約更新)の影響で、基準価額が現物価格と完全に一致しない場合があります。
短期売買や市場の値動きを生かした投資に向いています。
通貨ヘッジあり・なしの違い
金は世界市場で主に米ドル建てで取引されるため、日本円で投資する場合、金価格の変動に加えて為替の影響を受けます。
「通貨ヘッジ」とは、為替リスクを回避するための仕組みのことです。
同じ金価格の上昇でも、円高の場合は円換算でのリターンが小さくなり、円安の場合は利益が大きくなることがあります。
運用会社が為替リスクを避けるために先物や為替予約などを用いて円建てでの価値変動を抑えます。
その結果、基準価額は金価格の動きにほぼ忠実に連動します。
安定して金価格の変動だけに投資したい人や、為替リスクを避けたい長期投資家に向いていますが、ヘッジコストが運用コストに上乗せされるため、手数料負担がやや高くなる点には注意しましょう。
為替リスクを回避せず、そのまま米ドル建て金価格に連動させます。
円高・円安の影響を受けるため、金価格が横ばいでも円安ならリターンが上乗せされ、円高なら損失が拡大することがあるので注意しましょう。
為替差益を狙いたい人や、長期で円安を見込む投資家に向いています。
ただし、変動幅が大きくなるためリスクも増す点に注意が必要です。
アクティブ型・インデックス型の違い
金投資信託は運用手法によってアクティブ型とインデックス型に分かれます。
それぞれの特徴を理解すると、自分の投資目的に合った選択がしやすくなります。
運用会社のプロが市場動向や需給バランスを分析し、金現物や先物の売買タイミングを調整する運用方法です。
市場平均以上のリターンを目指す運用で、短期的な値動きを活かす戦略が可能です。
ただし手数料(信託報酬)が高めで、運用成績は運用会社の判断に大きく依存します。
金現物や金先物価格指数に連動する運用方法です。
市場平均に沿った運用で、運用コストが低く長期保有に向いています。
値動きは市場平均に忠実で、安定的に金価格の値動きを反映します。
短期的に大きな利益は狙いにくいですが、低コストで安心して運用できる点がメリットです。
金投資信託のメリット

金投資信託には、現物投資や純金積立と比べて投資家にとって魅力的なメリットが4点あります。
・保管コストや手間が不要
・分散投資しやすい
・価格透明性が高い
1つずつ確認していきましょう。
少額から投資できる
少額から投資できるため、まとまった資金がなくても金投資を始められるメリットがあります。
金投資信託は1万円程度から購入可能で、証券会社によっては月1,000円単位の積み立ても可能です。
現物の金を購入する場合は数十万円〜数百万円が必要なため、資金が限られる初心者や若年層でも無理なく資産形成に参加できます。
ただし、少額投資の場合は手数料や信託報酬がリターンに影響する点には注意が必要です。
保管コストや手間が不要
金投資信託には手数料はかかるものの、現物投資ならではの保管コストや手間がかからないため、手軽かつ低コストで金投資を行えるメリットがあります。
現物の金は自宅金庫や銀行貸金庫で保管する必要があり、盗難や劣化リスク、保管料が発生します。
一方、金投資信託は運用会社が現物や先物を管理するため、投資家は手間や費用をかけずに運用できます。
分散投資しやすい
金投資信託は分散投資が容易なため、資産全体のリスクを抑えつつリターンを安定させられるメリットがあります。
金投資信託は株式や債券と同じ証券口座で管理できるため、ポートフォリオに簡単に組み込めます。
金は景気や株価と連動しにくく、有事の資産としてリスク分散に役立ちます。
ただし、金価格自体も変動するため、分散投資の一部として位置づけることが重要です。
価格透明性が高い
金投資信託は価格が透明で、取引のタイミングや価値を判断しやすいことがメリットです。
基準価額は毎日公表され、金価格や先物価格に連動して算出されます。
現物購入のように店舗ごとの価格差やスプレッドの影響を受けにくく、公平な価格で取引が可能です。
投資判断もしやすく、初心者でも安心して運用できます。
ただし、信託報酬や売買手数料によって実際のリターンは基準価額よりやや低くなる点に注意が必要です。
金投資信託のデメリット

一方、金投資信託にはデメリットも4点あるので確認していきましょう。
・為替変動リスクがある(外貨建ての場合)
・現物引き出しができない
・価格変動による元本割れリスク
1つずつ紹介します。
信託報酬などの手数料がかかる
金投資信託には手数料がかかるため、長期保有時にはリターンが減少するリスクがあります。
金投資信託は運用管理費用として信託報酬が毎年発生し、売買時には購入・換金手数料がかかることもあります。
例えば、信託報酬が年0.5%の場合、長期間運用すると複利でコストが積み重なり、実際のリターンは基準価額より下回ることがあります。
したがって、金投資信託を始める際は、できるだけコストの低い商品を選ぶようにしましょう。
為替変動リスクがある(外貨建ての場合)
為替変動の影響を受けるため、金価格が上昇しても円換算で損失になる可能性があります。
海外市場の金は米ドル建てで取引されるため、円高になると円換算の価値が下がります。
逆に円安なら利益が増えます。
通貨ヘッジありの商品を選ぶことでリスクを抑えられますが、ヘッジコストが上乗せされるため、その分リターンが減る可能性があります。
現物引き出しができない
現物として金を手に入れられないため、物理的な所有感や資産防衛の手段としての価値は得られません。
金投資信託はあくまで金融商品であり、売却して換金する形でしか現金化できません。
現物保有が目的の人や、緊急時に手元に金を置きたい人には向かない投資手段です。
価格変動による元本割れリスク
基準価額が金価格や先物価格に連動するため、投資元本が減るリスクがあります。
金は株式ほど変動幅は大きくありませんが、市場の需給や金利、世界情勢などによって価格は上下します。
特に短期売買では元本割れの可能性があり、長期保有でも価格下落時に損失が発生することがあります。
投資目的や期間を明確にしておくことが、リスクを抑える鍵となります。
金投資信託の比較ポイント

金投資信託は商品ごとに運用方針や手数料、連動対象が異なるため、購入前に比較することが重要です。
特に注目すべき5つのポイントを紹介します。
・信託報酬・手数料の低さ
・連動対象(現物・先物)
・為替ヘッジの有無
・購入可能な証券会社
1つずつ確認していきましょう。
運用実績と純資産総額
金投資信託を選ぶ際は、証券会社で取り扱っているファンドの運用実績と純資産総額を確認することが重要です。
長期的に安定した運用実績がある商品は、投資方針が明確で市場の変動に対応できる可能性が高く、安心して投資できます。
また、純資産総額が大きい商品は売買が活発で、換金時に価格が大きく変動しにくく、流動性も高いです。
逆に、規模が小さい商品は途中で運用が終了するリスクもあるため注意が必要です。
信託報酬・手数料の低さ
信託報酬や購入・換金手数料の低さは、長期運用でのリターンに直結します。
金投資信託は年0.3〜1%程度の信託報酬がかかり、購入時・換金時にも手数料が発生する場合があります。
たとえ運用実績が良くても、手数料が高いと複利効果で長期的な利益が大きく減少する可能性があります。
そのため、低コストの商品を選ぶことが重要です。
連動対象(現物・先物)
金投資信託は、現物・先物のどちらを選ぶかで値動きの特徴が変わるため、投資期間や目的に合わせて選ぶことが重要です。
現物連動型は金価格に忠実に連動し、10年以上などの長期保有に向いています。
一方、先物連動型は短期的な値動きに敏感で、効率的に投資できますが、先物のロールオーバーや基準価額のずれにより、現物価格と完全に一致しない場合があります。
投資期間や目的に応じて、現物型か先物型かを選ぶようにしましょう。
為替ヘッジの有無
為替ヘッジがあるかないかで、円換算のリターンやリスクが大きく変わります。
通貨ヘッジありの商品は、円建ての基準価額がドル為替の影響を受けず、金価格の動きだけに集中して投資できます。
逆にヘッジなしの場合、円高では利益が減少し、円安では利益が増える可能性があります。
為替リスクを許容できるかどうかで商品を選ぶと良いでしょう。
購入可能な証券会社
金投資信託は証券会社によって取り扱い商品が異なります。
自分の口座で購入できるか、オンラインでの取引の利便性、手数料体系、積み立て設定のしやすさなどもチェックポイントです。
購入先によってコストや操作性が変わるため、取引条件を事前に比較して選ぶことが重要です。
代表的な金投資信託の比較一覧

ここでは代表的な金投資信託を紹介します。
| 商品名 | 連動対象 | 信託報酬・手数料 | 為替ヘッジ |
|---|---|---|---|
| 日興-Tracers S&P500ゴールドプラス | 金現物+株価指数(S&P500) | 信託報酬やや高め | なし |
| SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 金現物 | 比較的低め | なし |
| 三菱UFJ-三菱UFJ 純金ファンド | 金現物 | 平均的 | 商品による |
1つずつ見ていきましょう。
日興-TracersS&P500ゴールドプラス
金だけでなく株式との分散効果も期待できるため、中期的にリターンを重視する投資家に向いています。
長期保有よりも、相場状況に応じた中期運用に適した商品です。
SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
手数料が比較的低くコスト効率が高いのが特徴です。
為替ヘッジがないため、円高・円安による価格変動も受け入れられる投資家に適しており、中〜長期の積立投資にも向いています。
三菱UFJ-三菱UFJ 純金ファンド
長期積立や資産保全目的での投資に向いており、通貨ヘッジありの商品を選べば、為替リスクを抑えて運用できます。
初心者でも安心して購入できる商品として人気があります。
まとめ

金投資信託は、少額から手軽に始められる一方で、信託報酬や為替リスク、元本割れの可能性など、注意すべきポイントも少なくありません。
投資目的や運用期間、リスク許容度によって最適な商品は変わるため、どのファンドを選ぶかは慎重な判断が必要です。
そのため、金投資信託をはじめとする金投資を検討する際は、ファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
FPは、資産全体のバランスやライフプラン、他の投資との兼ね合いを踏まえて、あなたに合った投資方法や積み立て額、リスク管理の方法を提案してくれます。
ココザスはファイナンシャルプランナーとして投資や資産運用のサポートを行っております。
また、お客様の資産状況や家族構成、将来的なライフプランから適切な投資計画のアドバイスもしています。