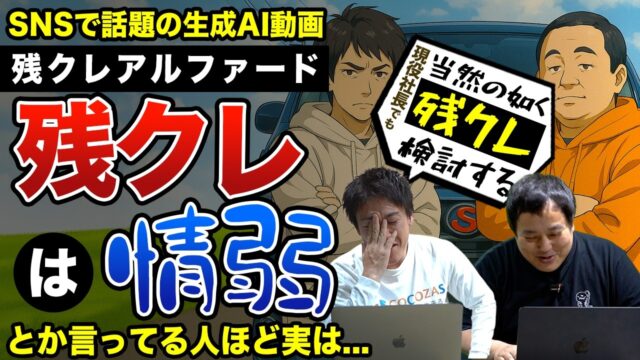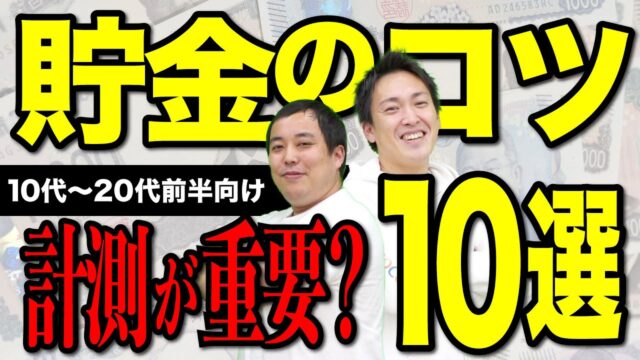子供にかかるお金(教育費)の総額はどれくらい?

代表的な2つの進学パターンに分けて、教育費の総額を比較してみましょう。
公立ルート|約800万円
日本政策金融公庫のホームページによれば、幼稚園から大学まで、すべて公立に通った場合の教育費の総額は約822万円と紹介されています。
この金額には授業料や入学金、教材費などの教育関連費用が含まれています。
一方で、生活費や塾代などの支出は含まれていないため、実際の負担は家庭によって増減する可能性がある点には注意が必要です。
私立ルート|約2,300万円
同様に、すべて私立の学校に進学した場合の総費用は、約2,300万円程度と見込まれます。
授業料や施設費が高額なうえ、寄付金や制服代など、公立ではかからない費用も追加されるため、全体の負担が大きくなりやすい傾向です。
また、進学先が都市部の私立校であれば、交通費や交際費などの生活コストも上乗せされる可能性があります。
高水準の教育環境を望む家庭にとっては魅力が多いものの、早い段階から長期的な備えが求められます。
【年齢別】子供にかかるお金の内訳

子供の成長に合わせて、支出の内容や金額は変化します。
保育料から大学の学費まで、家計への影響が大きくなる時期を把握しておくことが大切です。
こちらでは、年齢ごとに発生する主な支出の種類や特徴を紹介します。
乳幼児期(0〜6歳)
乳幼児期には、オムツやミルクといった日用品のほか、ベビーカーやチャイルドシートなどの初期費用がかかります。
保育園に通わせる場合は保育料が大きな支出となり、世帯年収によっては月数万円の負担になることもあるでしょう。
一時保育や幼児教室、習い事など任意の支出も増えてくるため、必要に応じた優先順位づけが求められます。
小中学校期(7〜15歳)
義務教育であっても、学校生活にかかる費用は少なくありません。
たとえば、学用品や給食費、PTA会費、修学旅行の積立金などが毎月発生します。
また、学年が上がるにつれて、塾に通わせたり通信教育を利用したりする家庭も増え、教育関連の支出がじわじわと膨らんでいきます。
小中学校は公立校を選ぶ家庭が多く、費用負担は比較的抑えやすい傾向です。
一方で私立校を選ぶ場合は、授業料や教材費などの水準が大きく異なります。
高校期(16〜18歳)
高校進学と同時に、教育費の負担が一段と大きくなります。
授業料のほか、制服代や教材費、修学旅行費、部活動の費用などがまとまって発生します。
私立高校に通う場合は、公立よりも年間で50万円以上の上乗せが発生するケースもあるでしょう。
さらに、通学定期代や交際費の増加など、子供の行動範囲が広がることで新たな費用も出てきます。
兄弟が同時期に高校や大学に通っている場合は、世帯全体で年間100万円以上の教育費が必要になることもあります。
大学期(19〜22歳)
大学では、入学金や授業料、施設費といった固定費のほか、一人暮らしをする場合の生活費も加わります。
とくに都市部に進学する場合、家賃や生活費の負担が大きくなり、家庭からの経済的支援が求められる場面も少なくありません。
奨学金を利用する家庭も多いですが、返済義務のあるタイプが主流のため、将来を見据えた利用が重要です。
兄弟が複数同時期に進学している場合、年間で200万円を超える教育費となることもあるでしょう。
意外と見落としがちな子供にかかるお金

学費や教材費以外にも、子育てには思わぬ出費が発生する場合があります。
代表的な支出項目をいくつか紹介します。
医療費・通院費・眼鏡・歯列矯正
子供は年齢によって免疫が未発達な時期があり、通院や予防接種などの医療費がかかる機会が多くなりがちです。
たとえば次のような費用が発生する可能性があります。
・眼鏡の買い替え:1〜3万円程度
・歯列矯正:50万〜150万円前後
自治体の助成制度ではカバーできない支出もあり、急にまとまったお金が必要になることもあるため注意が必要です。
お祝い・行事・写真代などの儀礼的支出
入学式や卒業式、七五三、発表会など、節目となる行事では思った以上に出費が重なります。
たとえば次のような費用が発生するケースがあります。(金額は目安です)
・記念写真の撮影:1〜6万円前後(スタジオ/出張で幅あり)
・お祝い返しや内祝い:5,000〜1万円程度(ご祝儀の半額程度が目安)
・ピアノ・バレエ発表会の衣装代:5,000〜2万円程度
まとまった支出が短期間に集中するため、タイミングによっては家計に影響が出やすくなります。
クラブ活動・部活動・遠征費
部活やクラブ活動では、ユニフォームや道具の購入、合宿・大会への遠征費などが継続的に発生します。
これらは月謝とは別のタイミングでまとまった額が必要になるため、意識しておかないと家計に負担がかかりかねません。
活動が複数にわたる場合や、兄弟姉妹の時期が重なると、年間で数十万円にのぼるケースもあります。
子供にかかるお金の備え方|始める前に知っておきたい視点

子供にかかるお金の概要は把握したものの、「具体的に何をすればいいのか分からない」と感じる方もいるでしょう。
こちらでは、家計への負担を抑えながら、子育てにかかる費用を準備するための基本的な考え方を紹介します。
少額でも今から始めるのがおすすめ
「余裕がないから貯金できない」と感じる方も、月1万円から積み立てを始めましょう。
もし18年間続ければ、元本で200万円以上の資金を確保できます。
この金額だけで大学費用をまかなえるとは限りません。
しかし、少なくとも初期費用や入学金には対応しやすくなるはずです。
小さな積立でも継続することで、お金を「使わずに残す」習慣がつき、計画的に貯める感覚が自然と身につきます。
将来的により大きな金額を積み立てる場面でも、精神的なハードルが下がりやすくなるでしょう。
途中で見直すことも可能なので、まずは無理のない金額で積み立てを始めてみることをおすすめします。
児童手当や保険など活用しやすい制度を押さえる
子育て費用を備えるうえで、制度の仕組みや特徴をあらかじめ把握しておくと安心です。
たとえば、児童手当を生活費に使わず積み立てておけば、将来の教育費に充てやすくなります。
学資保険は受取時期があらかじめ設定されており、大学入学などのタイミングでまとまった資金が確保できます。
また、所得に応じて授業料が軽減される「高等学校等就学支援金制度」などの併用も可能です。
家庭の方針や家計状況に合わせて適した制度を選べば、必要な時期に無理なく対応しやすくなります。
なお、児童手当や就学支援金制度などの詳しい内容は、このあと具体的に解説します。
複数の手段を組み合わせるのが堅実
特定の方法に絞らず、いくつかの手段を併用することで、予期しない支出にも対応しやすくなります。
たとえば、児童手当を学資保険に回しつつ、NISAや預金で追加の積立を行うと、途中での見直しや調整がしやすくなります。
学資保険は中途解約で元本割れするおそれがあり、NISAなどの運用商品は価格が常に変動しています。
そのため、複数の手段を組み合わせておけば、一方のリスクを補い合えるというメリットがあるのです。
家計の状況が変わったときも柔軟に対応できるため、長期間にわたる準備を続けやすくなります。
それぞれの手段の特徴を踏まえながら、家計や教育方針に応じた組み合わせを考えることが大切です。
ここまで紹介したのは、備えを始めるための基本的な考え方です。
次の見出しでは、手段ごとの具体的な特徴と使い分け方を紹介します。
子供にかかるお金の準備方法|保険・投資・貯金の使い分け

子供の教育資金を準備する方法には、保険・投資・貯金など複数の選択肢があります。
ここでは、それぞれの特徴を具体的に比較し、どのように使い分けると効果的かを解説します。
学資保険|計画的に積み立てたい家庭向け
契約者にもしものことがあっても保険料の支払いが免除され、満期金が確保される仕組みは、多くの家庭にとって安心材料になります。
ただし、途中で解約すると元本割れする可能性があり、急な資金の引き出しには不向きです。
満期時の使い道が明確な場合に適しており、学費の支払い時期が決まっているご家庭では、預金よりも効率的な選択肢になるでしょう。
返戻率や保障内容は商品によって異なるため、加入前に必ず比較・検討しておくことが大切です。
預貯金|柔軟性を重視したい場合に有効
元本が保証されており、安全性が高く、急な出費にも対応しやすいのが強みです。
ただし、金利が極めて低いため、長期で保有しても資産の増加はあまり見込めません。
教育資金の一部を現金で確保しておけば、学資保険や投資とのバランスを取る役割を果たせます。
たとえば、児童手当を別口座に自動で積み立てるだけで手間がかからず、自然と貯蓄を続けやすくなります。
NISA・つみたて投資|長期的な資産形成に
運用益が非課税になるNISAを活用すれば、長期の積み立てによって効率的な資金形成が期待できます。
ただし、元本保証はなく、市場環境によっては評価額が下がることもある点には注意が必要です。
投資のリスクを理解したうえで取り組むことが前提となります。
中学・高校までは現金や保険で備え、大学入学のように時期が明確な支出に向けて投資を充てるのが現実的です。
子育て家庭が活用できる公的支援・助成金

子供の教育費をすべて自力でまかなうのは難しいケースもあります。
国や自治体の制度を知り、使えるものは積極的に活用することがおすすめです。
こちらでは、代表的な4つの支援制度について紹介します。
児童手当
年齢や第何子かによって支給額が変わり、たとえば3歳以上〜高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は30,000円が支給されます。
支給は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に年6回、原則2か月分まとめて振り込まれます。
受給には申請が必要で、出生や転入時などのタイミングを逃すと受け取れないため注意が必要です。
幼児教育・保育の無償化
また、0〜2歳児についても、住民税非課税世帯であれば無償化の対象となります。
ただし、給食費や行事費は自己負担となるほか、認可外施設では上限付きの補助となるなど、利用形態によって内容が異なります。
対象施設や申請方法など、詳細は自治体によって異なるため、該当年齢になったら早めに確認することが望ましいです。
高等学校等就学支援金
公立・私立を問わず対象となり、保護者の年収目安が約590万円未満であれば支援対象になります。
私立高校でも支援額の上限内であれば、授業料が実質無償化される場合があります。
申請は原則として学校を通じて行い、支援金は学校に直接支払われます。
入学手続きや納付時期に影響するため、早めに内容を確認して必要書類を準備することが大切です。
高等教育修学支援制度
住民税非課税世帯またはそれに準ずる収入の家庭が対象で、文部科学省が指定する支援対象校への進学が条件です。
授業料の減免と、返済不要の給付型奨学金を併用できるのが特徴です。
高校3年生のうちに進学先を検討しながら、マイナンバーなどの必要書類を準備して申請手続きを進める必要があります。
利用を希望する場合は、高校在学中から制度の内容を確認しておくと安心です。
まとめ|子供にかかるお金は段階的に備えれば大丈夫

子供1人の教育費は、公立で約800万円、すべて私立なら2,000万円以上かかる場合があります。
すべてを一度に準備するのは現実的ではありません。
ただし、進学時期や必要額を見据えて、児童手当や保険、つみたて投資などを使い分ければ十分に対応可能です。
教育資金は段階的に発生するため、まずは「最初に備えるべきタイミング」と「使える制度や手段」を押さえることから始めてみましょう。