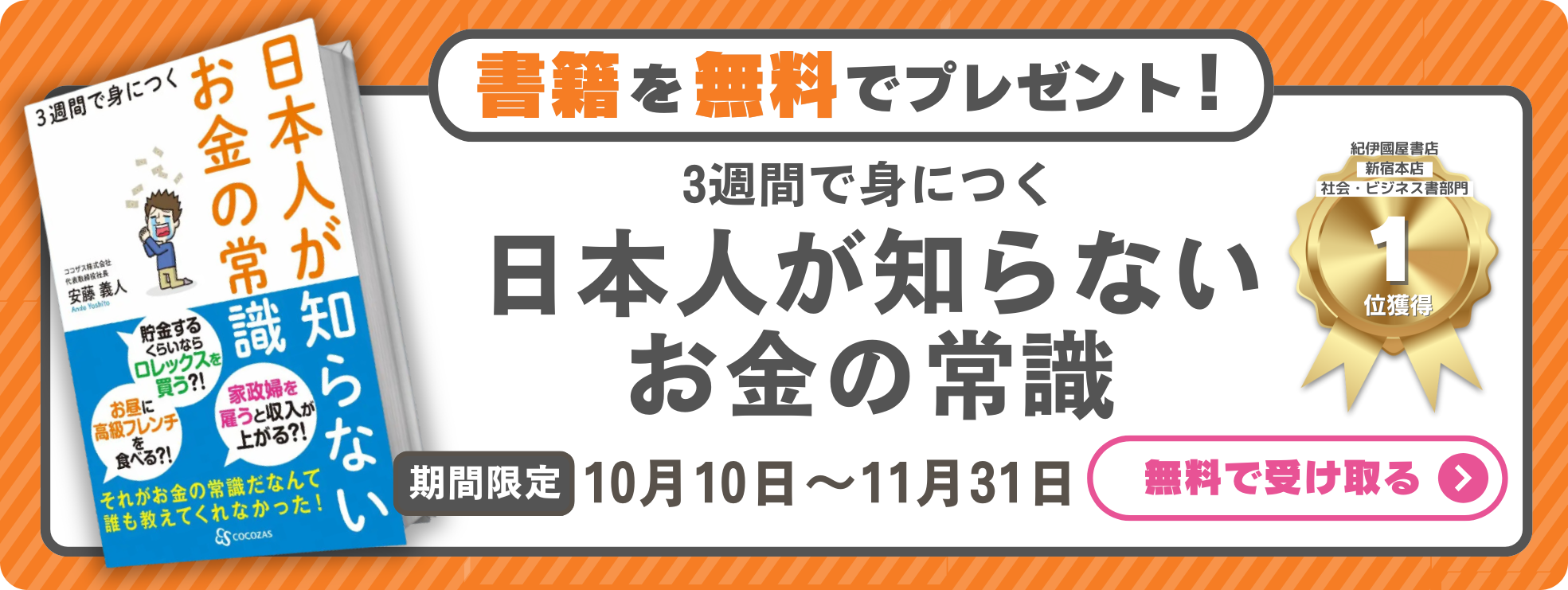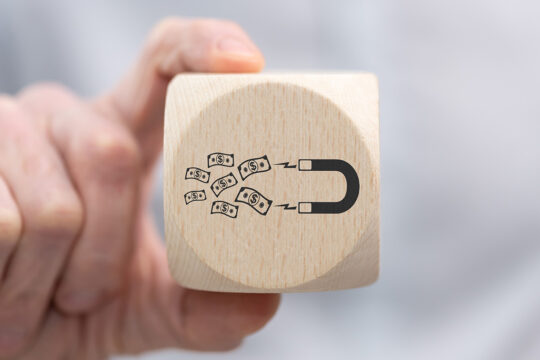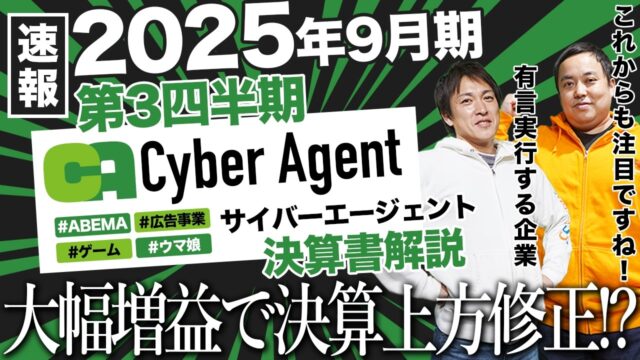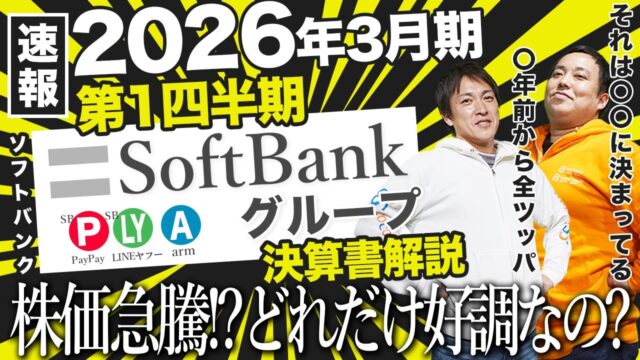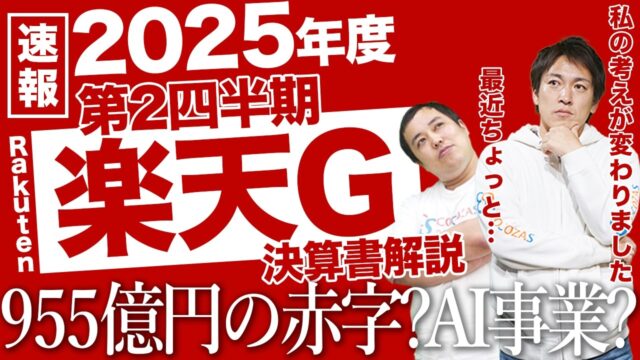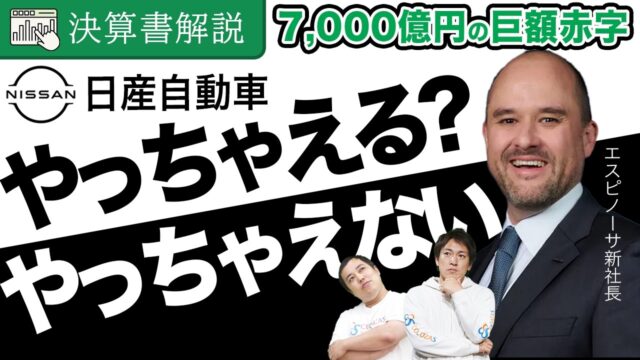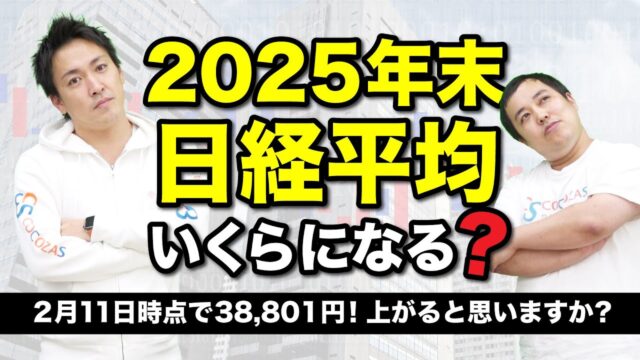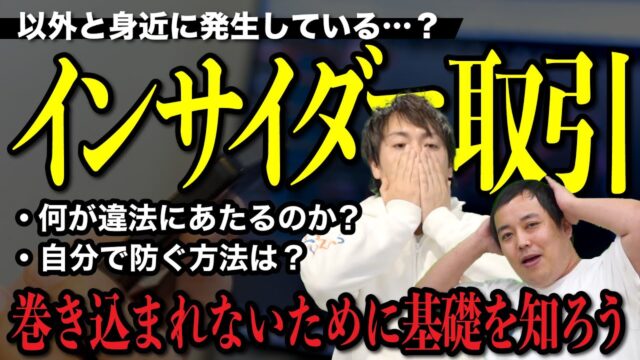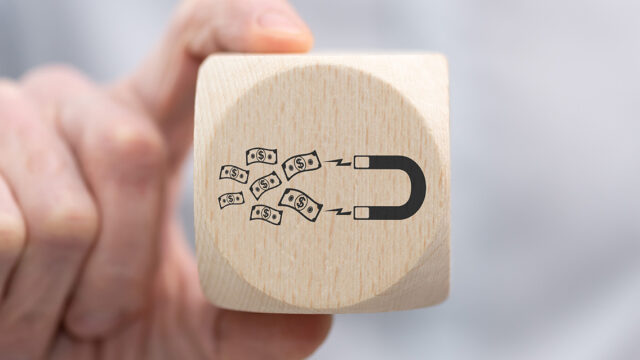資産運用は人生100年時代に必須の個人スキル

定年後の長い期間の生活費を年金だけで賄うのは難しくなってきました。
そのため、株式投資をはじめとする資産運用は、長寿社会を生き抜くために必要不可欠なスキルなのです。
(1)老後2,000万円問題問題に関係ない人はいない
テレビでも話題になった「老後2,000万円問題」。
実は、富裕層以外の大多数の人にとって、これは深刻な問題なのです。
平均寿命の伸長により、年金だけでは足りなくなると言われています。
自分の寿命を決められないからこそ、老後資金の準備が重要なのです。
▼ 合わせて読みたい
老後2000万円問題の対策とは?効率…
(2)日本円を銀行に預金しているだけでどんどん貧しくなる日本人
日本のタンス預金は1,000兆円あると言われています。
インフレが進行する中で、預金の価値は目減りしていきます。
日本人は預金を好む傾向にありますが、それだけでは資産価値が目減りしてしまうのが現実です。
日本銀行もインフレ目標を掲げています。
物価は上昇しても、賃金は上がりにくいのが現状です。
では、インフレ社会で私たちにできることは何でしょうか。
(3)「株式投資」+「年金」の2本柱で老後生活を守る
お金を増やす手段は「労働時間を切り売りして、お金に換える(働く)」と「お金に働いてもらう(株式投資などの資産運用)」の大きく2つです。
これからの時代、年金だけを頼りにするのではなく、資産運用しながら年金をもらうことも考えなければならないと言われています。
資産を守り増やすには、株式投資などの資産運用が効果的です。
株式投資とは?基本原則と注意点をまずはチェック

株式投資は、企業が発行する株式を買い「価格が上がったときに売る」または「配当金を得る」という2つの方法で利益を目指す投資です。
簡単に言うと、「会社のオーナーの一部になる」感覚で、企業の成長を一緒に楽しむものと考えるとわかりやすいでしょう。
資産を長期的に増やせる可能性がある一方、リスクもあるため、基本的な知識を持って始めることが大切です。
株式投資の3原則
株式投資に取り組むうえで、「長期」「分散」「積立」の3つの基本ルールを守ることが重要です。
それぞれのポイントを具体的に解説します。
1.長期
株式投資は短期間での利益を狙うより、じっくりと長い目で取り組むほうが安全です。
なぜなら、株価は一時的に下がることがあっても、長い期間で見ると経済成長とともに回復することが多いからです。
たとえば、10年以上保有すると、損をする確率がぐっと減るというデータもあります。
「焦らずじっくり」が長期投資の鍵です。
2.分散
分散投資は、リスクを減らすための基本テクニックです。
1つの企業だけにお金を集中させると、その会社がうまくいかなかったときに大きな損をするリスクがあります。
しかし、複数の会社や業界にお金を分けて投資すると、全体のバランスが取れます。
初心者には、多様な株に投資できる「投資信託」や「ETF」という商品がおすすめです。
▼ 合わせて読みたい
3.積立
積立投資は、毎月コツコツと一定額を投資する方法です。
このやり方なら、一度にたくさんのお金を準備しなくても始められます。
積立投資を続ければ、価格が高いときは少ししか買わず、価格が低いときはたくさん買う仕組みになり、自然と平均的な買い値が下がるのがポイントです。
「無理なく、コツコツ」を続ければ、いつの間にか大きな資産が育つ可能性があります。
初心者が知っておくべき3つのリスクと対策
株式投資は利益を得られる一方で、リスクも避けては通れません。
特に初心者が最初に直面しやすいのが、次の3つのリスクです。
あらかじめ理解しておくことで、不安を減らし、より安心して投資を始められます。
1. 元本割れリスク ─ 投資額が減ってしまう可能性
株式は値動きがあるため、買ったときより株価が下がると、投資した金額よりも少ない額しか戻ってこない可能性があります。
たとえば10万円で買った株が8万円に下がると、2万円の損失になります。
これを避けるには、少額から分散して投資を始めることや、短期的な値動きに一喜一憂せず長期的な視点を持つことが有効です。
株価よりも「その企業が今後も成長できそうか」という視点を大事にすると、冷静な判断がしやすくなります。
2. 企業倒産リスク ─ 株が無価値になる可能性
もし投資した企業が経営不振に陥り、最悪の場合は倒産してしまったとき、その株式はほぼ無価値になります。
特に、まだ業績が不安定なベンチャー企業などには注意が必要です。
このリスクを抑えるには、業績が安定している大手企業の株から始めたり、業種や銘柄を複数に分けて投資するなどの方法が考えられます。
1社に集中するより、リスクが分散されます。
3. 感情による売買リスク ─ 焦りや欲が判断を狂わせる
株価が下がると「損したくない」と焦って売ってしまい、逆に上がると「もっと上がるかも」と欲を出して無理に買い足す…これは多くの初心者が経験する落とし穴です。
感情に流されずに投資を続けるには、あらかじめ「いくらまで下がったら売る」「いくら利益が出たら確定する」といったルールを決めておくのが効果的。
また、感情に左右されにくい自動積立などを活用するのも1つの方法です。
まとめ
リスクをゼロにすることはできませんが、「知っておく」「備えておく」ことで、冷静に判断できるようになります。
怖がるよりも、正しく向き合うことが大切です。
▼ 合わせて読みたい
株式投資のポートフォリオの作り方!自…
株式投資を始める5ステップ【初心者向けにわかりやすく解説】
「投資を始めたいけど、何からやればいいの?」
そんな疑問を持つ方のために、この章では株式投資を始めるための基本ステップを5つに分けて丁寧に解説します。
初心者でも迷わず一歩を踏み出せるよう、順を追って解説していきますので、自分のペースで読み進めてみてください。
特別な知識や資金は必要ありません。
まずは「始める準備」ができることが大切です。
1.証券会社を選ぶ(SBI証券、楽天証券など)
株式投資の第一歩は、信頼できる証券会社を選ぶことです。
株式を買ったり売ったりするには、証券会社を通じて「証券口座」を開設する必要があります。
近年はスマートフォンで簡単に取引できるネット証券が主流で、特に「SBI証券」や「楽天証券」は初心者から経験者まで幅広い層に支持されています。
→ 業界最大級の情報量と商品数。長期運用に強い。
・楽天証券:
→ 楽天ポイントを活用可能。アプリが使いやすく初心者向け。
比較検討のポイントは、取引手数料・スマホアプリの使いやすさ・情報提供の質などです。
長く付き合うパートナーだからこそ、自分にとって「使いやすい」と感じるかどうかが最も大切です。
2.証券口座を開設する
証券会社が決まったら、次は口座開設です。
口座開設はオンラインで完結でき、特に難しい手続きではありません。
必要なものは本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)と、マイナンバー、そして入出金用の銀行口座情報です。
申し込みは10〜15分ほどで完了し、早ければ数日以内に口座が開設されます。
しかも、開設や維持に費用はかかりません。
「とりあえず口座だけ作っておく」という選択もありです。
口座ができて初めて、株を買う準備が整います。
3.NISAや特定口座の選び方
税金の仕組みを知っておくだけで、将来の利益に大きな差が出ます。
投資の利益には通常20.315%の税金がかかりますが、「NISA」や「特定口座(源泉徴収あり)」を活用することで、手間や税負担を減らすことができます。
→ 年間一定額までの投資利益が非課税。長期運用向け。
・特定口座(源泉徴収あり):
→ 税金計算や納付を証券会社が代行してくれる。手間なし。
初心者は、最初にNISAを選びつつ、必要に応じて特定口座も併用する形が一般的です。
自分の投資スタイルに合った口座を選ぶことで、無駄なコストを避けられます。
4.初めての銘柄選びのコツ(有名企業・分散投資)
株式投資を始めたばかりの人にとって、「何を買えばいいのか分からない」ということは、誰もが感じる悩みです。
ですが、初心者向けの銘柄選びには、いくつかの明確なコツがあります。
まずは、あなたがすでによく知っている企業から選ぶのが安心です。
たとえばテレビCMで見かけたり、ニュースで名前を聞くような会社は、業績が安定しているケースが多く、情報も手に入りやすいというメリットがあります。
次に注目したいのが、毎年配当金を出している企業です。
配当とは、企業の利益の一部を株主に還元するもので、長く保有することで安定した収益が見込める点が魅力です。
「持っているだけでお金が入ってくる」という安心感は、初心者にとって大きな支えになるでしょう。
そしてもう1つ大切なのが、投資する業種を分けることです。
たとえば「通信・食品・自動車」など異なる分野にまたがって株を持つことで、1つの業界が不調でも他でカバーできるため、全体のリスクが抑えられます。
投資の基本は、「1つに偏らない」こと。
まずは身近な企業をいくつか選び、少額ずつ複数の銘柄に投資していくスタイルが、初心者にとってもっとも堅実で王道なアプローチです。
▼ 合わせて読みたい
5.少額で実際に買ってみる
最終ステップは、実際に株を買ってみること。
ここからが本当のスタートです。
最近は「1株単位」や「100円単位」から購入できるサービスが増えており、まとまった資金がなくても始められます。
特にSBI証券やLINE証券などは少額投資に対応しています。
「とにかく一度やってみる」ことで、座学だけでは得られない気づきがあります。
少額投資を通して、投資に対する心理的なハードルを下げていきましょう。
▼ 合わせて読みたい
よくある初心者の失敗とその回避法
株式投資は、一見シンプルなようで奥が深い世界です。
始めたばかりのときは、誰もが期待と不安を抱えながら一歩を踏み出しますが、その中で「やってはいけない失敗」に気づかないまま進んでしまう人も少なくありません。
この章では、投資初心者がよく陥る3つの典型的なミスと、その背景にある心理、そして避けるための考え方を紹介します。
事前に知っておけば、防げることばかりです。
長く、安心して投資を続けるためのヒントとしてお役立てください。
1.一気に大金を投資してしまう
投資を始めた直後は、「どうせやるなら、ある程度まとまった額で勝負したい」と思ってしまうことがあります。
初めて証券口座を開設し、銘柄を調べ、ついに購入画面までたどり着くと、なぜか気持ちが大きくなりがちです。
数十万円、あるいはそれ以上を最初から投入してしまう人もいます。
しかし、投資経験がないうちに大金を動かすと、相場のちょっとした値動きにも不安や焦りを感じやすくなります。
わずかな下落で「このまま損するかも」とパニックになり、慌てて売ってしまう。
冷静さを欠いた判断は、損失につながる典型例です。
投資は、金額が大きいほど成功するものではありません。
むしろ少額から始めて、相場との付き合い方や自分のリスク許容度を体感することが、結果的に安定した運用につながります。
焦らず、地に足のついたスタートを切ることが大切です。
2.SNSや噂で売買を決めてしまう
現代の投資環境では、SNSやネット記事、YouTubeなどから手軽に情報を得ることができます。
それ自体は悪いことではありませんが、問題なのは「誰かが良いと言っていたから」「フォロワーが多い人が推していたから」という理由だけで、株の売買を決めてしまうことです。
情報の発信者がどんな立場で、どんな目的でその銘柄を勧めているのかまでを把握するのは簡単ではありません。
中には、自身が保有している株を高値で売るために、わざと話題にしているケースすらあります。
もちろん、他人の意見を参考にするのは悪いことではありません。
ただし、最終的な判断基準は、自分自身の納得感であるべきです。
企業の決算資料や中長期的な業績、業界の動向など、裏付けとなる情報に目を通した上で、自分の軸をもって判断する姿勢が、長く投資を続ける上で不可欠になります。
3.長期視点を持てずに売ってしまう
株式市場は、日々価格が上下します。
ニュースや株価チャートを眺めていると、つい目先の動きにばかり目が行きがちです。
特に、買った直後に値下がりすると、「やっぱり失敗だったかも…」と不安になり、すぐに売却してしまう人が多くいます。
けれども、短期的な値動きは、ほとんどが一時的なノイズです。
企業の本質的な価値や成長性は、数カ月、あるいは数年というスパンでじっくりと現れてくるものです。
目先の数字だけで判断するのではなく、「なぜこの株を買ったのか」という原点に立ち返ることが重要です。
長期的な視野を持つことで、多少の下落があっても落ち着いて対応できるようになります。
むしろ、安くなったタイミングを「買い増しのチャンス」と考えられるようになると、投資家として一段階ステップアップしたと言えるでしょう。
初心者が初めて株式投資をするとき、まずはどこに相談すべき?

株式投資を始めると言っても、何から始めればいいか分かりませんよね。
お金の問題は周りにも相談できません。
聞けば「株式投資で大損した」という話もよく耳にします。
ここでは、株式投資を始める前に覚えておきたいポイントを紹介します。
株式投資の相談前は「目的」をはっきりさせよう
株式投資の相談前は、資産運用の目的をはっきりさせる必要があります。
・どれくらいの金額を最終目標とするのか
・いくらくらいの余剰資金を投資に回せるのか
まずは自分の中で資産運用の目的をはっきりさせたうえで相談をしてみましょう。
それでは相談相手を決めるポイントについて見ていきます。
【ポイント①】中立的な第三者の立場であること
相談相手は中立的な第三者の立場であることが望ましいです。
銀行や証券会社の窓口では、どうしても相談者の立場に立って話を聞いてもらえません。
中立的な第三者の代表例として、プロのファイナンシャルプランナー(FP)が挙げられます。
【ポイント②】個人のライフプランに合った提案をしてもらえるか?
相談者の立場によってお金の悩み事は千差万別です。
既婚か未婚か、子供がいるかいないかで資産運用の目的も違います。性別や職種、保有している金融資産の規模によっても違うでしょう。
したがって、相談する相手はしっかりとあなたのライフプランに向き合ってもらえるかどうか、という点をポイントにしたほうがいいでしょう。
【ポイント③】透明性が高い金融商品を扱っているか?
銀行や証券会社の営業の立場だと、どうしても提案が自社の金融商品に偏りがちです。
特に保険会社の営業はいい例です。
先ほども紹介した通り、資産運用が必要なケースや目的は人によってばらばらです。
そのため、相談相手が提案する商品も、あなたに合ったものである必要があります。
株式投資がしたくて相談しても、場合によっては株以外の商品を提案されることもあります。
そのときに大切なのは、その商品が自分の目的や状況に合っていると納得できるかどうかです。
したがって、相談相手が投資商品のメリット・デメリットを客観的に説明し、透明性の高い商品を提案できるかどうかが重要です。
▼ 合わせて読みたい
30代の投資割合は約19%!資産形成…
株式投資の初心者はプロのFPに無料で相談

ここでは株式投資を始めるためにどこに相談するべきか、というお悩みについて紹介してきました。
記事の内容を簡単にまとめます。
・日本人だけが世界に取り残され、どんどん貧しくなっている
・モノの値段が上がるインフレ社会がすぐそこまで来ている
・株式投資について相談する前に、資産運用の目的をはっきりさせる
・資産運用を相談する相手は中立的な立場であるFPが望ましい
お金の問題は一人で悩まず、まずはFPに相談することをおすすめします。
「お金」「資産運用」「株式投資」に関わるお悩み解決ならぜひココザスへ!