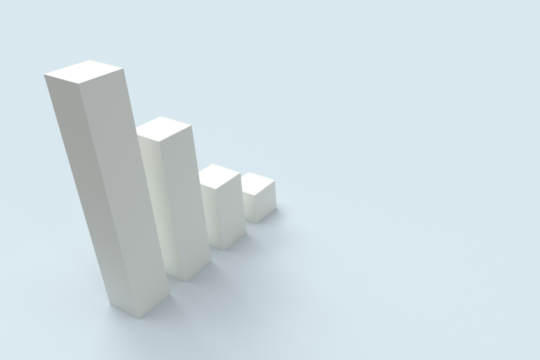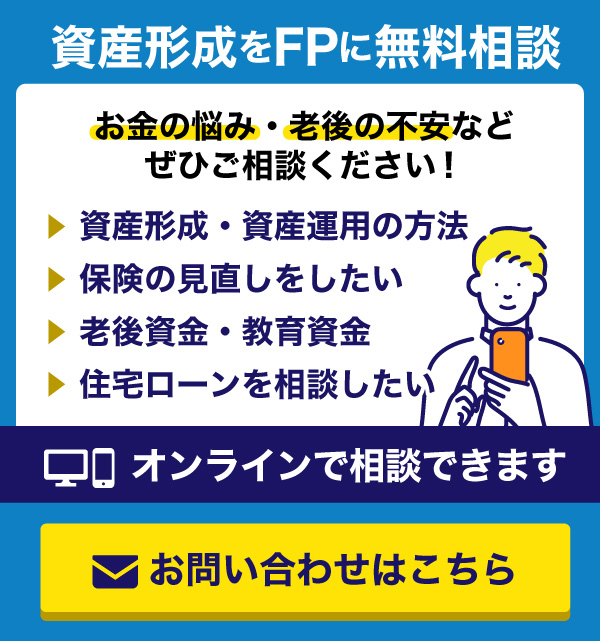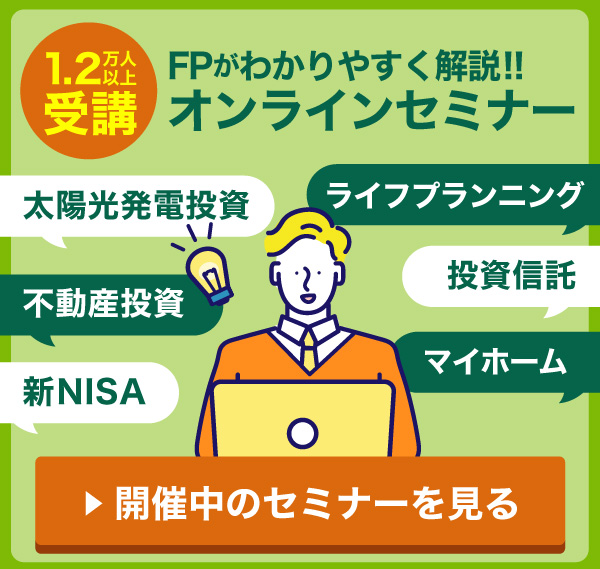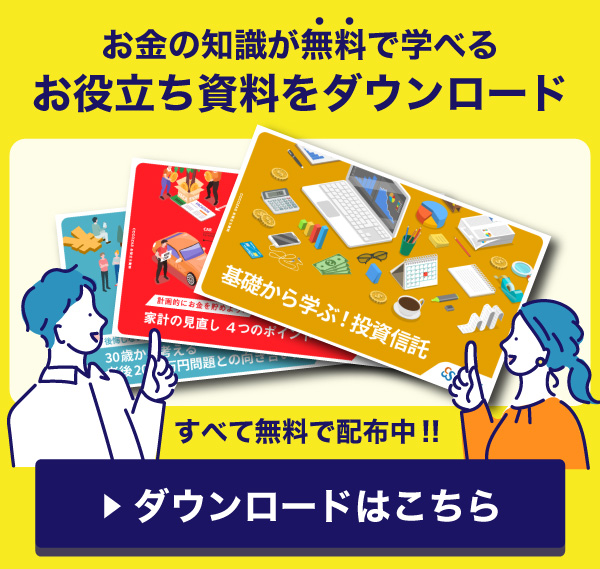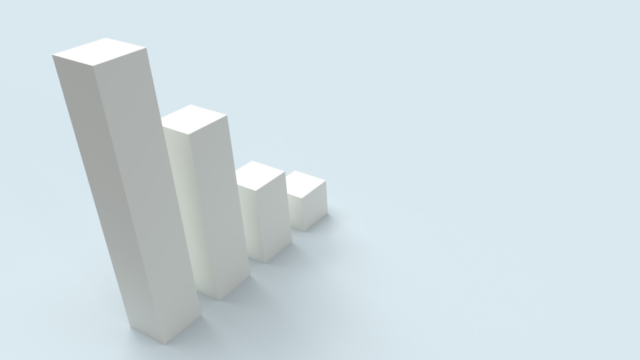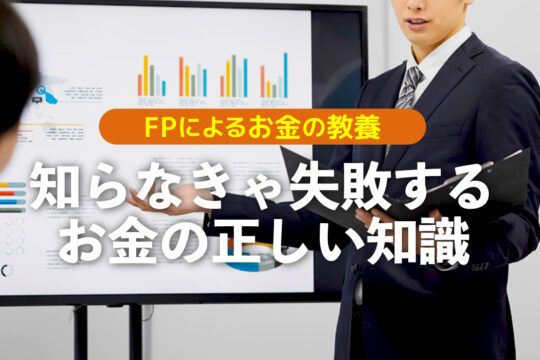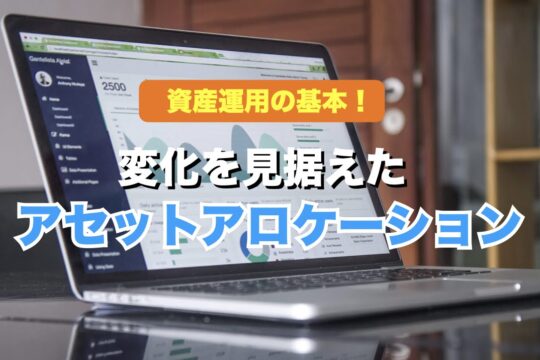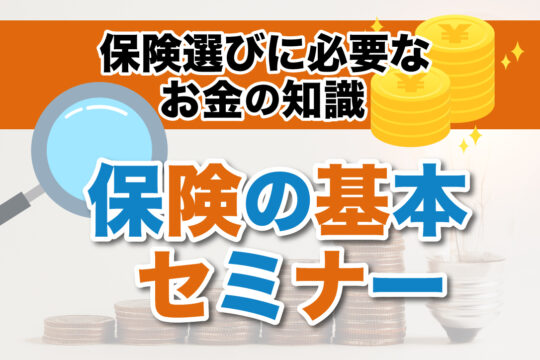もらえても喜べない場合も…分配金の仕組み

「分配金は、もらえればもらえるほどいいもの」
「投資信託は分配金で選ばなくちゃ」
と思っている人は意外と多いと思います。
実は、分配金は利息や配当金とは異なるため、「分配金=利益」とはならない場合があります。
また分配金が高い投資信託が良い投資信託であるとも限りません。
ここからは分配金の仕組みを詳しく解説しますので、正しく知識を身につけましょう。
分配金とは?
分配金とは、投資信託の純資産(運用資産)から投資家に還元されるお金のことです。
投資信託によって分配金が出るもの、出ないものがあり、分配金が出るかどうかは投資信託の「目論見書」で確認することができます。
また分配金が出る投資信託の中でも、分配金を出す回数や金額は商品ごとに異なります。
分配金を出す方針であっても、運用状況によっては支払われない場合や減額される場合もありますので注意が必要です。
分配金が出る投資信託を選ぶ際は、過去の分配金額の推移も確認しておくと良いでしょう。
また分配金が出る投資信託を購入する場合、「分配金を受け取るコース」か「分配金を受け取らずに再投資するコース」かを選ぶことができます。
それぞれのコースのメリットとデメリットは後ほど解説します。
〈参考記事〉
投資信託の基準価額・分配金とは?種類や受け取り方法などを徹底解説
株式の配当金との違い
分配金は運用会社が投資家に還元するお金のことを指しますが、配当金は、投資先の会社が株主に支払うお金のことです。
企業が得た利益の一部を配当金という形で渡します。一方分配金は、株式や債券、配当金などのすべての利益から還元されるお金であるため、お金の出所が異なります。
また、投資信託の分配金は、年に1回程度ですが、配当金の場合、企業によって異なりますが、年に1回〜2回ほど支払われます。
配当時期が異なる株を所有していれば、毎月配当金を受け取ることもできます。
さらに、分配金を支払った後の基準価額が個別元本を下回る部分は、「特別分配金」として非課税となりますが、配当金には20.315%の税率を掛けた税金が課せられるという違いもあります。
預貯金の利息との違い
預貯金の利息は、一定の割合で受け取れるのに対し、分配金は投資信託のファンドの運用状況によって大きく左右されます。
そもそも預貯金の利息は「銀行の預金額」を基準に算出されますが、投資信託の分配金は、運用実績に影響されます。
つまり、預貯金の利息は安定性があるのに対し、分配金は大きく増減する可能性が高いということです。
しかし、収益性は分配金の方が圧倒的に高い傾向にあります。金融機関の金利は、「0.001%〜0.2%」程度であるのに対し、投資信託の利回りは5%程度です。
大きな増減がある投資信託ですが、長期運用すれば利回りも安定するため、預貯金の利息より大きな利益を狙うこともできます。
普通分配金と特別分配金って?
分配金には、運用した利益から支払われる「普通分配金」と、元本の払い戻し金である「特別分配金」があります。
「元本の払い戻し金ってどういうこと?」と驚かれた方もいるかもしれません。
例えば毎月分配型の投資信託の場合、毎月出す分配金の金額があらかじめ決まっているため、相場が下落し利益が出ていない月でも分配金が支払われます。
その月は利益からは分配されず、元本を取り崩して分配金が支払われるのです。
以下は、普通分配金と特別分配金のイメージを表した図です。
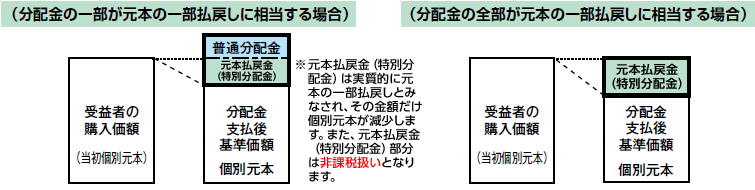
引用|楽天証券「毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意」
普通分配金は利益から支払われるため、課税されます。
一方、特別分配金は元本を受け取っているだけのため、非課税となります。
分配金の受取金額が毎月微妙に変わるのは、課税される普通分配金の割合が月によって異なるためです。
なお、NISA口座で投資信託を購入した場合は、通常課税される普通分配金が非課税になります。
分配金ありの投資信託を購入するメリット・デメリット
分配金のある投資信託を購入するメリット・デメリットは以下の表の通りです。
| メリット | デメリット |
| 定期的に利益が得られる | 複利効果を得にくい基準価額も下がり、利益が少なくなりやすい |
分配金ありの投資信託を購入するメリットは、定期的に利益が得られる点です。投資信託は、急激な価格変動が起これば、利益が無くなってしまうだけでなく、損失が生じる場合もあります。
しかし、分配金があれば、定期的に利益が得られるため、価格変動の不安要素をカバーしてくれるメリットがあります。
一方、運用益を分配金として支払ってしまうため、複利効果を得にくいデメリットがあります。複利効果とは、分配金や運用益を元本に加えることで、元本額を増やして利益を大きくさせる効果のことです。
長期運用することで元本が年々大きくなり、利益も増えていきますが、、分配金がある投資信託は、利益を分配金という形で支払ってしまうため複利効果が期待できません。
さらに、分配金を受け取ると、投資信託の1口価格(基準価格)も下がってしまうため、トータルの利益も少なくなります。
投資信託の分配金は、ファンドが保有している純資産をベースに支払われます。しかし、決済の度に支払われる純資産が減り、基準価格も下がってしまうことから、トータルの利益が少なくなりやすいというデメリットがあります。
分配金はいくらもらえる?分配金受取額の計算方法
「目論見書には、分配金額が30円って書いてある。この投資信託は毎月30円しかもらえないってこと?」と疑問をお持ちの方も多いでしょう。
目論見書などに記載されている分配金額は、一万口あたりの金額であるため、購入口数によって受け取れる金額は異なります。
分配金の受取額は、以下の計算で求めることができます。
(1)購入金額から購入時手数料を差し引いて、投資金額を求める
購入金額−(購入金額×手数料率)=投資金額
(2)保有口数を求める
(投資金額÷基準価額)×10,000=保有口数
(3)分配金受取額を求める
・(保有口数÷10,000)×1万口あたりの分配金額=税引き前分配金額
・税引き前分配金額×(100%−20.315%)=税引き後分配金額
例えば、以下のような場合を考えてみましょう。
・購入時手数料:3.3%
・基準価額:3,600円
・1万口あたりの分配金額:月額35円
(1)購入金額から購入時手数料を差し引いて、投資金額を求める
1,000,000円−(1,000,000円×3.3%)=967,000円
(2)保有口数を求める
(967,000円÷3,600円)×10,000=2,686,111口(端数切り捨て)
(3)分配金受取額を求める
(2,686,111÷10,000)×35円=9,401円(端数切り捨て)
9,401円×(100%−20.315%)=7,491円(端数切り捨て)
この場合、分配金受取額は月額約7,491円であると計算できます。
なお、実際には特別分配金部分は非課税になるため、実際の受取金額はこの通りとはならない場合があります。
利息や配当金とは異なる!分配金のよくある勘違い
分配金をもらえると得をしたような気分になってしまう方は多いと思います。
ですが、分配金の仕組み上、もらえても喜べない場合もあります。
分配金は預金の利息や株式の配当金とは異なります。
利息や配当金は、元本はそのままで、元本のプラスαとして支払われます。
一方、分配金は利益から支払われる場合もあれば、元本を切り崩して支払われる場合もあります。
つまり、利益が出ていない状況が続くと、自分のお金を自分で受け取っている状態になるのです。
必ずしもプラスαの収入が得られる訳ではないということを理解した上で、分配金を受け取るか再投資するかを選ぶことが大切です。
分配金ありの投資信託がおすすめの人・おすすめしない人
分配金ありの投資信託がおすすめの人・おすすめしない人は以下の表の通りです。
| 分配金ありの投資信託がおすすめの人 | 分配金ありの投資信託がおすすめしない人 |
| 定期的に利益を得たい人 | 少しでも利益を多く狙いたい人 |
分配金ありの投資信託がおすすめの人は、定期的に利益を得ておきたいと考える人におすすめです。
投資信託は、10年や20年と長期投資を行うことで利益が安定し、将来に備えることができる方法です。しかし毎月の生活の足しにしたいなど、定期的に利益を得て起きたい人は、分配金がある投資信託がおすすめです。
一方、将来を優先し、少しでも利益を多く狙いたい人は分配金なしの投資信託が良いでしょう。
分配金があると、複利効果が得られず、基準価額も下がってしまうため、トータルの利益が少なくなる可能性も高いためです。
もちろん、分配金はファンドの運用実績に影響します。分配金の有無だけでなく、ファンドの選定も重要です。
また、投資信託によって生活が左右される方は、ある程度資金力にゆとりが出てから始めるのことをおすすめします。
分配金再投資のメリット・デメリット

分配金を再投資すると、受け取るはずだった分配金(税引き後)で同じ投資信託が買い増しされます。
なお、買い増しはされるものの、購入時手数料はかかりません。
分配金再投資のメリットとデメリットは以下のとおりです。
分配金再投資のメリット
・複利効果が得られる
投資信託では、運用によって得られた運用益(分配金を含む)を投資した元本に上乗せして再投資することができます。
これを「複利(ふくり)」と言います。
この複利によって得られる効果を「複利効果」と呼び、複利効果は投資運用の時間が長くなればなるほど、大きくなる特徴があります。
分配金再投資のデメリット
・売却しない限り利益を受け取れない
再投資する場合は、運用中に得られる収入がないため、売却しない限り運用益を受け取ることができません。
分配金再投資に向いている人
分配金再投資には、「長期運用前提の人」が向いていると言えるでしょう。
なぜなら、複利効果は長期投資する方が効果が高いためです。
老後資金を見据えた20〜30年の長期運用を考えているなら、分配金再投資で複利の恩恵を受けるのがおすすめです。
また、長期運用前提であれば、分配金を再投資するだけでなく、分配回数が少ない商品を選ぶのも良いでしょう。
分配金受取のメリット・デメリット

毎月分配型投資信託の分配金受取を選んだ場合は、分配金が毎月普通預金口座に入金されます。
分配金受取のメリットとデメリットは以下のとおりです。
分配金受取のメリット
・定期的な収入を得られる
分配金受取を選択すると、定期的に一定額を受け取れるため、運用を続けながら収入を得ることができます。
そのため、何かの支払いに充てたり、生活費の足しにすることができます。
ただし、運用状況によっては分配金が支給されない場合や、減額される場合もあるため、注意が必要です。
分配金受取のデメリット
・複利効果の恩恵を受けられない
利益が出ない月は、分配金は元本を取り崩して支払われるため、投資元本が減ってしまいます。
分配金として受け取った元本は、普通預金に入金され運用されることはないため、複利効果や値上がり益を十分に得ることができません。
再投資している人と比べて、値上がり益が少なくなる可能性があります。
分配金受取が向いている人
分配金受取には、「定期的に収入を得たい人」が向いています。
受け取った分配金を何かの支払いに充てたり、使う目的がある人です。
また受け取った分配金を貯めて、別の投資信託を購入することで、分散投資の効果を得ることもできます。
まとめ

この記事では、分配金の再投資と受取のメリット・デメリットを解説しました。
メリット:複利効果が得られる
デメリット:売却しない限り利益を受け取れない
● 分配金受取
メリット:定期的な収入を得られる
デメリット:複利効果の恩恵を受けられない
分配金の仕組みを正しく知り、あなたの投資の目的に合った受け取り方法を選びましょう。
また投資信託を活用した運用についてより詳しい知識を身につけたい方は、セミナーに参加して情報収集していくのも良いでしょう。
また、お金の専門家でもあるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することもおすすめです。
あなたの年齢、家族構成、目的によって最適な運用方法は異なります。
プロの意見を参考にして、あなたにぴったりの効率の良い運用を考えましょう。
大切なお金に関する相談は信頼できるパートナーに
あなたに合う資産形成方法をFP(ファイナンシャルプランナー)に相談して、不安点をなくして投資の第一歩を踏み出してみませんか?
ココザスでは家計の見直しから、資産形成のご相談、投資信託に関する不明点の解消まで様々なご相談に無料で対応しております。
「自分にはどんな投資が合うんだろう?」「老後資金の準備で投資信託を活用したいけれど、いくら必要なのかな?」など…
気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。