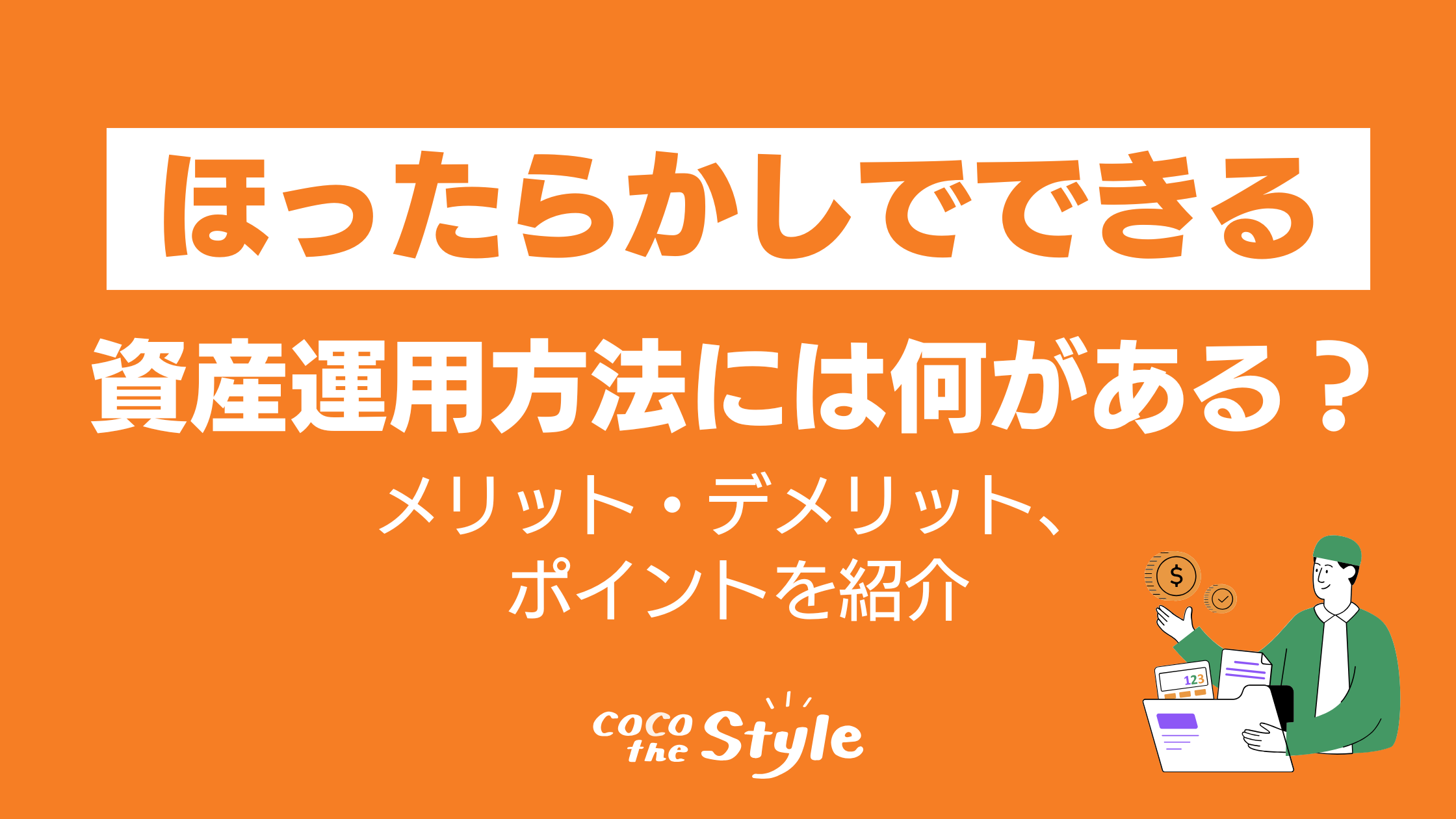一括投資をほったらかしでできる資産運用方法

一括投資をほったらかしでできる資産運用には以下の方法があります。
・投資信託
・ロボアドバイザー
・不動産クラウドファンディング
・国債
ほったらかしとはいえ、それぞれ運用方法が異なるのでひとつずつ確認しておきましょう。
Tweets by XDevelopers株式やETF投資
株式やETFは、一括でまとまった資金をほったらかし投資として活用できます。
株式投資では、将来の成長が期待できる企業や、配当金を継続的に出している安定した企業を選んでおけば、長期保有によって値上がり益(キャピタルゲイン)や配当収入(インカムゲイン)を狙うことができます。
ただし、個別株は業績や経済情勢によって大きく変動するため、リスク分散が重要です。
ETFは、株式や債券など複数の銘柄をまとめてパッケージ化した投資商品で、1本買うだけで自然に分散投資ができます。
例えば、「全世界株式ETF」や「米国株ETF」などは、広範囲な市場に投資することができ、長期の資産形成に向いています。
どちらもほったらかしで運用できる反面、定期的に経済ニュースをチェックしたり、年に1回程度は保有資産のバランスを見直したりする必要はあるため、ほったらかし過ぎるのには注意しましょう。
投資信託
投資信託とは、投資家から集めたお金を専門の運用会社がまとめて運用する仕組みです。投資対象は国内外の株式や債券、不動産などさまざまで、商品によってリスクやリターンも異なります。
一括で資金を投じれば、その後は運用会社が資産配分や売買などを代わりに行ってくれるため、自分で細かく管理する必要がありません。
特に「インデックス型」の投資信託は、手数料も低めで長期投資に適しており、ほったらかし投資に向いています。
ただし、価格は市場環境によって上下するため、短期的に大きく下がることもあります。また、専門の運用会社が運用するからと言って、必ず利益が出る保証はありません。最悪の場合は元本割れリスクが伴う点には注意しましょう。
また、信託報酬(保有中にかかる手数料)が商品ごとに異なるので、投資前にしっかり確認しましょう。長く保有するからこそ、手数料の差が将来の運用成績に大きく影響してきます。
投資信託は、少額からでも始められ、積立投資との相性も良いので、初めて資産運用をする人にとって非常に扱いやすい選択肢といえるでしょう。
ロボアドバイザー
ロボアドバイザーとは、AIやアルゴリズムを使って、あなたのリスク許容度や投資目的に合わせて自動で資産配分を行い、運用・リバランスまで自動でやってくれるサービスです。
代表的なサービスには「WealthNavi(ウェルスナビ)」や「THEO(テオ)」などがあります。
一括で資金を入金すれば、あとはロボアドバイザーが世界中の株式や債券などに分散投資してくれるため、自分で銘柄を選んだりタイミングを考える必要がありません。
運用中も自動で資産のバランス調整や利益の再投資を行ってくれるため、完全にほったらかしでも運用できます。
ただし、運用会社によって異なりますが手数料が年率1%程度かかる点には注意しなければいけません。
また、ロボアドバイザーであって市場全体が下落すれば資産が減るリスクも当然あります。
お任せできる特徴はありますが、投資である以上、元本保証ではないことは理解しておきましょう。
不動産クラウドファンディング
不動産クラウドファンディングとは、インターネットを通じて複数の投資家から少額ずつ資金を集め、その資金を使って不動産に投資する仕組みです。
投資家は運営会社を通じて、不動産から得られる家賃収入や売却益の一部を分配金として受け取ります。
実物不動産とは異なり、1口1万円〜10万円程度から投資できる案件が多く、手軽に不動産投資を始めることができます。
投資後は運営会社が物件の管理や運用を代行してくれるので、実物不動産のように物件の管理・修繕・空室対応・賃貸契約など、オーナーとしての手間や労力がかかりません。
また、物件の所有者はあくまで運営会社であり、固定資産税や管理費などのコストは運営側が負担するので、投資家は分配金の額だけを受け取る仕組みです。
ただし、運用期間があらかじめ決まっている案件が多く、その間は資金を引き出せない点には注意が必要です。また、元本保証はされておらず、空室や不動産価格の下落によって収益が減るリスクもあります。
国債
国債は国にお金を貸す形となり、満期まで保有することで元本の返済と利息を受け取れます。
満期まで保有すれば、基本的に元本割れのリスクはほとんどありません。特に日本国債は信用度が非常に高いため、安定した運用を望む人に向いています。
ただし、国債の利回りは株式や投資信託に比べてかなり低く、大きく資産を増やすことは難しいです。そのため、リスクを抑えて安定的に資産を守りたい場合には適した投資方法です。
また、国債は満期まで持つのが基本ですが、途中で売却も可能です。ただし、市場金利の変動によっては売却価格が購入価格を下回る場合があるため注意しましょう。
とはいえリスクが低いので他の資産と組み合わせて活用する場合におすすめな投資方法です。
ほったらかしで資産運用するメリット

ほったらかしで資産運用するメリットには以下の3点が挙げられます。
時間に捉われない
長期的な視点で資産形成ができる
心理的な負担軽減できる
ひとつずつ紹介します。
時間に捉われない
ほったらかしで資産運用する最大のメリットは時間に捉われない点です。
例えば、株価の値動きを毎日見ていると、それだけで精神的な負担が増えたり、生活リズムを乱したりしがちです。
しかし、ほったらかし運用なら一度投資をしてしまえば、基本的には何もせずに資産が育つのを待つだけになるでしょう。
その結果仕事や家庭、趣味に集中できるだけでなく、ストレス軽減にもつながります。結果的に心身の健康を守りながら長く投資を続けられるという大きなメリットがあるのです。
長期的な視点で資産形成ができる
ほったらかしの資産運用であれば、長期的な視点で資産形成ができるメリットがあります。
短期的な資産運用の場合は、日々の値動きに一喜一憂しやすく、元本割れする可能性も高まります。
ほったらかし投資は10年や⑳年と言った長期保有を前提にしているため、日々の細かい値動きに惑わされません。
長期間保有することで、利息や配当が再投資され、それがさらに利益を生む複利効果が最大限に働き、資産が雪だるま式に増えていきます。
実際に、多くの成功した投資家は長期的視点を持ち続けることで、大きな資産形成を実現しています。焦らず「時間を味方につける」ことで、安定的に資産を増やせるのがほったらかし投資の強みでもあるのです。
心理的な負担軽減できる
時間に捉われず、長期的な資産運用であれば最終的に心理的な負担軽減にもつながるメリットがあります。
資産運用で失敗している人の多くは、「損失に耐えられずやめてしまった」というケースが多いです。
投資を始めると、どうしても相場の上下に一喜一憂しがちです。この感情の揺れ動きは、時に冷静な判断を妨げ、不要な売買や損切りを誘発します。
ほったらかし運用では、基本的に自分で頻繁に売買しないため、そうした感情に振り回されにくいのが特徴です。
また、「ほったらかしで運用している」という意識が、投資に対する不安や焦りを軽減してくれるため、長期間投資を継続しやすくなり成功確率も上昇する傾向にあります。
ほったらかしは、心理的ストレスを減らして冷静に資産形成できることも大きなメリットと言えるでしょう。
ほったらかしで資産運用するデメリット

ほったらかしでの資産運用にはデメリットもあります。
相場の急変に対応できない
リバランスを怠るとリスクが偏る
利益などを再投資しないと効率が落ちる
ここでは3点紹介するのでひとつずつ確認しておきましょう。
相場の急変に対応できない
ほったらかし運用では、基本的に市場の動きをあまり見ないため、相場の急変や暴落時の対処が遅れるリスクがあります。
過去のリーマンショックやコロナショックのような世界的な金融危機が起きたとき、多くの資産が急落しました。
このような暴落が発生した際は保有資産を一部現金化するなどの対応が求められる場面もあります。
しかし、ほったらかし投資ではその判断が遅れ、結果的に大きな損失を抱えたまま耐えることになる場合もあります。
世界的な金融危機によって実際に元本割れして、資産運用から退場された方も多くいらっしゃいました。
「下がっても売らない」という姿勢で臨むのがほったらかし投資の前提なので、短期的な暴落に耐えられる金額での運用が求められます。
リバランスを怠るとリスクが偏る
ほったらかしにし過ぎた結果、リバランスを怠るとリスクが偏ってしまう可能性があります。
リバランスとは、資産配分を定期的に見直してバランスを整える作業のことです。
例えば株式と債券を50ずつで運用を始めたとしても、時間が経つと株式が値上がりして70%を占めるようになったりします。
そうなると、リスクの高い株式に偏ったポートフォリオになってしまい、本来のリスク管理ができていない状態になります。
リバランスを年1回でも行えば、リスクの偏りを修正し、運用効率を保つことが可能ですが、その作業さえ放置してしまうと、「ほったらかし」がかえってリスクを増やす原因になるデメリットがあります。
利益などを再投資しないと効率が落ちる
利益などを再投資しないと複利効果を活かせず投資効率が落ちてしまいます。
投資で得た配当金や分配金、売却益などをそのまま放置していると、お金が増えるペースが鈍くなることがあります。
資産運用で効果的なのは、「複利の力を活かすこと」であり、投資の基本とも言われています。
ほったらかしにしていることで、配当金や分配金を再投資せずに放置しておくと、複利効果が働かず、時間をかけても資産が思ったより増えないということにもつながるのです。
そのため、ほったらかしでの投資とはいえ、「完全放置」ではなく、「利益は定期的に再投資する」という方法を選択する必要があります。
初心者がほったらかしでよくあるミス

ここでは初心者がほったらかしでよくあるミスを4点紹介します。
・投資対象をよく理解せずに買ってしまう
・利益が出たからすぐ売る
・生活資金まで投資に回す
ひとつずつ確認しておきましょう。
下落時に不安になって売ってしまう
資産運用初心者の方は、下落時に不安になって売ってしまう傾向にあります。
これは「これ以上に損失が出る」という感情になってしまうためです。投資をしていると、価格が大きく下がる場面は必ず訪れます。初心者の多くがこのタイミングで「怖いから売ってしまおう」と判断してしまい、安値で損失確定するという失敗をします。
ほったらかし投資は、一時的な下落には反応しないことが前提で運用しなければいけません。長期で見れば価格は回復していくことも多いため、不安を感じてもすぐに動かない冷静さが必要です。
この冷静さを保つためには、無理のない金額で運用するのと同時に、生活に支障をきたさない資金力が大切となります。
投資対象をよく理解せずに買ってしまう
投資対象を理解せず買ってしまうと損をする可能性が高いです。特に近年ではネットで「おすすめの株」「おすすめの投資信託」などが掲載されています。
しかし、おすすめされたからと言っても、実際はどんな企業に投資しているのか、どんなリスクがあるのかを知らないまま投資してしまう人がいます。
高配当株だからといっても「利回りが高い=安全でお得」と勘違いする人も多いです。配当は企業業績に左右され、減配・無配になる可能性もあるうえ、高配当企業は成熟企業が多く、株価の成長性が低いこともあるのです。
そのため、おすすめというワードだけで投資対象を選ぶのではなく、最低限その商品がどんな仕組みで動いているのか、自分の資産がどこに投資されているのかは理解しておきましょう。
利益が出たからすぐ売る
含み益が出ると、「今のうちに利益を確定しておこう」と売ってしまいたくなる気持ちになる初心者が多いです。
しかし、資産運用の目的は「目先の利益」ではなく、「将来の資産形成」です。
長期的な資産形成を目的とした「ほったらかし投資」では、「その利益はまだ伸びる可能性があるもの」かどうかを冷静に判断することが重要です。
例えば10万円投資したETFが数ヶ月で12万円になったタイミングで、「+2万円の利益だし、今のうちに利確しよう」とする人も居ます。
もちろん損失がない時点でプラスですが、そのETFが経済回復や企業業績の上昇で数年後には20万円、30万円に成長することはよく見受けられます。
特に優良な投資商品は、時間をかけることで複利効果が働き、より大きな利益を生む可能性があるのです。短期的な利益で満足してしまうと、成長のチャンスを逃すことになりかねないため、利益を伸ばす計画で進めましょう。
生活資金まで投資に回す
生活資金まで投資に回すと損失がより多くなる可能性が高まるため注意しましょう。
資産運用初心者にありがちなのは「投資額を多くすればさらに増えるという考え」です。
生活費や急な出費に使うお金まで投資に入れてしまうと、思わぬトラブルが起きたときに対応できなくなります。
生活に必要なお金、緊急用の資金(生活費3〜6ヶ月分など)はしっかり確保しておき、資産運用はあくまで「余剰資金」で行うようにしましょう。
また、無理な資金で運用しなければ、精神的にも余裕を持ってほったらかし運用ができるようになります。
ほったらかしで資産運用する際のポイント

最後にほったらかしで資産運用する際のポイントを6点紹介します。
資産運用する際のポイント
- 投資目的と期間を明確にする
- 「短期の値動き」に耐える覚悟をしておく
- リバランスは最低でも年に1回行う
- 利益・損失に慣れておく(感情管理)
- 手数料・税金はしっかりチェックしておく
- ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談してから始める
ほったらかし投資を成功させるためのコツでもあるので、ひとつずつ確認しておきましょう。
投資目的と期間を明確にする
ほったらかし投資する際は、事前に投資目的と運用期間を決めておきましょう。
ほったらかし投資といっても、「なんのために、いつまでに、いくら必要か」というゴールを決めておかなければ、途中で方針がブレたり、損失を恐れて早く売ってしまう原因になります。
例えば「10年後に子どもの教育費として300万円必要」といったように、目的と期限が明確であれば、それに合った投資商品を選びやすくなります。
またゴールを設定しておけば、必要な運用額も把握できるため、今の金額で足りるのかの判断もできます。
一方目的が曖昧だと「今ちょっと上がったから売っちゃおうかな?」など感情的な判断が増え、長期投資のメリットを受けづらくなります。
「短期の値動き」に耐える覚悟をしておく
ほったらかし投資する際は、「短期の値動き」に耐える覚悟をしておきましょう。
株式や投資信託などの金融商品は、日々価格が変動します。短期的には大きく下がることもありますが、ほったらかし投資では「慌てて動かないこと」が重要です。
一時的に下落しても、企業の成長や経済全体の回復によって数年後に大きく値上がりすることも少なくありません。
例えばリーマンショック後の米国株は、大きく下落した後に10年で数倍に成長しています。
つまり、「一時的な含み損は想定内」と割り切れるかどうかが、ほったらかし投資の成功に直結するのです。最初のうちは少額で慣れていくのもおすすめします。
リバランスは最低でも年に1回行う
ほったらかし投資でもリバランスは最低でも年に1回行うようにしましょう。
先程もお伝えした通り、運用する時間が長くなるほど、最初の資産配分からバランスが変わるものです。
これを防ぐためにリバランスを行い、定期的に資産の配分を確認し、初期の目標に戻すことで、無駄なリスクを回避できます。
年に1回〜半年に1回程度の頻度で、保有資産の配分を見直しましょう。ロボアドバイザーや一部の投信では自動でリバランスしてくれるものもあります。
利益・損失に慣れておく(感情管理)
資産運用初心者の方には難易度が高いですが、利益・損失に慣れておくことが大切です。
投資では、値動きによる「含み益」や「含み損」が日常的に発生します。これに一喜一憂していると、冷静な判断ができなくなってしまうためです。
このように感情に左右されると、本来得られるはずだった利益を逃したり、逆に損を拡大してしまうこともあるでしょう。
そのためにも値動きに「慣れる」ことが大切です。どうしても経験による慣れとなってしまいますが、感情に振り回されずに済むようになるでしょう。
初心者の方は、最初から完璧を目指さず、経験を重ねることが感情管理の近道になります。
手数料・税金はしっかりチェックしておく
資産運用や投資には手数料・税金がかかるものなのでしっかりチェックしておきましょう。
投資で得た利益がそのまま手元に残るわけではありません。
知らない間に手数料や税金が差し引かれて、思ったほど資産が増えていなかったというケースも少なくないのです。
NISAやiDeCoを活用することで、一定額まで非課税で運用できるので、初心者ほど税制優遇を有効に使うことが大切です。
ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談してから始める
資産運用を始めるにあたって、自分だけで判断するのが不安な場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのがおすすめです。
特に、ほったらかし投資といっても「何を選んで、どう運用するか」は非常に重要で、人によって最適な方法が異なります。
特に自身でネットで調べ、おすすめな投資商品を選んで始める人は注意が必要です。
その投資商品が正しいのかの判断ができないうえ、誤った知識を身に付けてしまう可能性もあります。
ファイナンシャルプランナーは、あなたのライフプラン全体を踏まえたうえで、収支・資産状況・目標に合わせた投資の進め方を一緒に考えてくれるため、専門家の力を借りるところからスタートしましょう。
ココザスはファイナンシャルプランナーとして投資や資産運用のサポートを行っております。また、お客様の資産状況や家族構成、将来的なライフプランから適切な投資計画のアドバイスもしています。
さらに税金アドバイスや余剰金作りのための家計の見直し、保険やローンなどについての相談も承っておりますので、ぜひ一度ご相談下さいませ。
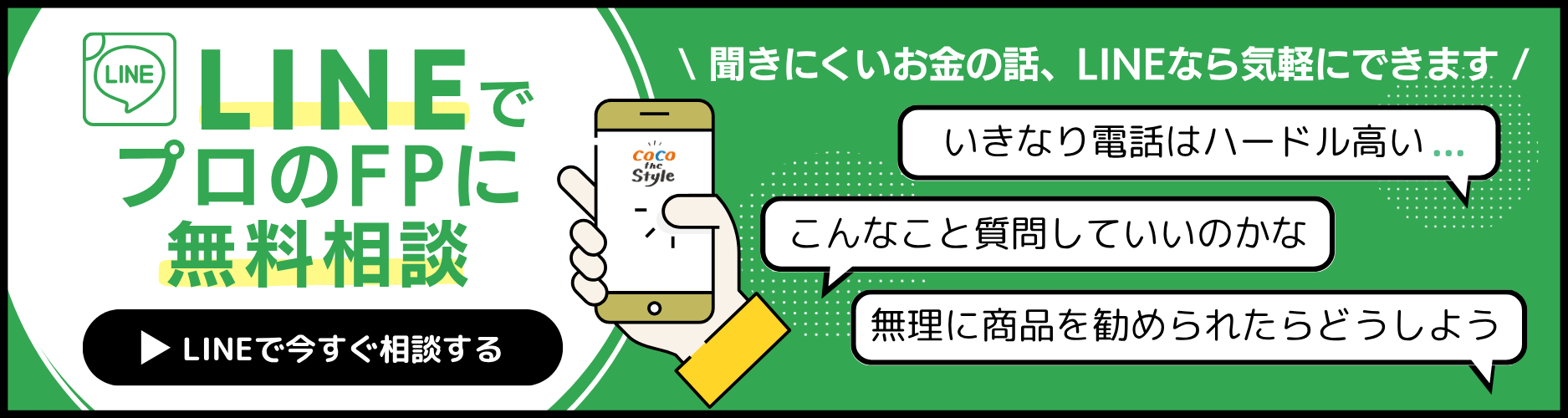
まとめ

一括投資によるほったらかし資産運用には、株式・ETF、投資信託、ロボアドバイザー、不動産クラウドファンディング、国債など、さまざまな選択肢があります。
忙しい日常の中でも手間をかけずに資産を増やせる反面、「完全放置」はリスク管理を怠る原因にもなりかねません。年に一度はポートフォリオを見直したり、利益を再投資するなど、最低限のチェックは必要です。
また、ほったらかし運用を成功させるには「自分がどのくらいリスクを取れるか」「どんな目的で資産を増やしたいのか」といった、自分自身の投資スタイルを理解することも重要です。
まずは無理のない範囲で小さく始め、自分に合った方法を試してみたい方もいらっしゃいますが、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談してみるのをおすすめします。